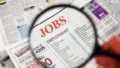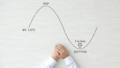「えっ、国民健康保険料ってこんなに高いの!?」
退職後に届いた国民健康保険料の通知書を見て、びっくりした経験はありませんか。
国民健康保険料は、世帯収入で決まる仕組みになっています。
つまり、あなた一人の収入だけでなく、家族全員の収入を合計した金額が保険料に影響するのです。

「家族みんなの収入が関係するなんて知らなかった…」と戸惑う方も多いでしょう。
この記事では、国民健康保険料が世帯収入でどう決まるのか、計算方法や節約のポイントまで詳しく解説します。
保険料の負担を少しでも減らしたい方は、ぜひ最後まで読んでくださいね。
国民健康保険料が世帯収入で決まる理由
国民健康保険料は、なぜ世帯収入で決まるのでしょうか。
まずはその仕組みから理解していきましょう。
世帯単位で計算される国民健康保険の基本

国民健康保険は、世帯単位で加入し、保険料も世帯ごとに計算されます。
これは社会保険とは大きく異なる点なんです。
社会保険の場合、個人ごとに給与から保険料が天引きされますよね。
しかし国民健康保険は、世帯主がまとめて家族全員分の保険料を支払う仕組みになっています。
たとえば、夫婦と子ども2人の4人家族で全員が国民健康保険に加入している場合、4人分の所得を合算して保険料が決まります。
世帯主に納付書が届き、世帯主が支払う責任を負うのです。

えっ?家族全員の収入が関係するの?知らなかったわ!

そうなんだにゃ!国保は世帯みんなで支え合う仕組みにゃ!
「世帯収入」ではなく「世帯所得」で計算される

ここで重要なポイントがあります。
国民健康保険料は、厳密には「世帯収入」ではなく「世帯所得」で決まります。
この違い、わかりますか?
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 収入 | 給与やボーナスなど、手元に入ってくるお金の総額 |
| 所得 | 収入から必要経費や控除を差し引いた金額 |
たとえば、年収300万円の人でも、給与所得控除を引くと所得は約190万円になります。
国民健康保険料を計算するときは、この「所得」の金額を使うのです。
世帯主が国保に入っていなくても納付義務がある
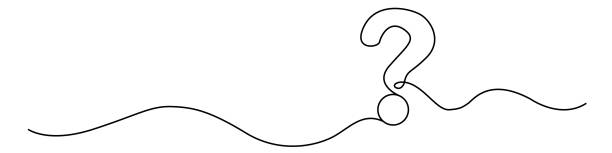
もうひとつ、驚くポイントがあります。
それは、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、納付義務は世帯主にあるということ。
たとえば、夫が会社員で社会保険に加入、妻がパートで国民健康保険に加入している場合。
妻の国民健康保険料の納付書は、世帯主である夫の名前で届きます。
夫は国保に入っていないのに、夫宛てに請求が来るのです!

うそ!?夫宛てに私の保険料の請求が来るの!?

そういうことにゃ!だから夫婦でしっかり確認する必要があるにゃ!
関連記事:https://sigomama.com/kokuho-dou-kimaru/
税務署から通知が来て青ざめる場合も...
世帯収入をもとにした国民健康保険料の計算方法
それでは、具体的に国民健康保険料がどう計算されるのか見ていきましょう。
計算方法を知れば、なぜこんなに高いのかが理解できるはずです。
所得割・均等割・平等割の3つの要素

国民健康保険料は、主に3つの要素で構成されています。
| 要素 | 計算方法 |
|---|---|
| 所得割 | 加入者の所得に応じて計算(所得が高いほど高額) |
| 均等割 | 加入者の人数に応じて一定額を加算 |
| 平等割 | 世帯ごとに固定額を加算(自治体による) |
この3つを合計した金額が、あなたの世帯の年間保険料になります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
計算式の基本
年間保険料 = 所得割 + 均等割 + 平等割
所得割は世帯全員の所得を合算して計算
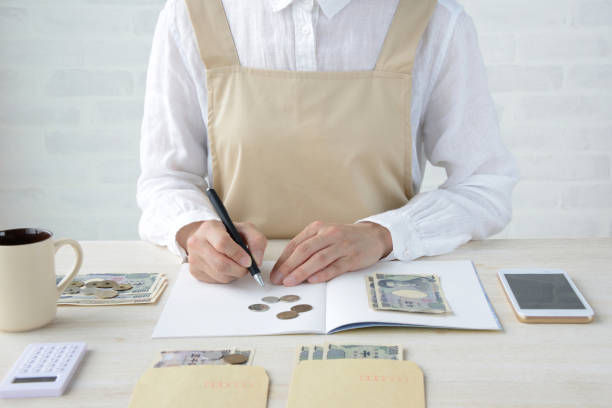
所得割は、国民健康保険料の中で最も大きな割合を占める部分です。
これは、世帯内の国保加入者全員の所得を合計し、そこに自治体が定めた料率をかけて計算します。
計算式はこうなります:
所得割の計算式
(前年の所得合計 - 基礎控除43万円) × 料率
たとえば、夫の所得が200万円、妻の所得が100万円の世帯の場合:
(200万円 + 100万円 - 43万円) × 料率 = 257万円 × 料率
この257万円に対して料率がかけられるため、家族の所得が多いほど保険料も高くなるのです。

うぅ…夫婦で働いてると、その分保険料も高くなるのね…

その通りにゃ…でも後で節約方法も教えるから安心するにゃ!
均等割と平等割で加入人数も影響する

所得割に加えて、均等割と平等割も保険料に含まれます。
均等割は、国民健康保険に加入している人数分だけかかります。
たとえば、1人あたり年間3万円の均等割なら、4人家族で4人とも国保加入なら:
3万円 × 4人 = 12万円
この金額が所得割に上乗せされます。
平等割は、世帯ごとに固定でかかる金額です。
ただし、平等割を設定していない自治体もあるため、お住まいの市区町村で確認してください。
関連記事:https://sigomama.com/kokuho-zennen-syotoku/
世帯収入が多いと国民健康保険料が高くなる理由
ここまでの説明で、なぜ国民健康保険料が高いのか、少しずつ見えてきたのではないでしょうか。
世帯収入(正確には世帯所得)が多いほど、保険料が跳ね上がる理由を整理しましょう。
所得が増えれば所得割も増える仕組み

国民健康保険料は、所得に比例して増える仕組みです。
所得が100万円の人と、所得が300万円の人では、保険料は3倍近く違ってきます。
しかも、世帯内の国保加入者全員の所得を合算するため、共働き世帯ほど保険料が高くなりやすいのです。
たとえば:
| 世帯構成 | 世帯所得 | 年間保険料の目安 |
|---|---|---|
| 単身(所得100万円) | 100万円 | 約8万円 |
| 夫婦(各100万円) | 200万円 | 約20万円 |
| 夫婦(各200万円) | 400万円 | 約50万円 |
※自治体や加入者数により異なります
世帯所得が倍になれば、保険料も倍以上になることがわかります。

えぇっ!共働きのほうが損するってこと!?

…まぁ、そういう面もあるにゃ。だから扶養に入れる選択肢も検討する価値があるにゃ。
子どもが多い世帯ほど均等割で負担増

もうひとつ、国民健康保険料が高くなる理由があります。
それは、子どもの人数分だけ均等割がかかること。
社会保険なら、子どもは扶養に入れば保険料はかかりません。
しかし国民健康保険には扶養の概念がないため、赤ちゃんでも1人分の均等割がかかるのです。
たとえば、均等割が1人3万円の自治体で、子どもが3人いる世帯なら:
3万円 × 3人 = 9万円
子どもの人数分だけで年間9万円も上乗せされることになります。
自治体によって保険料率が大きく異なる

同じ世帯収入でも、住んでいる自治体によって保険料が大きく変わることをご存知ですか?
国民健康保険は市区町村ごとに運営されているため、料率や均等割の金額が異なります。
たとえば、東京23区と地方都市では、同じ所得でも年間10万円以上の差が出ることもあるのです。
| 自治体 | 所得割料率の目安 |
|---|---|
| 東京23区 | 約7〜9% |
| 地方都市A | 約10〜12% |
| 地方都市B | 約6〜8% |
住んでいる場所によって負担が変わるため、市区町村のホームページで正確な料率を確認することが大切です。
関連記事:https://sigomama.com/kokuho-heikin-getsugaku/
世帯収入を抑えて国民健康保険料を節約する方法
国民健康保険料は世帯収入で決まるため、所得を抑える工夫をすることで保険料を減らせる可能性があります。
ここでは、合法的に保険料を節約する方法を紹介します。
扶養に入ることで保険料負担をゼロにする

もっとも効果的な方法は、家族の社会保険の扶養に入ることです。
扶養に入れば、自分の保険料負担はゼロになります。
ただし、扶養に入るには以下の条件を満たす必要があります。
| 条件 | 詳細 |
|---|---|
| 年収 | 130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満) |
| 続柄 | 配偶者、子ども、両親など |
| 同居・別居 | 配偶者や子どもは別居でも可、その他は原則同居 |
特にパートで働く主婦の方は、年収130万円の壁を意識して働くことで、社会保険の扶養に入り続けることができます。

130万円以内で働けば、保険料が0円になるのね!

その通りにゃ!扶養のメリットは大きいから検討する価値ありにゃ!
所得控除を活用して課税所得を減らす

扶養に入れない場合でも、所得控除を活用することで保険料を減らせます。
所得控除とは、所得から一定額を差し引ける制度のこと。
控除が増えれば課税所得が減り、結果として国民健康保険料も下がるのです。
活用できる主な所得控除
・医療費控除(年間10万円以上の医療費)
・社会保険料控除(国民年金・健康保険料)
・生命保険料控除(生命保険の保険料)
・地震保険料控除(地震保険の保険料)
・寄附金控除(ふるさと納税など)
・小規模企業共済等掛金控除(iDeCoなど)
特にiDeCo(個人型確定拠出年金)は、掛金が全額所得控除になるため、保険料削減と老後資金の準備を同時に行える優れた方法です。
世帯分離で保険料を分けて計算してもらう

最後に紹介するのは、世帯分離という方法です。
世帯分離とは、同じ住所に住んでいても、住民票上の世帯を別々にすることです。
世帯を分けることで、それぞれの世帯で独立して国民健康保険料が計算されます。
たとえば、親と同居している場合、親の所得が高いと世帯全体の保険料が高くなってしまいます。
しかし世帯分離すれば、あなたの所得だけで保険料が計算されるため、負担が軽くなる可能性があるのです。

世帯を分けるなんて、そんな方法もあるのね!

ただしデメリットもあるから、必ず専門家に相談してから決めるにゃ!
関連記事:https://sigomama.com/taisyoku-kokuho-tetuduki/
国民健康保険料が世帯収入で決まる仕組み。まとめ
国民健康保険料は、世帯全員の所得を合算して計算される仕組みです。
自分一人の収入だけでなく、家族全員の所得が影響するため、共働き世帯や子どもが多い世帯ほど保険料が高くなりやすいことがわかりました。

しかし、扶養に入る、所得控除を活用する、世帯分離を検討するなど、保険料を減らす方法はいくつもあります。
まずは自分の世帯がどれくらいの保険料を払っているのか確認し、節約できる方法がないか考えてみましょう。
国民健康保険料の仕組みを理解することで、無駄な支出を減らし、賢く節約できるようになります。
この記事で紹介した対策を参考に、あなたに合った方法を見つけてくださいね。

勇気が出てきたわ!明日、市役所に行ってくる!

その意気にゃ!きっと道は開けるにゃ!応援してるにゃ!
「あと数万円稼げたのに…」「扶養を外れた方が実は手元に多く残ったのに…」
数年後にそう気づいても、過ぎた時間は戻ってきません。
今ならオンラインで、「あなたの場合、いくら稼ぐのが一番お金が貯まるか」をプロが無料で試算してくれます。
家計の健康診断だと思って、早めに一度チェックしてみてください。浮いたお金で家族旅行に行けるかもしれませんよ!
👉 【無料】何度でも相談OK!世帯年収を最大化するライフプラン相談はこちら![]()