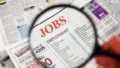「国民健康保険料って、最低でもいくらかかるの?」
収入が少ないときや無職のとき、保険料の最低額がどれくらいになるのか気になりますよね。
結論から言うと、国民健康保険料の最低額は年間2万円前後からになります。

ただし、この金額は7割軽減が適用された場合の最低ラインです。
軽減なしだと年間6万円~8万円程度になりますし、自治体によっても大きく異なります。
この記事では、国民健康保険料の最低額がどう決まるのか、軽減制度を適用した場合の具体的な金額、自治体別の違いまで詳しく解説します。
「できるだけ安く抑えたい」という方は、ぜひ最後まで読んでくださいね。
国民健康保険料の最低額はどう決まるのか
まずは、国民健康保険料の最低額がどのように決まるのか理解しましょう。
保険料の仕組みを知れば、なぜ最低額が発生するのかが見えてきます。
所得割は0円でも均等割は必ずかかる

国民健康保険料は、所得割と均等割の2つで構成されています。
| 保険料の種類 | 計算方法 | 所得が0円の場合 |
|---|---|---|
| 所得割 | 前年の所得に応じて計算 | 0円になる |
| 均等割 | 加入者1人あたり一定額 | 必ずかかる |
所得がゼロなら所得割は0円になりますが、均等割は収入に関係なく必ず発生します。
この均等割が、国民健康保険料の「最低額」を形成しているのです。

え?所得がゼロでも払うものがあるの?

そうにゃ!均等割は人数分かかるから、必ず負担が発生するにゃ!
均等割の金額は自治体ごとに異なる

均等割の金額は、自治体ごとに大きく異なります。
これは、国民健康保険が市区町村単位で運営されているためです。
たとえば、東京都内の自治体でも、以下のように差があります:
| 自治体例 | 医療分(年額) | 支援金分(年額) | 介護分(年額) |
|---|---|---|---|
| A区 | 約45,000円 | 約16,000円 | 約16,600円 |
| B市 | 約47,000円 | 約16,800円 | 約16,800円 |
| C市 | 約40,000円 | 約14,000円 | 約15,000円 |
※介護分は40~64歳のみ
同じ東京都内でも、年間で数千円~1万円以上の差が出ることがあります。
自分の住んでいる自治体の均等割額は、市区町村のホームページで確認できます。
40歳以上は介護分も加わり最低額が上がる

もうひとつ注意したいのが、40歳以上になると介護分が加わることです。
国民健康保険料は、以下の3つで構成されています:
国民健康保険料の内訳
・医療分:すべての年齢が対象
・後期高齢者支援金分:すべての年齢が対象
・介護分:40~64歳のみ対象
40歳未満なら、医療分+支援金分のみですが、40歳になると介護分が上乗せされます。
介護分の均等割は年間1万5,000円~1万7,000円程度なので、最低額も約1万5,000円高くなるのです。

うぅ…40歳になったら保険料が上がるのね…

仕方ないにゃ…でも軽減制度もあるから安心するにゃ!
関連記事:https://sigomama.com/kokuho-setai-syunyu/
税務署から通知が来て青ざめる場合も...
国民健康保険料の最低額は軽減後いくらになるか
ここからが本題です。
軽減制度を適用した場合、国民健康保険料の最低額は実際にいくらになるのでしょうか。
7割軽減なら年間2万円前後が最低額

所得が低い世帯には、7割・5割・2割の軽減制度があります。
この中でもっとも軽減率が高いのが7割軽減です。
7割軽減が適用されると、均等割が3割だけの負担になります。
たとえば、東京都内の自治体で単身・40歳未満の場合:
| 項目 | 軽減なし | 7割軽減 |
|---|---|---|
| 医療分 | 約45,000円 | 約13,500円 |
| 支援金分 | 約16,000円 | 約4,800円 |
| 合計 | 約61,000円 | 約18,300円 |
このように、7割軽減が適用されれば、年間2万円前後が最低額になります。
月額にすると約1,500円程度なので、かなり負担が軽くなりますね。

わぁ!月1,500円くらいなら安心ね♪

そうにゃ!7割軽減は大きいから、条件を確認するにゃ!
40歳以上は介護分が加わり3万円台になる

40歳以上になると、介護分が加わります。
先ほどの例に介護分を追加すると:
| 項目 | 軽減なし | 7割軽減 |
|---|---|---|
| 医療分 | 約45,000円 | 約13,500円 |
| 支援金分 | 約16,000円 | 約4,800円 |
| 介護分 | 約16,600円 | 約4,980円 |
| 合計 | 約77,600円 | 約23,280円 |
40歳以上で7割軽減が適用されると、年間2万3,000円前後が最低額になります。
月額にすると約1,900円です。
40歳未満より少し高くなりますが、それでも軽減なしと比べれば約7万円以上も安くなります。
未就学児がいれば均等割がさらに半額に

さらに、未就学児(小学校入学前)がいる世帯には特別な軽減措置があります。
未就学児の均等割は、すでに軽減された金額からさらに半額になるのです。
たとえば、7割軽減が適用されている世帯で未就学児が1人いる場合:
| 対象 | 7割軽減後 | 未就学児軽減後 |
|---|---|---|
| 大人 | 約18,300円 | 約18,300円 |
| 未就学児 | 約18,300円 | 約9,150円 |
未就学児1人あたり年間約9,000円も安くなります。
子どもが多い世帯ほど、この制度のメリットは大きくなりますね。
関連記事:https://sigomama.com/kokuho-musyoku-ikura/
国民健康保険料の最低額を実現する軽減の条件
それでは、この「最低額」を実現するための軽減制度は、どうすれば適用されるのでしょうか。
軽減の条件と手続き方法を詳しく見ていきましょう。
7割軽減は世帯所得43万円以下が条件

7割軽減を受けるための条件は、世帯所得が43万円以下であることです。
ここでいう「世帯所得」とは、国民健康保険に加入している家族全員の所得を合計した金額です。
たとえば:
7割軽減の対象例
・単身で無職(所得0円)→ 対象
・単身で所得40万円 → 対象
・夫婦で夫の所得40万円、妻の所得0円 → 対象
・単身で所得50万円 → 対象外(5割軽減の可能性あり)
所得43万円以下なら、ほぼ無条件で7割軽減が適用されます。
ただし、世帯主が国保に加入していなくても、世帯主の所得が計算に含まれる場合があるので注意してください。

世帯全体の所得で判断されるのね?

その通りにゃ!家族全員の所得を合計するから注意が必要にゃ!
5割・2割軽減の条件も確認しておく

7割軽減に該当しない場合でも、5割軽減や2割軽減が適用される可能性があります。
| 軽減率 | 世帯所得の基準 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円以下 |
| 5割軽減 | 43万円+(29.5万円×加入者数)以下 |
| 2割軽減 | 43万円+(54.5万円×加入者数)以下 |
たとえば、2人世帯で国保加入者が2人なら:
・7割軽減:43万円以下
・5割軽減:43万円+(29.5万円×2)=102万円以下
・2割軽減:43万円+(54.5万円×2)=152万円以下
このように、人数が増えるほど軽減の対象範囲も広がります。
軽減を受けるには住民税申告が必須

軽減制度を受けるために、住民税の申告を忘れずに行いましょう。
所得がゼロでも、申告しないと「所得不明」として扱われ、軽減が適用されません。
住民税の申告は、毎年2月16日~3月15日の確定申告期間に、市区町村の窓口で行えます。
住民税申告の手順
1. 市区町村の税務課窓口へ行く
2. 「所得がゼロ」と申告する
3. 申告書を提出する
4. 軽減が自動的に適用される
この申告を忘れると、軽減が受けられず、年間6万円~8万円の保険料を払うことになります。
無職の方や収入が少ない方は、必ず住民税申告を行うことを忘れないでください。

住民税申告、忘れずにやらなくちゃね!

そうにゃ!申告するだけで年間4万円以上も変わることもあるにゃ!
関連記事:https://sigomama.com/kokuho-dou-kimaru/
国民健康保険料の最低額を知って賢く節約。まとめ
国民健康保険料の最低額は、7割軽減が適用されれば年間2万円前後になります。
40歳以上でも年間2万3,000円程度、月額にすると約2,000円以下です。

ただし、この最低額を実現するには、住民税申告を忘れずに行うことが必須です。
申告しないと軽減が受けられず、年間6万円~8万円の保険料を払うことになってしまいます。
国民健康保険料は自治体によって金額が大きく異なるため、自分の住んでいる市区町村のホームページで必ず確認してください。
「○○市 国民健康保険料 計算」で検索すれば、試算できるサイトが見つかります。
この記事で紹介した方法を参考に、保険料の負担を少しでも減らしてくださいね。

最低額の仕組みがよくわかったわ!すぐに確認してみる♪

その意気にゃ!賢く節約して、無理のない生活を送るにゃ!
「あと数万円稼げたのに…」「扶養を外れた方が実は手元に多く残ったのに…」
数年後にそう気づいても、過ぎた時間は戻ってきません。
今ならオンラインで、「あなたの場合、いくら稼ぐのが一番お金が貯まるか」をプロが無料で試算してくれます。
家計の健康診断だと思って、早めに一度チェックしてみてください。浮いたお金で家族旅行に行けるかもしれませんよ!
👉 【無料】何度でも相談OK!世帯年収を最大化するライフプラン相談はこちら![]()