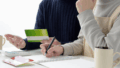「国民健康保険料が高すぎて払えない…」
「減免制度があるって聞いたけど、本当?」
「どうやって申請すればいいの?」
国民健康保険料の負担に悩んでいる方は多いでしょう。
実は、国民健康保険料には減免制度があるんです。
所得が低い世帯、出産を控えた方、災害に遭われた方など、様々な状況に応じた減免制度が用意されています。
この記事では、国民健康保険料の減免制度について、制度の種類、対象者、申請方法、必要書類まで詳しく解説します。
減免制度を正しく理解して、保険料の負担を軽くしましょう。

えっ?国民健康保険料って減免できるの?知らなかった!

実はあるんだにゃ!知らないと損するから、しっかり覚えるにゃ!
国民健康保険料の減免制度とは?4つの種類を解説
まず、国民健康保険料の減免制度にはどんな種類があるのか見ていきましょう。
主に4つの制度があり、それぞれ対象者や条件が異なります。
低所得世帯向けの均等割額軽減制度

最も多くの方が該当するのが、低所得世帯向けの均等割額軽減制度です。
前年の世帯所得が一定の基準以下の場合、保険料の均等割額が7割、5割、2割のいずれかで軽減されます。
この制度の大きな特徴は、申請不要で自動的に適用されることが多い点です。
住民税の申告さえしていれば、自治体が自動的に判定して軽減してくれるのです。
軽減の基準は以下の通りです。
| 軽減割合 | 世帯所得の基準(令和6年度) |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
| 5割軽減 | 43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
| 2割軽減 | 43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
たとえば、単身世帯で給与所得者が1人の場合、前年所得が43万円以下なら7割軽減の対象になります。
産前産後期間の保険料減額制度

出産を控えた方に嬉しいのが、産前産後期間の保険料減額制度です。
出産予定月の前後一定期間の保険料が減額されます。
具体的な減額期間は以下の通りです。
- 単胎妊娠の場合:出産予定月の前月から4か月分
- 多胎妊娠の場合:出産予定月の3か月前から6か月分
たとえば、8月に出産予定の場合、単胎なら7月から10月までの4か月分が減額対象になるのです。
ただし、減額額は所得割額の部分が中心で、均等割額は減額されないことが多いです。
また、この制度は申請が必要なので、妊娠が分かったら早めに手続きしましょう。
旧被扶養者に対する減免制度

65歳から74歳の方で、会社を退職して社会保険から国保に切り替えた方が対象になるのが、旧被扶養者に対する減免制度です。
特に、配偶者が後期高齢者医療制度(75歳以上の保険)に移行したため、それまで扶養されていた方が国保に加入するケースが該当します。
この制度では、以下の減免が受けられます。
- 所得割額:全額免除
- 均等割額:2年間は5割減額
つまり、保険料がかなり軽減されるのです。
ただし、この制度も申請が必要です。
資格喪失証明書など、前の保険からの切り替えを証明する書類が必要になります。
災害や失業など特別な事情による減免

災害に遭われた方や、会社の倒産・解雇などで失業された方には、特別な事情による減免制度があります。
この制度では、一時的に生活が困難になった場合、保険料の減額や免除が受けられます。
対象となる「特別な事情」には、以下のようなものがあります。
- 地震、火災、風水害などの災害で住宅や家財に損害を受けた
- 世帯主が死亡、または重度の障害を負った
- 会社の倒産や解雇により失業した
- 事業の休廃止や著しい損失があった
- 干ばつや冷害などで農作物に被害を受けた
減免の割合は、所得の減少度合いや被害の程度によって決まります。
重要なのは、納期限の7日前までに申請しなければならない点です。
納期限を過ぎてからの申請は認められないことが多いので、早めに相談しましょう。

わぁ!こんなにたくさん減免制度があるのね!知らなかったわ!

そうなんだにゃ!自分が該当する制度がないか、しっかり確認するといいにゃ!
税務署から通知が来て青ざめる場合も...
国民健康保険料の減免申請方法と必要書類
減免制度の種類が分かったところで、次は実際の申請方法を見ていきましょう。
制度によって申請の有無や必要書類が異なるので、注意が必要です。
低所得世帯の軽減は申請不要で自動適用

低所得世帯向けの均等割額軽減は、申請不要です。
住民税の申告さえしていれば、自治体が自動的に判定して軽減してくれます。
ただし、住民税の申告をしていない場合は軽減されないので注意しましょう。
所得がゼロでも、必ず住民税の申告をすることが大切です。
申告は毎年2月16日から3月15日の間に行いますが、所得がない場合は年中いつでも申告できます。
もし申告していない場合は、すぐに市区町村の税務課で申告しましょう。
住民税申告のポイント
- 所得がゼロでも申告が必要
- 市区町村の税務課で申告
- 申告後、自動的に保険料が軽減される
- 遡って軽減されることもある
産前産後期間の減額は市区町村窓口で申請

産前産後期間の減額は、申請が必要です。
市区町村の国民健康保険課で申請を行います。
必要な書類は以下の通りです。
- 国民健康保険証
- 母子健康手帳(出産予定日が確認できるページ)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 印鑑(認印可)
申請は出産予定日の6か月前から可能です。
出産後でも申請できますが、遡って適用される期間には制限があることが多いので、早めに申請するのがおすすめです。
申請すると、該当期間の保険料通知書が再発行され、減額後の金額が反映されます。
旧被扶養者の減免は資格喪失証明書が必要

旧被扶養者の減免も、申請が必要です。
市区町村の国民健康保険課で申請を行います。
必要な書類は以下の通りです。
- 国民健康保険証
- 健康保険資格喪失証明書
- 本人確認書類
- 印鑑
- 世帯主のマイナンバーが分かるもの
特に重要なのが健康保険資格喪失証明書です。
これは、前の保険(社会保険や後期高齢者医療制度)を脱退したことを証明する書類です。
配偶者の会社や、年金事務所、健康保険組合などで発行してもらえます。
この証明書がないと申請できないので、国保に切り替える際は必ず取得しましょう。

あっ!資格喪失証明書って、国保の加入手続きで使った書類のことね!

その通りだにゃ!加入手続きの時に使った証明書を、減免申請でも使うんだにゃ!
国民健康保険料の減免申請で注意すべきポイント
減免申請をする際に注意すべきポイントを見ていきましょう。
これを知っておくと、スムーズに申請できます。
減免は申請した月以降の保険料が対象

多くの自治体では、減免は申請した月以降の保険料が対象になります。
つまり、遡って過去の保険料を減免してもらうことは難しいのです。
たとえば、10月に失業して生活が苦しくなったのに、申請したのが12月だった場合。
この場合、12月以降の保険料は減免されますが、10月と11月分は減免されないことが多いのです。
ですから、困ったらすぐに相談・申請することが大切です。
「まだ大丈夫」と先延ばしにせず、早めに動きましょう。
滞納がある場合でも減免申請は可能

「保険料を滞納しているから、減免申請できないのでは?」と心配する方もいるでしょう。
しかし、滞納があっても減免申請は可能です。
むしろ、滞納している方こそ減免制度を利用すべきなのです。
減免が認められれば、今後の保険料負担が軽くなり、滞納を解消しやすくなります。
ただし、滞納分の保険料は減免されないことが多いです。
減免されるのは、申請後の保険料だけです。
滞納分については、分割払いの相談ができるので、窓口で相談してみましょう。
自治体によって減免の基準や内容が異なる
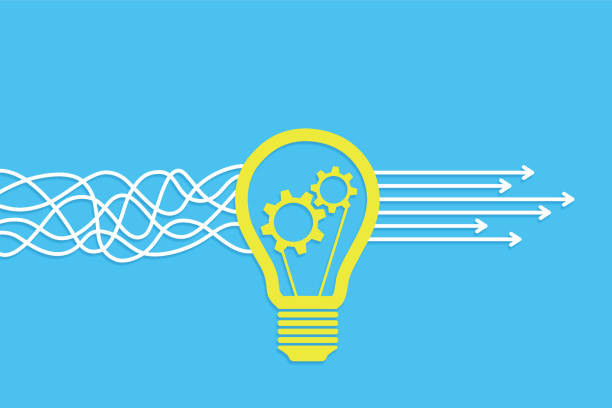
国民健康保険料の減免制度は、自治体によって基準や内容が異なることがあります。
この記事で紹介した内容は一般的なものですが、詳細は各自治体で確認する必要があります。
たとえば、所得基準の金額や、減免の割合、申請期限などが自治体ごとに違うことがあるのです。
ですから、必ず自分が住んでいる市区町村の窓口で確認しましょう。
自治体のホームページにも詳しい情報が載っていることが多いので、事前に調べてから窓口に行くとスムーズです。
また、窓口では丁寧に説明してもらえるので、分からないことは遠慮なく質問しましょう。
自治体に確認すべきポイント
- 自分が該当する減免制度はあるか
- 必要な書類は何か
- 申請期限はいつまでか
- 減免の割合や金額はどれくらいか
- 申請後、いつから適用されるか
国民健康保険料の減免以外の負担軽減策
減免制度以外にも、国民健康保険料の負担を軽くする方法があります。
ここでは、その他の負担軽減策を紹介します。
分割納付で無理なく支払う

一括で保険料を払うのが難しい場合は、分割納付の相談ができます。
市区町村の窓口で相談すれば、無理のない金額で分割払いにしてもらえることがあります。
たとえば、年間24万円の保険料を一括で払えない場合、月2万円ずつの分割払いにしてもらえるのです。
分割納付にしても延滞金が発生することがありますが、滞納して差し押さえになるよりは遥かにマシです。
困ったら、まず窓口で相談しましょう。
社会保険への切り替えを検討する

国民健康保険料が高いと感じる場合、社会保険(健康保険)への切り替えを検討するのも一つの方法です。
会社の社会保険に加入すれば、保険料は会社と折半になり、負担が軽くなることがあります。
また、扶養に入れる条件を満たせば、扶養家族として加入でき、自分の保険料負担がゼロになります。
パートで働いている方は、労働時間を増やして社会保険に加入する基準を満たす方法もあります。
詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

高額療養費制度を活用する

保険料とは別の話ですが、高額療養費制度も覚えておくと便利です。
これは、医療費が高額になった場合、一定額を超えた分が払い戻される制度です。
たとえば、入院して医療費が100万円かかった場合でも、実際の自己負担は所得に応じて8万円〜25万円程度で済むのです。
この制度を知っていれば、「医療費が払えない」という不安が軽くなります。
国民健康保険に加入していれば、誰でも利用できる制度なので、覚えておきましょう。

減免以外にも、いろんな方法があるのね!知っておくと安心だわ♪

その調子にゃ!困ったときの選択肢を知っておくことが大事だにゃ!
国民健康保険料の減免制度を活用して負担を軽くしよう:まとめ
国民健康保険料には、様々な減免制度が用意されています。
低所得世帯向けの軽減、産前産後の減額、旧被扶養者の減免、災害や失業時の特別減免など、状況に応じて利用できる制度があるのです。
特に、低所得世帯向けの軽減は申請不要で自動適用されるため、住民税の申告さえしていれば誰でも利用できます。
その他の減免制度は申請が必要なので、該当する方は忘れずに手続きしましょう。
重要なのは、困ったらすぐに相談することです。
減免は申請した月以降が対象になることが多いため、早めの行動が大切です。
自治体の窓口では丁寧に説明してもらえるので、分からないことは遠慮なく質問してください。
保険料の負担で悩んでいる方は、ぜひ減免制度を活用して、生活を少しでも楽にしてくださいね。

よく分かったわ!困ったらすぐに自治体に相談してみるわね♪

その調子にゃ!一人で抱え込まないで、どんどん相談するにゃ!応援してるにゃ!
「あと数万円稼げたのに…」「扶養を外れた方が実は手元に多く残ったのに…」
数年後にそう気づいても、過ぎた時間は戻ってきません。
今ならオンラインで、「あなたの場合、いくら稼ぐのが一番お金が貯まるか」をプロが無料で試算してくれます。
家計の健康診断だと思って、早めに一度チェックしてみてください。浮いたお金で家族旅行に行けるかもしれませんよ!
👉 【無料】何度でも相談OK!世帯年収を最大化するライフプラン相談はこちら![]()