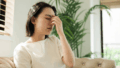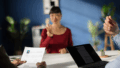「自己都合で会社を辞めたから、国民健康保険料の軽減は無理よね…」
諦めていませんか。
実は、自己都合退職でも国民健康保険料の軽減を受けられる場合があるんです。
会社都合退職だけが対象というわけではありません。「正当な理由のある自己都合退職」であれば、軽減制度を利用できます。

この記事では、自己都合退職でも国民健康保険料の軽減を受けられる条件、申請方法、注意点まで詳しく解説します。
退職後の保険料負担を少しでも減らしたい方は、ぜひ最後まで読んでくださいね。
自己都合退職でも国民健康保険の軽減は受けられるのか
結論から言うと、正当な理由のある自己都合退職なら軽減を受けられます。
ただし、単なる転職やキャリアアップを目的とした退職では対象外です。
会社都合退職と自己都合退職の違い

まず、会社都合退職と自己都合退職の違いを理解しましょう。
会社都合退職とは、会社の倒産や解雇、雇い止めなど、労働者の意思に関係なく退職せざるを得なくなった場合を指します。
一方、自己都合退職とは、労働者自身が退職を希望して会社を辞めた場合です。
国民健康保険料の軽減制度は、基本的に「非自発的失業者」が対象です。つまり、会社都合退職が中心となります。
正当な理由のある自己都合退職なら対象になる

ただし、すべての自己都合退職が対象外というわけではありません。
「正当な理由のある自己都合退職」と認められれば、会社都合退職と同じように軽減を受けられるんです。
正当な理由とは、以下のようなケースを指します。
正当な理由のある自己都合退職の例
・病気やけがで働けなくなった
・家族の介護や看護のため退職せざるを得なかった
・事業所の移転で通勤が困難になった
・長時間労働やパワハラ、セクハラなど職場環境が著しく悪化した
・配偶者の転勤で転居が必要になった
こうした「やむを得ない事情」での退職は、形式上は自己都合でも、実質的には退職せざるを得なかったとみなされます。

えぇっ!?介護で辞めた場合も軽減してもらえるの!?

そうにゃ!やむを得ない理由があれば、自己都合でも軽減の対象になるにゃ!
離職理由コードで判断される

あなたの退職が軽減対象になるかどうかは、「離職理由コード」で判断されます。
離職理由コードとは、雇用保険の受給資格者証に記載されている2桁の番号です。
このコードを見れば、会社都合なのか、正当な理由のある自己都合なのか、それとも一般的な自己都合なのかが分かります。
| 区分 | 離職理由コード | 軽減対象 |
|---|---|---|
| 会社都合退職 | 11、12、21、22、31、32 | ◯ |
| 正当な理由のある自己都合退職 | 23、33、34 | ◯ |
| 一般的な自己都合退職 | 40番台以降 | × |
あなたの離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかであれば、軽減を受けられます。
税務署から通知が来て青ざめる場合も...
自己都合退職で国民健康保険の軽減を受ける条件
ここからは、自己都合退職で軽減を受けるための具体的な条件を詳しく見ていきましょう。
雇用保険に加入していたことが必須

まず、雇用保険に加入していたことが条件です。
雇用保険に加入していなかった場合、残念ながらこの軽減制度は利用できません。
パートやアルバイトで雇用保険に入っていなかった方は、この軽減ではなく、低所得による軽減制度を利用することになります。
離職時の年齢が65歳未満であること

次に、離職時の年齢が65歳未満である必要があります。
65歳以上で退職した場合は、この軽減制度の対象外となります。
ただし、65歳以上の方には別の軽減制度(後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減など)がある場合もあるので、窓口で相談してみましょう。

65歳未満っていう条件があるのね。知らなかったわ…

うん、年齢条件があるにゃ。でも65歳以上の人には別の支援制度もあるから、諦めないでにゃ!
国民健康保険に加入していること

当然ですが、国民健康保険に加入していることが条件です。
退職後に家族の社会保険の扶養に入った場合や、任意継続を選択した場合は、国民健康保険に加入していないため、この軽減は受けられません。
国民健康保険の軽減を受けたい場合は、退職後に国保へ加入する手続きが必要です。
軽減を受けるための3つの条件まとめ
・雇用保険に加入していた
・離職時の年齢が65歳未満
・国民健康保険に加入している
自己都合退職による国民健康保険の軽減内容
条件を満たせば、どのくらい保険料が安くなるのでしょうか。
ここでは、軽減の具体的な内容を見ていきます。
前年の給与所得を30%として計算される

軽減制度では、前年の給与所得を30%として計算してもらえます。
通常、国民健康保険料は前年の所得をもとに計算されるため、退職直後は収入がないのに高額な保険料を請求されてしまいます。
しかし、この軽減を使えば、前年の給与所得を実際の7割減として扱ってもらえるため、保険料が大幅に安くなるのです。
具体例
前年の給与所得が300万円だった場合:
通常→300万円をもとに保険料計算
軽減適用後→90万円(300万円×30%)をもとに保険料計算
約70%の負担軽減!
軽減期間は最大約2年間

この軽減は、離職日の翌日の属する月から翌年度末まで適用されます。
たとえば、2025年6月30日に退職した場合、2025年7月から2026年3月まで(9か月間)が軽減期間です。
さらに、2026年4月以降も再就職していなければ、2027年3月まで軽減が延長されます。つまり、最大で約2年間の軽減が可能です。

わぁ!最大2年間も軽減してもらえるのね♪

そうにゃ!再就職活動中の負担を大きく減らせる制度にゃ!
給与所得以外は軽減対象外

注意すべきは、給与所得のみが軽減対象という点です。
事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得などは軽減の対象になりません。
たとえば、会社員として働いていた給与所得は30%として計算されますが、副業の事業所得や不動産収入は通常通り計算されます。
自己都合退職で国民健康保険の軽減を受ける申請方法
ここからは、実際に軽減を受けるための申請方法を解説します。
必要書類を準備する

まず、申請に必要な書類を準備しましょう。
必要書類
・雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)の原本
・国民健康保険証
・マイナンバーカード(または通知カード)
・本人確認書類(運転免許証など)
・印鑑(自治体によっては不要)
もっとも重要なのは「雇用保険受給資格者証」です。
この書類に記載されている離職理由コードで、軽減対象かどうかが判断されます。ハローワークで失業保険の手続きをすると発行されるので、必ず持参しましょう。
市区町村の国民健康保険担当窓口で申請
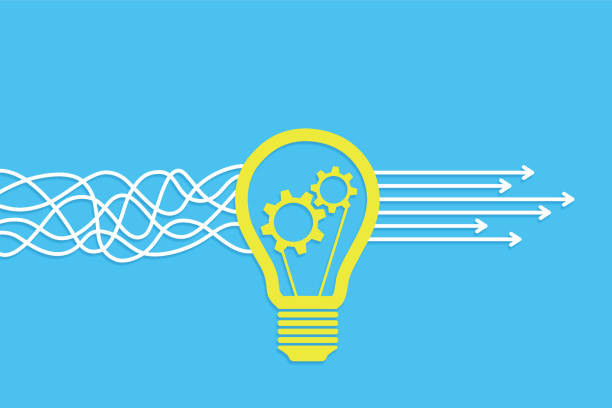
必要書類を揃えたら、お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口へ行きましょう。
窓口で「失業による保険料軽減の申請をしたい」と伝えれば、担当者が手続きを案内してくれます。
申請書に必要事項を記入し、雇用保険受給資格者証を提示すれば、手続きは完了です。
申請のタイミングと注意点

軽減申請は、なるべく早く行うことが大切です。
というのも、軽減は申請した月から適用されるため、申請が遅れるとその分損をしてしまいます。
退職後、国民健康保険に加入したらすぐに申請しましょう。遡っての適用はできません。
また、再就職して社会保険に加入したら、軽減は終了します。その場合は、国民健康保険の脱退手続きも忘れずに行いましょう。

申請って難しいのかしら…?

全然難しくないにゃ!窓口で「失業で保険料を安くしたい」って言えば、担当者が丁寧に教えてくれるにゃ!
国民健康保険の軽減と自己都合退職。諦めずに申請しよう:まとめ
自己都合退職だからといって、国民健康保険料の軽減を諦める必要はありません。
正当な理由のある自己都合退職であれば、会社都合退職と同じように軽減を受けられます。

大切なのは、離職理由コードを確認し、対象になるかどうかをチェックすること。
そして、対象になるなら早めに申請することです。
この記事のポイント
・正当な理由のある自己都合退職なら軽減を受けられる
・離職理由コードが23、33、34なら対象
・会社都合退職(11、12、21、22、31、32)も対象
・前年の給与所得を30%として計算してもらえる
・軽減期間は最大約2年間
・申請は市区町村の国民健康保険担当窓口で行う
・申請は早めに行うことが大切
失業中は経済的に不安な時期です。
使える制度はしっかり活用して、少しでも負担を減らしましょう。
もし申請方法が分からなければ、市区町村の窓口で相談すれば丁寧に教えてもらえます。
一人で悩まず、まずは相談してみてくださいね。

よく分かったわ!自己都合退職でも軽減してもらえる場合があるのね。早速確認してみるわ♪

その調子にゃ!制度をしっかり使って、安心して再就職活動に取り組んでにゃ!応援してるにゃ!
「あと数万円稼げたのに…」「扶養を外れた方が実は手元に多く残ったのに…」
数年後にそう気づいても、過ぎた時間は戻ってきません。
今ならオンラインで、「あなたの場合、いくら稼ぐのが一番お金が貯まるか」をプロが無料で試算してくれます。
家計の健康診断だと思って、早めに一度チェックしてみてください。浮いたお金で家族旅行に行けるかもしれませんよ!
👉 【無料】何度でも相談OK!世帯年収を最大化するライフプラン相談はこちら![]()