「国民健康保険料を滞納してしまった…」
「払いたくても払えない…このままだとどうなるの?」
督促状が届くたびに不安が募りますよね。差し押さえや延滞金のことを考えると、夜も眠れないという方もいるでしょう。
でも、滞納しても諦める必要はありません。早めに相談すれば、分割払いや減免など、解決策はあります。

この記事では、国民健康保険料を滞納して払えない場合の対処法を詳しく解説します。
差し押さえを回避する方法、分割払いや減免の申請方法まで、具体的な解決策をお伝えします。
国民健康保険を滞納して払えないとどうなるか
まず、国民健康保険料を滞納したまま放置すると、どうなるのかを理解しましょう。
段階的に措置が厳しくなっていくため、早めの対応が重要です。
督促状と催告書が届く

納期限を過ぎると、まず督促状が届きます。
これは「保険料が未払いです」という通知で、納期限から20日以内に送られてくることが多いです。
督促状を無視すると、次は催告書が届きます。これは督促状よりも厳しいトーンで、「このまま支払いがなければ、差し押さえなどの措置を取ります」という警告です。
さらに、電話や訪問による催告が行われることもあります。
短期保険証に切り替えられる

滞納が1年未満続くと、通常の保険証から短期被保険者証に切り替えられます。
短期保険証とは、有効期限が3〜6か月と短い保険証のことです。
この保険証でも医療機関を受診できますが、更新のたびに市区町村の窓口へ行き、滞納分の支払いについて相談する必要があります。

短期保険証って、病院には行けるの…?

行けるにゃ!通常の保険証と同じように3割負担で受診できるにゃ。でも放置すると次の段階に進むから要注意にゃ!
資格証明書が交付され医療費が10割負担に

滞納が1年以上続くと、保険証が使えなくなり被保険者資格証明書が交付されます。
これは「国民健康保険に加入している」ことを証明する書類ですが、医療機関で提示しても、医療費は一時的に10割全額自己負担となります。
後日、市区町村の窓口で払い戻し(療養費の支給)を申請できますが、滞納分と相殺されるため、実質的に手元に戻ってくるお金はほとんどありません。
税務署から通知が来て青ざめる場合も...
国民健康保険を滞納して払えない。差し押さえまでの流れ
資格証明書が交付された後も支払いがない場合、最終的には財産の差し押さえに進みます。
差し押さえ予告通知が届く

督促状や催告を無視し続けると、差し押さえ予告通知が届きます。
これは「指定した期限までに支払いがなければ、財産を差し押さえます」という最終警告です。
この段階でも、まだ相談すれば差し押さえを回避できる可能性があります。絶対に無視せず、すぐに市区町村の窓口に連絡しましょう。
預金・給与・不動産などが差し押さえられる

予告通知後も対応しないと、財産の強制差し押さえが実行されます。
差し押さえの対象となるのは以下のようなものです。
差し押さえの対象
・預金口座(銀行口座の残高)
・給与(勤務先から直接徴収)
・不動産(家や土地)
・動産(車、貴金属など換金できるもの)
・生命保険の解約返戻金
もっとも多いのは預金口座の差し押さえです。ある日突然、口座が凍結されて引き出せなくなります。
給与の差し押さえの場合、勤務先に通知が行くため、会社に滞納の事実が知られてしまいます。

うわーん!本当に差し押さえられちゃうのね…!

ちょっと待つにゃ!差し押さえは最悪のケースにゃ。でも、そうなる前に相談すれば回避できるにゃ!
延滞金も発生する

滞納すると、保険料本体に加えて延滞金も発生します。
延滞金の利率は自治体によって異なりますが、年14.6%程度が一般的です(納期限から1か月以内は年7.3%程度)。
滞納期間が長くなればなるほど延滞金は膨らみ、支払い総額が増えてしまいます。

国民健康保険を滞納して払えない場合の対処法
ここからが重要です。国民健康保険料を払えない場合、必ず取るべき行動があります。
すぐに市区町村の窓口に相談する
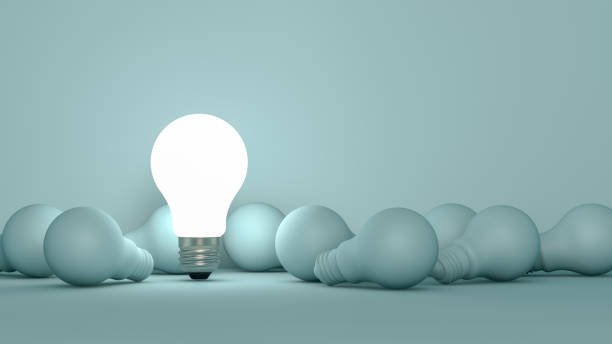
もっとも重要なのは、すぐに市区町村の国民健康保険担当窓口に相談することです。
「払えない」と正直に伝えるだけでも構いません。
窓口では、あなたの収入状況や生活状況を聞いた上で、以下のような対応を検討してくれます。
窓口で相談できること
・分割払いの相談
・減免制度の案内
・納付猶予の申請
・支払い計画の作成
・生活困窮者への支援制度の紹介
「相談したら怒られるかも」と心配する必要はありません。担当者は、滞納者の事情を理解し、解決策を一緒に考えてくれます。
分割払いを申請する

一括で払えない場合は、分割払いを申請しましょう。
「毎月5,000円ずつなら払える」「ボーナス時に多めに払いたい」など、具体的な支払い計画を提案すれば、多くの自治体が応じてくれます。
分割払いの合意ができれば、差し押さえを回避できます。

へぇ!分割払いにしてもらえるのね♪

そうにゃ!無理のない金額で相談すれば、柔軟に対応してもらえるにゃ!
減免制度を利用する

収入が著しく減少した、失業した、病気で働けなくなったなど、生活が困難な場合は減免制度を申請しましょう。
減免が認められれば、保険料の一部または全額が免除されます。
減免の対象例
・失業や廃業で収入がなくなった
・前年より収入が30%以上減少した
・病気やけがで働けなくなった
・災害で財産を失った
・生活保護に準ずる状況
減免の申請には、所得証明書や診断書などの書類が必要になる場合があります。詳しくは窓口で確認しましょう。

国民健康保険を滞納中でもできること
すでに滞納してしまっている場合でも、諦める必要はありません。
今からできることがたくさんあります。
滞納分を少しずつでも支払う意思を示す

たとえ少額でも、支払う意思を示すことが重要です。
「毎月3,000円しか払えない」でも構いません。少しずつでも支払いを続けることで、自治体との信頼関係が築けます。
支払う意思を示すことで、差し押さえを避けられる可能性が高まります。完全に無視するのではなく、「払えないけど、少しずつでも払いたい」という姿勢を見せましょう。
過去の滞納分も減免対象になる場合がある

「もう滞納してしまったから減免は無理」と思っていませんか。
実は、過去の滞納分も減免の対象になる場合があります。
特に、病気や失業、災害などで収入が大幅に減少した場合、滞納期間中の保険料についても減免を申請できることがあります。
自治体によって対応は異なりますが、諦めずに窓口で相談してみる価値があります。
生活保護の相談も選択肢の一つ

どうしても生活が困難で、保険料を払う余裕がない場合は、生活保護の相談も検討しましょう。
生活保護を受給すると、国民健康保険ではなく医療扶助が適用されるため、医療費の自己負担がなくなります。
また、生活保護受給中は国民健康保険料の支払い義務もなくなります。
「生活保護は恥ずかしい」と感じる方もいるかもしれませんが、これは憲法で保障された権利です。生活を立て直すための一時的な制度として、必要なら利用を検討してください。
国民健康保険の滞納を防ぐための予防策
滞納してしまう前に、予防策を講じることも大切です。
ここでは、保険料負担を減らす方法や、滞納を防ぐ工夫を紹介します。
社会保険の扶養に入れないか確認する

配偶者や親が社会保険に加入している場合、扶養に入ることを検討しましょう。
扶養に入れば、国民健康保険料の支払いがゼロになります。
扶養の条件は、年収130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)であることです。また、配偶者の年収の半分未満であることも求められます。
パートで働いている主婦の方なら、年収を130万円未満に抑えることで扶養に入れる可能性があります。配偶者の会社の健康保険組合に問い合わせてみましょう。
就職して社会保険に加入する

仕事を見つけて社会保険に加入するのも有効な方法です。
社会保険の保険料は給与から天引きされるため、滞納の心配がありません。
また、扶養家族がいても保険料は変わらないため、国民健康保険より負担が軽くなる場合があります。
口座振替や自動引き落としを設定する

納付書での支払いは、うっかり忘れてしまうことがあります。
口座振替や自動引き落としを設定すれば、支払い忘れを防げます。
市区町村の窓口で申請できるので、滞納を繰り返してしまう方は検討しましょう。

なるほど!予防策もいろいろあるのね♪

そうにゃ!滞納する前に対策を取ることも大事にゃ!
国民健康保険の滞納で払えない。放置せず今すぐ相談しよう:まとめ
国民健康保険料を滞納して払えない状況は、誰にでも起こりうることです。
大切なのは、放置せず、早めに相談すること。

差し押さえまで進んでしまう前に、市区町村の窓口で相談しましょう。
この記事のポイント
・滞納すると督促状→短期保険証→資格証明書→差し押さえと進む
・資格証明書では医療費が10割負担になる
・延滞金も発生し、滞納期間が長いほど負担が増える
・差し押さえの対象は預金・給与・不動産など
・すぐに市区町村の窓口に相談することが最重要
・分割払いや減免制度を利用できる
・扶養に入る、社会保険に加入するなどの予防策もある
「払えない」と正直に伝えることは、恥ずかしいことではありません。
窓口の担当者は、あなたの状況を理解し、一緒に解決策を考えてくれます。
分割払いや減免など、必ず何らかの方法があります。
一人で抱え込まず、今日から行動を起こしてくださいね。

よく分かったわ!放置しないで、すぐに窓口に相談してみるわね♪

その調子にゃ!早めの相談が解決への一番の近道にゃ!応援してるにゃ!
「あと数万円稼げたのに…」「扶養を外れた方が実は手元に多く残ったのに…」
数年後にそう気づいても、過ぎた時間は戻ってきません。
今ならオンラインで、「あなたの場合、いくら稼ぐのが一番お金が貯まるか」をプロが無料で試算してくれます。
家計の健康診断だと思って、早めに一度チェックしてみてください。浮いたお金で家族旅行に行けるかもしれませんよ!
👉 【無料】何度でも相談OK!世帯年収を最大化するライフプラン相談はこちら![]()


