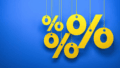「失業中なのに国民健康保険料って払わなきゃいけないの?」
「失業保険をもらっていても、国保っていくらかかるの?」
退職後、収入がなくなった途端に届く国民健康保険料の通知書。
予想外の金額に驚いて、不安になっている方も多いのではないでしょうか。

実は、失業中の国民健康保険料には軽減制度があるんです。
この記事では、失業保険を受給している間の国民健康保険料がいくらになるのか、軽減制度の使い方まで詳しく解説します。
知らないと損する情報ばかりですので、ぜひ最後まで読んでくださいね。
失業保険を受給中でも国民健康保険料は必要
まず基本から確認しましょう。
失業保険を受給していても、国民健康保険料の支払いは必要です。
失業保険と国民健康保険は別の制度

失業保険(雇用保険の基本手当)と国民健康保険は、全く別の制度です。
失業保険は「収入の保障」、国民健康保険は「医療費の保障」という異なる目的を持っています。
| 制度 | 目的 | 管轄 |
|---|---|---|
| 失業保険 | 失業中の生活費を保障 | 雇用保険(ハローワーク) |
| 国民健康保険 | 医療費の自己負担を軽減 | 市区町村 |
失業保険をもらっていても、病院にかかる可能性はありますよね。
だから、国民健康保険への加入と保険料の支払いは必須なんです。

え?失業保険もらってるのに、国保も払うの?

そうにゃ!でも安心して、失業中は軽減制度があるんだにゃ!
通常の国民健康保険料は前年の所得で計算される

国民健康保険料は通常、前年の所得をもとに計算されます。
つまり、今年退職して収入がゼロになっても、前年の収入に基づいた保険料が請求されるんです。
これが失業中の人にとって大きな負担になります。
例えば、前年の年収が300万円だった場合、国保の保険料は月2万円〜3万円程度になることも。
収入がないのにこの金額を払うのは、正直きついですよね。
失業中は軽減制度を利用できる

でも、安心してください。
失業した場合、国民健康保険料の軽減制度を利用できるんです。
この制度を使えば、前年の給与所得を30%として計算してもらえます。
つまり、保険料が約7割も安くなる可能性があるということ。
税務署から通知が来て青ざめる場合も...
失業保険受給中の国民健康保険料はいくらになる?
では、具体的に失業保険を受給している間、国民健康保険料はいくらになるのでしょうか。
収入別にシミュレーションしてみましょう。
前年年収300万円の場合の国保料シミュレーション

前年の年収が300万円だった場合の国民健康保険料を比較してみましょう。
| 計算方法 | 年間保険料(目安) | 月額(目安) |
|---|---|---|
| 通常計算 | 約28万円〜32万円 | 約2.3万円〜2.7万円 |
| 軽減後(30%計算) | 約9万円〜11万円 | 約7,500円〜9,000円 |
軽減制度を使えば、月額で約1.5万円も安くなるんです。
年間にすると約20万円の差。これは大きいですよね。

えっ!こんなに安くなるの!?

そうにゃ!だから軽減制度は絶対に使うべきだにゃ!
前年年収500万円の場合の国保料シミュレーション

前年の年収が500万円だった場合はどうでしょうか。
| 計算方法 | 年間保険料(目安) | 月額(目安) |
|---|---|---|
| 通常計算 | 約45万円〜50万円 | 約3.8万円〜4.2万円 |
| 軽減後(30%計算) | 約15万円〜18万円 | 約1.3万円〜1.5万円 |
年収が高かった人ほど、軽減の効果は大きくなります。
月額で2.5万円以上、年間で30万円近くも安くなる計算です。
自治体によって保険料は異なる

ここで注意してほしいのは、自治体によって保険料が異なるということ。
国民健康保険は市区町村ごとに運営されているため、保険料率が地域によって違うんです。
上記のシミュレーションはあくまで目安。
具体的な金額は、お住まいの市区町村のホームページで確認できます。
関連記事:https://sigomama.com/kokuho-heikin/
失業保険受給中の国保軽減制度の条件と手続き
では、どうすれば軽減制度を利用できるのでしょうか。
条件と手続き方法を詳しく見ていきましょう。
軽減制度を利用できる人の条件

国民健康保険料の軽減制度を利用できるのは、非自発的失業者です。
具体的には、以下の条件を満たす必要があります。
軽減制度の対象者
- 倒産・解雇・雇い止めなどで離職した人
- 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者
- 離職時の年齢が65歳未満
- 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが対象(11、12、21、22、23、31、32、33、34)
自己都合退職の場合は、原則として軽減の対象外です。
ただし、正当な理由のある自己都合退職(例:通勤困難、賃金未払いなど)は対象になることがあります。
軽減制度の申請方法と必要書類

軽減制度は自動適用されません。
必ず市区町村の窓口で申請手続きが必要です。
申請に必要な書類は以下の通り。
軽減申請に必要な書類
- 国民健康保険証
- 雇用保険受給資格者証(ハローワークで発行)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 印鑑(自治体によっては不要)
手続きは簡単で、窓口で書類を提出するだけ。
申請が通れば、次回の保険料から軽減が適用されます。

え?自分で申請しないとダメなの?

そうにゃ!申請しないと軽減されないから、必ず手続きするにゃ!
軽減期間は最長2年間

軽減制度が適用される期間は、離職日の翌日から翌年度末までです。
最長で約2年間、軽減を受けることができます。
例えば、2024年3月に退職した場合、2026年3月末まで軽減が続きます。
ただし、再就職して社会保険に加入したり、65歳になったりすると、そこで軽減は終了します。
関連記事:https://sigomama.com/kokuho-genmen/
失業保険と国保料どっちが高い?支払いのバランス
失業保険をもらっていても、国民健康保険料を払うのは負担ですよね。
でも、実際にはどっちの金額が大きいのでしょうか。
失業保険の受給額は人によって異なる

失業保険の受給額は、退職前の給与と年齢によって決まります。
基本手当日額は、賃金日額の50%〜80%です。
例えば、月収25万円(賃金日額約8,300円)の場合、基本手当日額は約5,800円程度。
月額にすると約17万円程度の失業保険が受け取れます。
軽減後の国保料なら失業保険で十分カバーできる

軽減制度を使った場合の国民健康保険料は、月額7,000円〜1.5万円程度。
失業保険の受給額が月15万円以上あれば、十分にカバーできる金額です。
それでも支払いが厳しい場合の対処法

それでも保険料の支払いが厳しい場合、以下の方法があります。
支払いが厳しいときの対処法
- 分割払い:市区町村の窓口で相談すれば、分割払いに応じてもらえる
- 減免制度:生活が困窮している場合、さらなる減免を受けられることも
- 扶養に入る:配偶者の社会保険の扶養に入れば保険料はゼロ
絶対に滞納だけは避けてください。
滞納すると延滞金が発生したり、保険証が使えなくなったりします。
困ったときは、まず市区町村の窓口に相談しましょう。

よかった!軽減制度があるなら安心ね♪

その調子にゃ!制度を上手に使って、安心して求職活動に集中するにゃ!
失業保険受給中の国民健康保険料はいくら?軽減制度で負担を減らそう。まとめ
失業保険を受給している間も、国民健康保険料の支払いは必要です。

しかし、非自発的失業者なら軽減制度を利用できるため、保険料を大幅に抑えることができます。
この記事のポイント
- 失業保険受給中でも国民健康保険料の支払いは必要
- 軽減制度を使えば保険料が約7割安くなる
- 対象は非自発的失業者(倒産・解雇・雇い止めなど)
- 申請は市区町村の窓口で手続きが必要
- 軽減期間は最長2年間
- 支払いが厳しい場合は分割払いや減免制度を検討
特に重要なのは、軽減制度は自動適用されないこと。
必ず自分で申請する必要があります。
退職したら、すぐに市区町村の窓口で手続きをしてくださいね。
軽減制度を上手に活用して、失業中の経済的な負担を少しでも減らしましょう。
安心して次の仕事探しに集中できる環境を整えることが大切です。

よくわかったわ!明日すぐに申請してくるわね♪

その調子にゃ!雇用保険受給資格者証を忘れずに持っていくにゃ!応援してるにゃ!
「あと数万円稼げたのに…」「扶養を外れた方が実は手元に多く残ったのに…」
数年後にそう気づいても、過ぎた時間は戻ってきません。
今ならオンラインで、「あなたの場合、いくら稼ぐのが一番お金が貯まるか」をプロが無料で試算してくれます。
家計の健康診断だと思って、早めに一度チェックしてみてください。浮いたお金で家族旅行に行けるかもしれませんよ!
👉 【無料】何度でも相談OK!世帯年収を最大化するライフプラン相談はこちら![]()