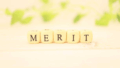「世帯分離をすると介護費用が安くなるって聞いたけど…」
「でも、何か落とし穴があるんじゃないの?」
「デメリットをちゃんと知ってから決めたい」
親の介護費用を抑えるために世帯分離を検討している方、こんな不安を感じていませんか?

実は、世帯分離にはメリットだけでなく、知らないと損するデメリットも存在します。
特に注意すべきは、国民健康保険料が逆に高くなるケースや、扶養手当が受けられなくなることなんです。
この記事では、世帯分離のデメリットを具体的な金額シミュレーション付きで徹底解説!
あなたの家庭に世帯分離が本当に合っているのか、冷静に判断できる情報をお届けします。後悔しない選択をするために、ぜひ最後までお読みください。
世帯分離のデメリット1。国民健康保険料が高くなる場合がある
世帯分離で最も注意すべきデメリット、それが国民健康保険料の負担増です。
「え、世帯分離って保険料が安くなるんじゃないの?」と思った方も多いはず。
実は、ケースによっては逆に高くなってしまうんですよ。
世帯ごとに均等割がかかるため合計額が増える

国民健康保険料は「所得割」と「均等割」の2つから構成されています。
所得割は収入に応じて決まりますが、均等割は世帯ごとに固定でかかる金額なんです。
世帯分離をすると、この均等割が2世帯分かかるようになります。
| 項目 | 世帯分離前 | 世帯分離後 |
|---|---|---|
| 均等割 | 1世帯分 | 2世帯分 |
| 平等割(自治体による) | 1世帯分 | 2世帯分 |
| 合計負担 | 約3〜5万円/年 | 約6〜10万円/年 |
自治体によって金額は異なりますが、年間で数万円の差が出ることも珍しくありません。

え!?安くなると思ってたのに、高くなることもあるの!?

そうなんだにゃ!だから事前に必ず試算してもらうことが大事なんだにゃ!
具体的なシミュレーション。どんなケースで高くなる?

実際の数字で見てみましょう。
ケース1:親(年金80万円)+子(年収400万円)
【世帯分離前】
・所得割:約12万円
・均等割:約4万円
・合計:約16万円/年
【世帯分離後】
・親の世帯:約2万円
・子の世帯:約10万円
・合計:約12万円/年
→ 4万円安くなる
ケース2:親(年金180万円)+子(年収250万円)
【世帯分離前】
・所得割:約6万円
・均等割:約4万円
・合計:約10万円/年
【世帯分離後】
・親の世帯:約5万円
・子の世帯:約7万円
・合計:約12万円/年
→ 2万円高くなる
このように、親の年金額が比較的多く、子の収入が少ない場合は、世帯分離で保険料が高くなってしまうんです。
必ず事前に市区町村で試算してもらおう

世帯分離を決める前に、必ず市区町村の国民健康保険課で試算してもらいましょう。
「世帯分離した場合、保険料がどう変わるか教えてください」と伝えれば、無料で計算してくれますよ。
税務署から通知が来て青ざめる場合も...
世帯分離のデメリット2。扶養手当や家族手当が受けられなくなる
世帯分離の2つ目のデメリットは、会社からの扶養手当・家族手当が受けられなくなることです。
これ、実は見落としがちなんですが、年間で考えるとかなり大きな金額になりますよ。
扶養手当は月1〜2万円。年間で20万円以上の損失も

多くの会社では、扶養家族がいる社員に対して扶養手当を支給しています。
金額は会社によって異なりますが、一般的には以下の通りです。
| 扶養対象 | 月額手当 | 年間 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 5,000円〜10,000円 | 6万円〜12万円 |
| 親(1人) | 3,000円〜8,000円 | 3.6万円〜9.6万円 |
| 合計 | 8,000円〜18,000円 | 9.6万円〜21.6万円 |
世帯分離をすると、親が扶養から外れるため、この手当が受けられなくなります。
年間で10万円〜20万円の収入が減ることになるんです。

うわぁ…年間20万円も減るなんて…

そうなんだにゃ。介護費用が安くなっても、手当がなくなったら相殺されちゃう可能性もあるにゃ。
会社の規定を必ず確認すること

扶養手当の支給条件は会社によって異なります。
「税法上の扶養」で判断する会社もあれば、「同一世帯であること」が条件の会社もあるんです。
世帯分離を決める前に、必ず会社の人事部や総務部に確認しましょう。
確認すべきポイント
・扶養手当の支給条件は何か?
・世帯分離をした場合、手当はどうなるか?
・手続きに必要な書類は何か?
・いつから手当が停止されるか?
健康保険組合の福利厚生も使えなくなる

会社の健康保険組合に加入している場合、被扶養者として様々な福利厚生を受けられます。
例えば、人間ドックの補助、スポーツジムの割引、保養所の利用などですね。
世帯分離で扶養から外れると、これらの福利厚生もすべて使えなくなります。
金銭面だけでなく、生活の質にも影響する可能性があることを覚えておきましょう。
世帯分離のデメリット3。税金の扶養控除が使えなくなる可能性
3つ目のデメリットは、税金の扶養控除が使えなくなることです。
これも見落としがちですが、年間で数万円の税負担増になることがありますよ。
扶養控除は年間38万円〜58万円の所得控除

税法上の扶養控除を受けていると、以下の金額が所得から控除されます。
| 扶養親族の年齢 | 控除額 |
|---|---|
| 一般の扶養親族 | 38万円 |
| 70歳以上(同居) | 58万円 |
| 70歳以上(別居) | 48万円 |
世帯分離をすると「生計を一にしている」とみなされず、扶養控除が使えなくなる可能性があります。
その結果、所得税と住民税が合わせて年間5万円〜10万円ほど増えることがあるんです。
世帯分離しても扶養控除を受けられるケースもある

ただし、世帯分離をしても扶養控除を受けられるケースもあります。
税法上の「生計を一にしている」の判断は、実態で判断されるからです。
同じ家に住んでいて、実際に生活費を援助している場合は、世帯分離していても扶養控除を受けられる可能性があります。
扶養控除を受けられる可能性があるケース
・同じ家に住んでいる
・親の生活費を定期的に援助している
・食事や日用品を共有している
・親の医療費を負担している
判断が難しい場合は、税務署や税理士に相談することをおすすめします。

へぇ〜、世帯分離しても扶養控除を受けられることもあるのね!

そうにゃ!でも自己判断は危険だから、必ず専門家に確認するにゃ!

世帯分離のデメリット4。手続きが煩雑で時間がかかる
4つ目のデメリットは、手続きの煩雑さです。
「住民票を分けるだけでしょ?簡単じゃない?」と思うかもしれませんが、実はそうでもないんですよ。
複数の窓口で別々の手続きが必要

世帯分離をすると、以下のような手続きが必要になります。
必要な手続き一覧
① 市区町村窓口で住民票の世帯分離
② 国民健康保険の変更手続き
③ 介護保険の負担割合変更申請
④ 高額介護サービス費の区分変更
⑤ 会社への扶養控除の変更届
⑥ 健康保険組合への被扶養者削除届
それぞれ別の窓口で手続きをする必要があり、半日〜1日がかりになることも珍しくありません。
高齢の親が自分で手続きするのは難しい

特に問題なのが、高齢の親が自力で手続きをするのは難しいということ。
世帯分離の手続きは本人が行う必要がありますが、認知機能が低下していたり、体が不自由だったりすると、一人では対応できません。
その場合、委任状を作成して代理人が手続きをする必要があります。
これがまた面倒で、委任状の書き方を間違えると受理されないこともあるんです。
書類の不備で何度も窓口に通うことも

初めて世帯分離の手続きをする場合、書類の不備で何度も窓口に通うことになるケースも多いんです。
「これも必要でした」「この書類の書き方が違います」といった理由で、2回、3回と足を運ぶことに。
仕事をしながら何度も役所に行くのは、かなりの負担ですよね。

うぅ…手続きだけでこんなに大変なのね…

だから事前に市区町村に電話して、必要な書類を全部確認しておくといいにゃ!
世帯分離のデメリット5。介護費用の合算ができなくなる
5つ目のデメリットは、介護費用の合算ができなくなることです。
これは、複数の家族が介護サービスを利用している場合に特に影響します。
高額介護サービス費の世帯合算ができない

高額介護サービス費制度では、同じ世帯の介護費用を合算して上限額を計算できます。
例えば、夫婦2人とも介護サービスを利用している場合、2人分を合算して月額44,400円(住民税課税世帯の場合)が上限になります。
しかし、世帯分離をするとそれぞれの世帯で別々に計算されるため、合算のメリットが受けられません。
具体例
【世帯分離前】
・夫の介護費用:月3万円
・妻の介護費用:月2万円
・合計:5万円 → 上限44,400円で5,600円が払い戻し
【世帯分離後】
・夫の世帯:月3万円(上限以下なので払い戻しなし)
・妻の世帯:月2万円(上限以下なので払い戻しなし)
・合計:5万円 → 払い戻しなし
このように、複数人が介護を受けている場合は、世帯分離でかえって損をすることもあるんです。
医療費の世帯合算もできなくなる

同様に、高額療養費制度の世帯合算もできなくなります。
医療費が高額になった場合、同一世帯であれば家族の医療費を合算して限度額を計算できますが、世帯分離をするとこれができません。
親も子も医療費がかかる家庭では、トータルの負担が増える可能性があります。

世帯分離のデメリット6。相続税の特例が使えなくなる場合がある
最後のデメリットは、相続税の特例が使えなくなる可能性です。
これは将来のことなので見落としがちですが、金額的には非常に大きな影響があります。
小規模宅地等の特例が適用できないケース

親が亡くなって自宅を相続する場合、小規模宅地等の特例を使えば、土地の評価額を80%減額できます。
例えば、5,000万円の土地が1,000万円の評価になるため、相続税を大幅に減らせるんです。
しかし、この特例を受けるには「同居していた親族が相続する」ことが条件の一つ。
世帯分離をしていると「同居」とみなされず、特例が使えなくなる可能性があります。
二世帯住宅の区分登記は特に注意

二世帯住宅で区分登記をしている場合、世帯分離との組み合わせで特例が使えなくなるリスクが高まります。
区分登記とは、親世帯と子世帯の住居部分をそれぞれ別の不動産として登記すること。
これに世帯分離が加わると、税務署から「完全に別々の生活」と判断されやすくなるんです。

え…相続税にまで影響するの!?

そうにゃ!目先の介護費用だけじゃなくて、将来の相続税も考えないとダメなんだにゃ!
世帯分離のデメリットを理解して慎重に判断しよう。まとめ
ここまで、世帯分離のデメリットについて詳しく解説してきました。
最後に、重要なポイントをもう一度整理しましょう。

世帯分離は介護費用を抑える有効な手段ですが、デメリットも決して小さくありません。
世帯分離の主なデメリット
① 国民健康保険料が高くなる場合がある → 均等割が2世帯分かかる
② 扶養手当・家族手当が受けられなくなる → 年間10〜20万円の収入減
③ 税金の扶養控除が使えなくなる可能性 → 所得税・住民税が年間5〜10万円増
④ 手続きが煩雑で時間がかかる → 複数の窓口で別々の手続きが必要
⑤ 介護費用・医療費の合算ができない → 複数人が利用する場合は損することも
⑥ 相続税の特例が使えなくなる場合がある → 数百万円〜数千万円の影響も
世帯分離を検討する際は、メリットとデメリットを天秤にかけることが何より大切です。
介護費用が年間20万円安くなっても、扶養手当や税金で20万円増えたら意味がないですよね。
世帯分離を決める前に必ずやるべきこと
① 市区町村で国民健康保険料の試算をしてもらう
② 会社の人事部に扶養手当の条件を確認する
③ 税務署や税理士に扶養控除について相談する
④ ケアマネジャーに介護費用の削減額を試算してもらう
⑤ 将来の相続税への影響を税理士に相談する
これらをすべて確認した上で、トータルで得になるかを判断しましょう。
また、金銭面だけでなく、家族の気持ちも大切にしてください。
「世帯を分ける」という手続きに、親が寂しさを感じることもあります。
しっかりと話し合い、家族全員が納得した上で進めることが大切ですよ。
世帯分離は「使える制度」ですが、「万能の解決策」ではありません。
デメリットをしっかり理解した上で、あなたの家庭に合った選択をしてくださいね。

よくわかったわ!まずは専門家に相談してみるわね♪

その調子にゃ!焦らずじっくり検討して、後悔しない選択をするにゃ!応援してるにゃ!
「あと数万円稼げたのに…」「扶養を外れた方が実は手元に多く残ったのに…」
数年後にそう気づいても、過ぎた時間は戻ってきません。
今ならオンラインで、「あなたの場合、いくら稼ぐのが一番お金が貯まるか」をプロが無料で試算してくれます。
家計の健康診断だと思って、早めに一度チェックしてみてください。浮いたお金で家族旅行に行けるかもしれませんよ!
👉 【無料】何度でも相談OK!世帯年収を最大化するライフプラン相談はこちら![]()