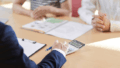「夫が個人事業主なんですが、私は扶養に入れるんですか?」
「手続きはどうやってするんですか?」
「会社員の扶養と同じなんですか?」
個人事業主の妻からこんな質問をよく聞きます。

実は、この答えは「条件さえ満たせば、ある程度は可能だけど、会社員の扶養とは違う」というところなんですよ。
個人事業主の夫の扶養に入る手続きは、会社員の場合とは異なります。なぜなら、個人事業主は社会保険ではなく国民健康保険と国民年金に加入しているからです。
この記事では、個人事業主の夫の扶養に入るための条件、必要な手続き、必要書類、注意点を詳しく解説します。
「我が家の場合、扶養に入れるのかな」を判断できるようになり、実際に手続きを進めるステップが明確になりますよ。
個人事業主の夫の扶養に入る。そもそも可能なのか
まず最初に確認しておくべき点があります。
個人事業主の妻が扶養に入るのは可能だけど条件がある

答えから言うと「可能です」。
ただし、会社員の妻が扶養に入る場合と比べると、条件が異なるんですよ。個人事業主の妻が扶養に入るには、妻の年間所得が130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満)である必要があります。
この「年間所得」というのが重要なポイント。売上ではなく、「売上から経費を引いた額」で判断されるんです。つまり、売上が150万円でも、経費が30万円あれば所得は120万円となり、扶養要件を満たす可能性があるんですよ。
同一世帯で生計を一にしていることが条件

もう一つ重要な条件があります。夫と妻が同一世帯で、生計を一にしていることが必須です。
つまり、住所が同じで、家計が一つという状態でなければいけません。別居していたり、完全に経済的に独立していれば、扶養に入ることはできないんですよ。
個人事業主の妻が扶養に入るための条件
✓ 妻の年間所得が130万円未満(60歳以上・障害者は180万円)
✓ 同一世帯で生計を一にしている
✓ 夫が社会保険に加入していない(ただし特定の条件で加入している場合もある)
✓ 妻が他の健康保険の被扶養者になっていない
✓ 妻の所得が夫より多くない

え、売上と所得が違うの?そっか、経費を引くんだ!

そこが大事だにゃ!だから所得を正確に計算することが第一歩なんだにゃ!
税務署から通知が来て青ざめる場合も...
個人事業主の夫の扶養に入るための手続き。ステップバイステップ
では、実際に扶養に入るためにはどんな手続きをすればいいのでしょうか。
ステップ1:所得を正確に計算する

最初にすべきことは、妻の所得を正確に計算することです。
妻が自営業をしている場合は、過去1年間の売上から経費を引いた額が所得になります。妻が青色申告をしている場合は、青色申告決算書を確認しましょう。白色申告の場合は、収支計算書を見て所得を確認します。
所得が130万円未満なら扶養要件を満たす可能性があります。この時点で、夫の健康保険組合に「扶養に入れるか」を相談するのが効率的です。
ステップ2:夫の健康保険組合に相談する

個人事業主の場合、加入している健康保険は「協会けんぽ」か「各業種別健保組合」です。
夫の健康保険証を確認して、どちらに加入しているかを把握しましょう。その上で、健保組合に電話して「妻を扶養に入れたいのですが、条件や手続きを教えてください」と相談するんです。
健保組合によって基準や手続きが多少異なることもあるので、これを事前に確認することが本当に大切なんですよ。
ステップ3:必要書類を準備する

健保組合に相談した際に「どんな書類が必要か」を聞きましょう。一般的には以下のような書類が必要になることが多いです。
一般的に必要な書類
□ 被扶養者申請書(健保組合から入手)
□ 夫の健康保険証のコピー
□ 妻の運転免許証など身分証のコピー
□ 過去1年分の妻の確定申告書の控え
□ 妻の所得を証明する書類
□ 住民票(同一世帯確認用)
□ 妻が現在何か他の保険に加入していないことの証明書
特に重要なのが「妻の所得を証明する書類」です。青色申告をしている場合は青色申告決算書、白色申告の場合は収支計算書が必要になります。
ステップ4:被扶養者申請書を提出する

必要書類が揃ったら、被扶養者申請書に記入して、夫の健保組合に提出します。
申請書は郵送でも窓口でも受け付けることが多いです。郵送の場合は、書類を失くさないために、特定記録郵便や簡易書留で送ることをお勧めします。
申請後、健保組合が書類を審査します。一般的には2週間から1ヶ月で審査結果が出ることが多いですが、書類が不足している場合は連絡が来るので、その場合は追加書類を提出しましょう。
ステップ5:認定を受けて新しい保険証を取得

審査が通ったら、妻の新しい保険証が郵送されてきます。
この新しい保険証が手元に届いたら、それが「扶養に入った」というサイン。その日から妻は夫の健康保険の被扶養者として扱われ、医療費の自己負担額が変わります。
個人事業主の扶養申請で気をつけるべき点。後悔しないために
では、実際に申請する際に気をつけるべき点は何でしょうか。
所得が130万円を超えそうになったら早めに報告する
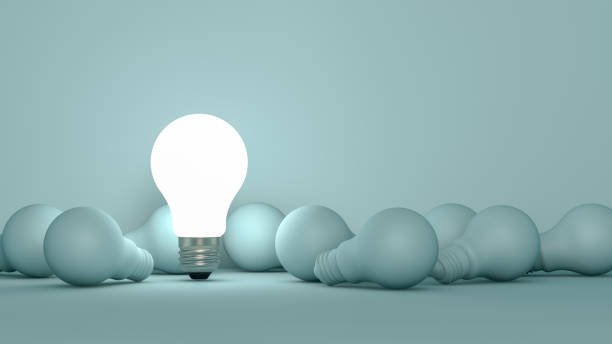
扶養に入ってから、妻の事業が好調になり、所得が130万円に近づいてくることもあります。
その場合は、早めに夫の健保組合に報告する必要があります。所得が130万円を超えてしまうと、妻は自動的に扶養対象外になってしまい、妻自身で健康保険に加入し直さなければいけなくなるんですよ。
手続きを怠ると、医療費が全額自己負担になるリスクもあります。定期的に所得を見直し、130万円を超えそうなら健保組合に相談することが大切です。
青色申告の継続性が重要

妻が青色申告をしている場合、申告を続けることが大切です。
健保組合は毎年、扶養要件を確認することがあります。その際に青色申告決算書を提出することになるので、申告を続けないと扶養資格を失う可能性があるんですよ。
健保組合によって基準が異なることがある
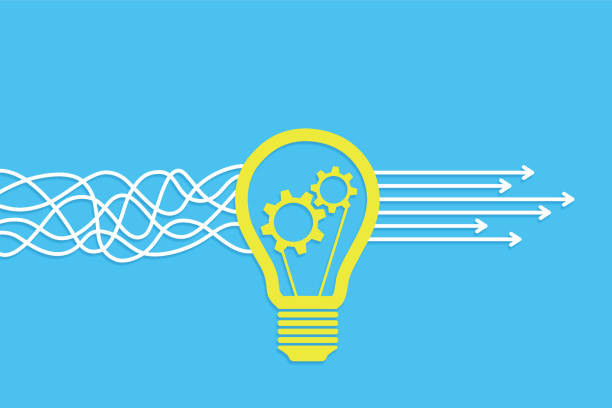
協会けんぽと業界別健保組合では、扶養要件の判断基準が多少異なることがあるんです。
例えば、「青色申告だから経費控除が大きい」という場合、ある健保組合では認可されるが、別の健保組合では認可されないということもあり得るんですよ。だからこそ、自分たちの健保組合の基準を正確に把握することが本当に大切なんです。

結構手続きが複雑なのね。でも大事なことばっかり!

そうだにゃ。だからこそ、最初の相談が超重要だにゃ!
個人事業主の妻が扶養に入るメリット。何が得られるのか
では、実際に扶養に入るとどんなメリットがあるのでしょうか。
健康保険の保険料を払わなくて済む

最大のメリットがこれです。
扶養に入る前は、妻が自分で国民健康保険に加入して、毎月5,000円から8,000円の保険料を支払っていたかもしれません。扶養に入ると、妻の保険料を払わなくて済むんですよ。
年間で6万円から10万円の節約になるんです。これは家計にとって本当に大きいですよね。
医療費の自己負担が3割になる

扶養に入ると、妻が病院にかかった時の医療費自己負担は3割になります。
扶養に入っていない場合も医療費自己負担は3割ですが、扶養に入ることで「保険が安定する」という心理的メリットもあるんですよ。また、高額療養費制度の対象にもなりやすくなるんです。
家族手当や各種手当の対象になる可能性

夫が別の会社に勤めている場合や、業界別健保組合に加入している場合、妻が扶養に入ることで「家族手当」などの対象になることもあるんです。
月5,000円程度の家族手当が支給されるなら、それも大きなメリットになるんですよ。


年間6万円以上の削減か〜。結構大きいわね〜!

だからこそ、手続きをちゃんとやることが大事なんだにゃ!
個人事業主の夫の扶養に入る手続きで成功するために
最後に、実際に手続きを進める際のポイントをまとめておきます。
早めに夫の健保組合に相談する

「いつから申請したらいいのか」という疑問があれば、迷わずに夫の健保組合に電話して相談しましょう。
組合によっては「今の所得なら大丈夫」「書類が足りない」など、具体的なアドバイスをくれますよ。
所得の計算を正確に

妻の所得が130万円未満か超えるか、それは扶養要件の判断を大きく左右します。
所得計算に迷ったら、税理士や会計士に相談することをお勧めします。正確な所得を基に、自信を持って申請できるようになるんですよ。
夫婦で家計管理を話し合う

扶養に入ることで「妻が月いくらまで稼げるのか」が決まります。
夫婦で「月いくら稼ぎたいのか」「税金や保険料をどう考えるのか」を話し合って、人生計画を立てることが大切なんですよ。
個人事業主の夫の扶養に入る手続きは、会社員の場合と異なり、少し複雑な部分があります。でも「どんな書類が必要か」「何を確認すべきか」が明確になっていれば、進めるのはそこまで難しくありません。
最初の相談が本当に大切。夫の健保組合に連絡して、「我が家の場合、扶養に入れるのか」を確認するところから始めてください。そこから先は、指示に従って書類を準備して提出するだけです。夫婦で協力して、家計をより良くする道を選んでいってくださいね。
個人事業主の家だからこそ、扶養という制度を上手に活用することが大切なんです。

よし。まずは夫の健保組合に電話してみるわ!

その調子だにゃ。最初の一歩が全ての始まりだにゃ!
「あと数万円稼げたのに…」「扶養を外れた方が実は手元に多く残ったのに…」
数年後にそう気づいても、過ぎた時間は戻ってきません。
今ならオンラインで、「あなたの場合、いくら稼ぐのが一番お金が貯まるか」をプロが無料で試算してくれます。
家計の健康診断だと思って、早めに一度チェックしてみてください。浮いたお金で家族旅行に行けるかもしれませんよ!
👉 【無料】何度でも相談OK!世帯年収を最大化するライフプラン相談はこちら![]()