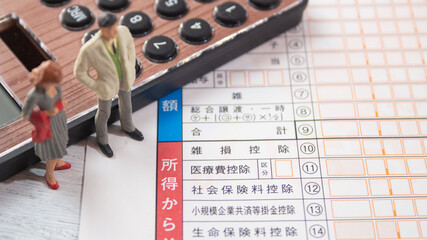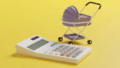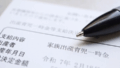「育休中だけど、配偶者控除って受けられるの?」
「妻の年末調整はどうすればいいの?夫の会社に出すの?」
「育児休業給付金があると控除が受けられなくなる?」
育休中の年末調整、本当にわかりにくいですよね。
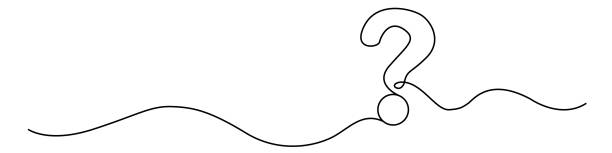
でも安心してください。育休中でも配偶者控除は受けられます!
しかも、育児休業給付金は非課税なので、控除の条件を満たしやすいんです。
この記事では、育休中の配偶者控除と妻の年末調整について徹底解説!
受けられる条件、妻と夫それぞれの手続き、よくある誤解まで完全網羅します。
※個別事情が複雑な場合は、記事後半で
子育て家庭向けの無料サポート窓口も案内しています。
育休中の配偶者控除:妻の年末調整はどうなる?
まず結論からお伝えします。
育休中の妻は配偶者控除の対象になり、夫の税金が安くなります!
結論:育休中の妻は配偶者控除の対象になる

育休中の妻は、配偶者控除の対象になります。
なぜなら、育休中は給与が大幅に減少するか、まったく支払われないことが多いからです。
配偶者控除を受けるには、妻の年間所得が一定額以下である必要がありますが、育休中はこの条件を満たしやすいんです。
具体的には、妻の年間給与収入が123万円以下(2025年の税制改正後)であれば、夫が配偶者控除を受けられます。
育休中で給与がほとんど出ていなければ、この条件は簡単に満たせますよね。

育休中でも配偶者控除が受けられるのね!知らなかった♪

そうなんだにゃ!しっかり申請して節税するにゃ!
育児休業給付金は非課税で所得に含まれない

ここで重要なポイントがあります。育児休業給付金は非課税です。
非課税ということは、所得としてカウントされないため、配偶者控除の判定にまったく影響しません。
つまり、育児休業給付金をいくらもらっても、それが原因で配偶者控除が受けられなくなることはないんです。
例えば、育休中に給与がゼロで育児休業給付金だけを受け取っている場合、妻の所得はゼロ。
所得がゼロということは、配偶者控除の条件(所得48万円以下、給与なら103万円以下)を満たすので、夫は配偶者控除をフルで受けられます。
妻と夫、それぞれの年末調整の違い

妻と夫、それぞれの年末調整は別々に行います。
妻は自分の会社で年末調整を受けます。育休中であっても、会社に在籍していて給与を受け取っていれば(育休前の給与など)、年末調整の対象です。
夫は自分の会社で年末調整を受けますが、その際に「配偶者控除」を申請します。
つまり、妻は「自分の控除」を自分の会社で申請し、夫は「配偶者控除」を自分の会社で申請するという形です。
この2つは別々の手続きなので、それぞれしっかり対応することが大切です。
税務署から通知が来て青ざめる場合も...
育休中に配偶者控除を受けるための条件
では、具体的にどんな条件を満たせば配偶者控除を受けられるのでしょうか。
条件を正確に理解して、確実に控除を受けましょう。
妻の年収が123万円以下であること

配偶者控除を受けるための第一の条件は、妻の年収が一定額以下であることです。
2025年の税制改正後は、妻の給与収入が123万円以下であれば、夫が配偶者控除を受けられます。
所得で言えば、48万円以下です。給与所得控除があるため、給与収入103万円=所得48万円となります。
育休中で1年のほとんどを休んでいる場合、給与収入が123万円を超えることはまずありません。
例えば、1〜3月まで働いて4月から育休に入った場合、3か月分の給与が123万円を超えることは少ないでしょう。
夫の所得が1000万円以下であること

配偶者控除を受けるためには、夫の所得にも制限があります。
夫の合計所得金額が1000万円以下(給与収入で約1220万円以下)であることが条件です。
夫の所得がこれを超える場合は、配偶者控除を受けることができません。
ただし、一般的なサラリーマン家庭であれば、この条件を超えることは少ないでしょう。
また、夫と妻が生計を一にしていること、妻が青色事業専従者として給与を受けていないことなども条件に含まれます。
育休中の収入計算で注意すべき点

育休中の収入計算で注意すべき点があります。
まず、育児休業給付金は非課税なので、収入に含めません。これは何度強調してもしすぎることはありません。
しかし、副業やフリーランスの収入がある場合は、それも含めて計算する必要があります。
また、年の途中で収入が変動する場合は、年末時点での年収全体を確認することが大切です。
例えば、1〜3月は通常勤務で月給30万円、4月から育休で給与ゼロの場合、年収は90万円。育児休業給付金が月15万円出ていても、それは収入に含まれないので、所得は90万円のままです。

副業の収入も含まれるのね!気をつけなきゃ!

そうなんだにゃ!全部の収入を正確に把握することが大事にゃ!
妻の年末調整で必要な手続き
では、具体的な手続きを見ていきましょう。
妻と夫、それぞれが提出する書類を確認します。
妻が自分の会社に提出する書類

妻が自分の会社に提出する書類は、主に以下の通りです。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、育休中であっても年末調整の対象になる場合は提出が必要です。
この書類では、自分の基礎控除や扶養親族の情報を申告します。
また、生命保険料控除や地震保険料控除を受ける場合は、「給与所得者の保険料控除申告書」も提出します。
育休中で給与がほとんどない場合でも、源泉徴収された税金がある場合は年末調整で還付を受けられる可能性があるので、しっかり申告しましょう。
夫が自分の会社に提出する書類

夫が自分の会社に提出する書類で最も重要なのが、「給与所得者の配偶者控除等申告書」です。
この書類に、妻の氏名、マイナンバー(または個人番号)、所得金額などを記入します。
妻の所得金額は、妻の年収から給与所得控除を引いた金額です。育休中で給与が少ない場合は、所得もほぼゼロに近くなります。
この書類を提出することで、夫の年末調整で配偶者控除が適用され、税金が還付されます。
記入方法がわからない場合は、会社の総務や人事に相談するか、税務署に問い合わせましょう。
年末調整の提出期限と注意点

年末調整の提出期限は、会社によって異なりますが、一般的には11月中旬から12月上旬です。
会社から配布される申告書は、毎年10月から11月に配られることが多いので、早めに記入して提出しましょう。
期限を過ぎてしまった場合でも、諦める必要はありません。翌年の確定申告期間(2月16日〜3月15日)に確定申告をすれば、配偶者控除を受けることができます。
ただし、年末調整で済ませられるものは年末調整で済ませた方が簡単なので、期限内に提出することをおすすめします。
育休中の配偶者控除でよくある誤解
育休中の配偶者控除には、よくある誤解があります。
誤解を解消して、正しく控除を受けましょう。
給付金を収入と誤解してしまうケース

最もよくある誤解が、育児休業給付金を収入と考えてしまうケースです。
「給付金で月15万円もらっているから、年間180万円の収入がある」と計算してしまい、配偶者控除が受けられないと思い込んでしまうんです。
しかし、何度も繰り返しますが、育児休業給付金は非課税で所得に含まれません。
つまり、給付金がいくらあっても、それは配偶者控除の判定に影響しないということ。
この誤解で配偶者控除を受けずに損をしている人が実際にいるので、注意しましょう。
妻の年末調整をしなくていいと思い込むケース

「育休中だから妻の年末調整は必要ない」と思い込むケースもよくあります。
しかし、育休中であっても会社に在籍していて給与を受け取っている場合は、年末調整の対象です。
例えば、育休前の1〜3月に給与があった場合、そこから源泉徴収されている税金があるかもしれません。
年末調整をすることで、払いすぎた税金が還付される可能性があります。
また、生命保険料控除などを受けることもできるので、妻も自分の年末調整をしっかり行いましょう。
年の途中で収入が変動した場合の対応

年の途中で収入が大きく変動した場合、どう対応すべきか迷いますよね。
育休に入るタイミングによって、年間の収入が大きく変わります。
例えば、1月に育休に入った場合と、12月に育休に入った場合では、年収が全く異なります。
重要なのは、年末時点での年収全体を確認することです。
年の途中で収入が減っても、年末調整の時点で年間の収入を正確に計算すれば、配偶者控除が受けられるかどうかがわかります。
不安な場合は、会社の総務や税務署に相談して、正確な金額を確認しましょう。

誤解が解けてスッキリしたわ♪ちゃんと申請しなきゃね!

その調子にゃ!正しく理解して、もらえる控除を確実に受け取るにゃ!
育休中の配偶者控除と妻の年末調整:節税チェックリストまとめ
育休中の配偶者控除と妻の年末調整について、詳しく見てきました。
育休中でも配偶者控除は受けられ、年間数万円の節税が可能です!

育児休業給付金は非課税なので、所得に含まれません。
そのため、育休中で給与がほとんどない場合、配偶者控除の条件(妻の年収123万円以下)を満たしやすいんです。
妻は自分の会社で年末調整を受け、夫は自分の会社で配偶者控除を申請します。
それぞれ別の手続きなので、両方しっかり対応しましょう。
よくある誤解は、育児休業給付金を収入と考えてしまうことです。給付金は非課税なので、いくらもらっても配偶者控除の判定には影響しません。
また、妻の年末調整も必要ないと思い込む人がいますが、育休中でも給与があれば年末調整の対象です。
配偶者控除を受けることで、夫の税金が年間で約7万円安くなります(配偶者控除38万円の場合)。
これは家計にとって大きな金額なので、必ず申請しましょう。
年末調整の提出期限は会社によって異なりますが、一般的には11月〜12月です。
期限を過ぎてしまっても、確定申告で申請できるので諦めないでください。

これで年末調整もバッチリね!7万円の節税は大きいわ♪

その調子にゃ!正しい知識で、家計をしっかり守るにゃ!
育休中の年末調整は複雑に見えますが、一度理解すれば簡単です。
「あと数万円稼げたのに…」「扶養を外れた方が実は手元に多く残ったのに…」
数年後にそう気づいても、過ぎた時間は戻ってきません。
今ならオンラインで、「あなたの場合、いくら稼ぐのが一番お金が貯まるか」をプロが無料で試算してくれます。
家計の健康診断だと思って、早めに一度チェックしてみてください。浮いたお金で家族旅行に行けるかもしれませんよ!
👉 【無料】何度でも相談OK!世帯年収を最大化するライフプラン相談はこちら![]()