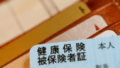「出産手当金、私はもらえないのかな…?」
「条件に当てはまらなかったらどうしよう」
「もらえないって聞いて不安になってきた…」
そんな心配を抱えていませんか?

確かに、出産手当金にはもらえないケースがあります。
でも大丈夫。もらえない理由にはパターンがあり、事前に確認すれば対策できることも多いんです。
この記事では、出産手当金がもらえない5つのケースと、それぞれの対処法を詳しく解説します。
もらえない場合でも使える支援制度もご紹介するので、一緒に確認していきましょう!
出産手当金がもらえないケース。まず確認すべきこと
もらえない理由には明確なパターンがある

出産手当金がもらえないケースは、大きく分けて5つのパターンがあります。
①国民健康保険に加入している
②健康保険の扶養に入っている
③任意継続被保険者である
④休業中に給与が支払われている
⑤申請期限を過ぎている
この5つのどれかに当てはまると、残念ながら出産手当金は受け取れません。
でも、それぞれに対処法や代替の支援制度があるので、諦める必要はないんです。

もらえないケースがこんなにあるなんて…不安になってきたわ

落ち着いて聞くにゃ。もらえなくても他の支援があるから、まずは自分がどのケースか確認するにゃ
自分の加入している保険を確認しよう

まず最初にチェックすべきは、自分がどの健康保険に加入しているか。
手元の保険証を見てみましょう。
「全国健康保険協会」や「◯◯健康保険組合」と書いてあれば、会社の健康保険に加入している可能性が高いです。
一方、「◯◯市国民健康保険」と書いてあれば国保加入なので、出産手当金の対象外。
保険証の記載内容で、ある程度判断できます。
被保険者本人かどうかが重要

保険証の種類だけでなく、「被保険者本人」かどうかも大切なポイント。
保険証には「被保険者」と「被扶養者」の欄があります。
自分の名前が「被保険者」の欄にあれば本人、「被扶養者」の欄にあれば扶養に入っている状態です。
出産手当金は被保険者本人だけが対象なので、扶養に入っている場合は受け取れません。
税務署から通知が来て青ざめる場合も...
もらえないケース①国民健康保険に加入している
国保には出産手当金の制度がない

国民健康保険には、そもそも出産手当金という制度がありません。
自営業やフリーランス、無職の方が加入している国保では、出産手当金は支給されないんです。
これは制度の仕組み上、どうしようもない部分。
国保加入者は、会社員のように産休中の給料補填を受けられる仕組みがないのが現実です。

フリーランスの友達、何ももらえないってこと?それって不公平じゃない!

その気持ちわかるにゃ。でも出産育児一時金は国保でももらえるから、全くゼロじゃないにゃ
国保加入者が使える支援制度

国保加入者でも、出産育児一時金は受け取れます。
これは出産費用を補助するための一時金で、基本的に42万円が支給されます。
出産手当金とは別の制度なので、国保でも問題なく受け取れるんです。
また、自治体によっては独自の出産支援金を設けているところもあるので、お住まいの市区町村に確認してみましょう。
自営業・フリーランスの出産準備

国保加入の自営業やフリーランスの方は、産前から経済的な準備が必要。
出産手当金がない分、自分で貯蓄するか、働き方を調整するしかありません。
産後すぐに仕事復帰が難しい場合は、数ヶ月分の生活費を事前に確保しておくことをおすすめします。
また、可能であれば産前産後だけパートナーの扶養に入るという選択肢も検討してみてください。
もらえないケース②健康保険の扶養に入っている
扶養は被保険者本人ではない

夫や親の健康保険の扶養に入っている場合、出産手当金は受け取れません。
出産手当金は「被保険者本人」だけが対象の制度。
扶養に入っている人は「被扶養者」という立場なので、対象外なんです。
専業主婦や扶養内パートの方の多くが、このケースに該当します。

扶養に入ってるけど、パートで働いてるのよ?それでもダメなの?

働いていても、扶養に入ってる限りは対象外にゃ。でも自分の会社の保険に入れば対象になるにゃ!
扶養を抜けて自分の保険に入る選択肢

パートで働いている場合、勤務先の社会保険に加入できる可能性があります。
週20時間以上勤務し、月収8.8万円以上などの条件を満たせば、社会保険の加入対象に。
自分の会社の健康保険に加入すれば、被保険者本人となり出産手当金も受け取れるようになります。
ただし、扶養を抜けると保険料の負担が発生するので、よく検討してから決めましょう。
社会保険加入の条件(2024年10月以降)
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8.8万円以上
・雇用期間が2ヶ月を超える見込み
・学生でないこと
・従業員51人以上の企業
扶養のままでも出産育児一時金は受け取れる

扶養に入っていても、出産育児一時金は問題なく受け取れます。
こちらは被扶養者でも対象なので、42万円の支援が受けられるんです。
出産手当金はもらえなくても、出産費用の補助は受けられるので安心してください。
また、児童手当も全員が対象なので、忘れずに申請しましょう。
もらえないケース③任意継続被保険者である
任意継続は原則対象外

退職後に健康保険を任意継続している場合、原則として出産手当金は受け取れません。
任意継続とは、退職後も最長2年間、元の会社の健康保険に加入し続ける制度。
保険料は全額自己負担になりますが、保険証はそのまま使えます。
ただし、出産手当金や傷病手当金などの現金給付は、基本的に対象外となるんです。
退職後は国保か扶養か選択を

退職後の健康保険は、任意継続・国保・扶養の3択。
任意継続を選ぶと保険料が高くなる上、出産手当金も受け取れないことが多いです。
配偶者の扶養に入れる場合は、保険料負担がゼロになるのでおすすめ。
扶養に入れない場合は、国保に加入するのが一般的です。
それぞれのメリット・デメリットをよく比較して選びましょう。
退職前に在職中の条件を満たせば受給可能

ただし、退職前に一定の条件を満たせば、退職後も出産手当金を受け取れます。
条件は以下の3つ。
①退職日まで継続して1年以上健康保険に加入
②退職日に出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしていた
③退職日に出勤していない
特に③が重要で、退職日に出勤してしまうと全額もらえなくなるので要注意です。
もらえないケース④休業中に給与が支払われている
給与が出ると手当金は支給されない

産休中に会社から給与が支払われている場合、出産手当金は支給されません。
出産手当金は「給与が支払われない期間」を補填する制度だからです。
すでに給料をもらっているのに、さらに手当金も受け取ることはできないんです。
ただし、給料が出産手当金の日額より少ない場合は、差額分が支給されます。

え?産休中も給料が出る会社もあるの?

福利厚生が充実している会社だと、産休中も一部給料が出ることがあるにゃ。その場合は手当金との調整になるにゃ
差額支給の仕組みを理解する

産休中に少しでも給料が出ている場合、給料が出産手当金の日額より少なければ差額が支給されます。
例えば、出産手当金の日額が5,000円で、会社から2,000円の給料が出ていたら、差額の3,000円が支給される仕組み。
逆に、会社から6,000円の給料が出ていたら、出産手当金は支給されません。
給料が多い方が得というわけではないので、しっかり確認しましょう。
給与と出産手当金の関係
・給料なし:出産手当金を全額支給
・給料あり(手当金より少):差額を支給
・給料あり(手当金より多):支給なし
会社の給与規定を事前に確認

産休に入る前に、会社の給与規定を確認しておくことが大切。
産休中も給料が出るのか、出る場合はいくらなのかを人事・総務部に聞いてみましょう。
給料が出る場合でも、出産手当金の日額より少なければ差額がもらえるので損にはなりません。
ただし、申請書類には給与支払いの有無を正しく記入する必要があるので注意してください。
もらえないケース⑤申請期限を過ぎている
出産手当金の申請期限は2年

出産手当金には、申請期限が2年間と決まっています。
産休開始日の翌日から2年以内に申請しないと、時効で受け取れなくなってしまうんです。
「後でまとめて申請しよう」と思っていると、うっかり期限を過ぎてしまうことも。
産後はバタバタして忘れがちなので、できるだけ早めに申請しましょう。

2年もあるなら大丈夫そうね!

油断は禁物にゃ!育児に追われてあっという間に時間が過ぎちゃうから、早めに申請するにゃ!
産後なるべく早く申請を済ませる

出産手当金は、産後56日を過ぎたらすぐに申請するのがおすすめ。
産前分と産後分をまとめて申請すれば、手続きは1回で済みます。
産後は赤ちゃんのお世話で忙しいですが、退院後すぐに医師の証明をもらい、会社に書類を提出しましょう。
早めに動けば、支給も早くなるので一石二鳥です。
期限切れになったら一切もらえない

2年の期限を1日でも過ぎると、一切もらえなくなります。
「知らなかった」「忘れていた」では済まないので、絶対に期限内に申請してください。
数十万円の手当金を受け取り損ねるのは、本当にもったいないです。
カレンダーやスマホのリマインダーに申請期限を登録して、忘れないようにしましょう。
出産手当金もらえないケース。それでも使える支援制度
出産育児一時金は全員が対象

出産手当金がもらえなくても、出産育児一時金は全員が受け取れます。
これは出産費用を補助するための一時金で、基本的に42万円が支給される制度。
国保でも、扶養でも、どんな健康保険に入っていても対象です。
ほとんどの病院で直接支払制度が使えるので、出産費用の窓口負担を減らせます。
自治体独自の出産支援金
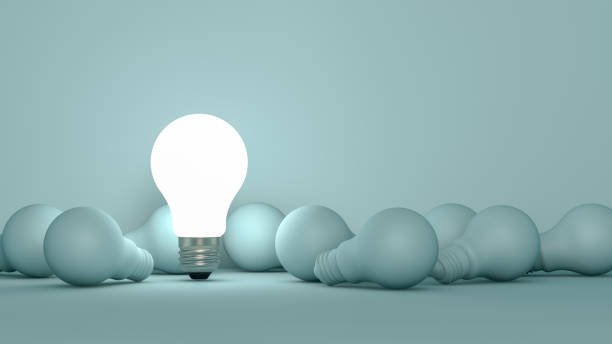
お住まいの自治体によっては、独自の出産支援金や子育て支援金があります。
金額は自治体により異なりますが、5万円〜30万円程度の給付金が受けられることも。
市区町村の子育て支援課や保健センターに問い合わせて、どんな支援があるか確認してみましょう。
申請しないともらえない制度がほとんどなので、積極的に情報収集してください。
生活が苦しいときは福祉資金貸付も

出産手当金がもらえず生活が厳しい場合、生活福祉資金貸付制度の利用を検討しましょう。
各自治体の社会福祉協議会が実施している公的な貸付制度で、低金利または無利子で借りられます。
出産や育児による一時的な生活費の不足にも対応しているので、まずは相談してみてください。
緊急小口資金なら、最大10万円まで無利子で借りられます。
出産手当金もらえないケース。確認と対策のまとめ
出産手当金がもらえないケースは、大きく分けて5つのパターンがあります。
でも、もらえなくても他の支援制度が使えるケースがほとんどです。

まずは自分がどのケースに当てはまるか、保険証を見て確認してください。
もらえない場合でも、出産育児一時金や自治体の支援金など、使える制度は必ずあります。
「知らなかった」で損をしないよう、産前からしっかり情報収集しておきましょう。
不明な点があれば、勤務先の人事・総務部や自治体の窓口に遠慮なく相談してください。
使える制度をすべて活用して、安心して出産・育児に臨みましょう。

もらえないケースでも、他の支援があるって分かって安心したわ!

その調子だにゃ!制度を知って、賢く活用していくにゃ!
「あと数万円稼げたのに…」「扶養を外れた方が実は手元に多く残ったのに…」
数年後にそう気づいても、過ぎた時間は戻ってきません。
今ならオンラインで、「あなたの場合、いくら稼ぐのが一番お金が貯まるか」をプロが無料で試算してくれます。
家計の健康診断だと思って、早めに一度チェックしてみてください。浮いたお金で家族旅行に行けるかもしれませんよ!
👉 【無料】何度でも相談OK!世帯年収を最大化するライフプラン相談はこちら![]()