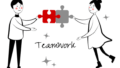「育休中、夫の扶養に入った方がお得なのかな?」
「配偶者控除を受けるとデメリットもあるって聞いたけど…」
「入った方がいいの?入らない方がいいの?」
そんな迷いを抱えていませんか?

育休中は収入が減るため、配偶者控除を受けられるケースが多いです。
でも、メリットばかりではなくデメリットもあるんです。
この記事では、育休中に配偶者控除を受けるデメリットとメリットを詳しく比較。入るべきか、入らない方がいいのか、判断材料をすべてお伝えします。
損をしないための注意点も解説するので、最後まで読んで賢く判断しましょう!
育休中の配偶者控除。まず基本を理解しよう
配偶者控除とは?育休中でも使える?

配偶者控除とは、配偶者の年間所得が48万円以下の場合、夫(または妻)の所得税を減額できる制度。
給与収入でいうと年103万円以下なら対象です。
育休中は給料が出ないことが多いため、年間の給与収入が103万円以下になるケースも。
その場合、配偶者控除を受けることができるんです。

育休中って給料出ないから、103万円以下になりそうね

そうだにゃ。でも賞与がある場合は要注意にゃ。それも年収に含まれるにゃ
育児休業給付金は収入に含まれない

ここで重要なのが、育児休業給付金は収入に含まれないということ。
育児休業給付金は非課税なので、年収103万円の計算には入りません。
つまり、育休中に育児休業給付金だけもらっていて、給料や賞与がほとんどなければ、配偶者控除の対象になりやすいんです。
ただし、年の途中まで働いていた給料や賞与は年収に含まれるので要注意。
年収103万円に含まれるもの・含まれないもの
・含まれる:給料、賞与(ボーナス)、各種手当
・含まれない:育児休業給付金、出産手当金、出産育児一時金
社会保険の扶養とは別の制度

混乱しやすいのが、配偶者控除(税金の扶養)と社会保険の扶養は全く別の制度だということ。
配偶者控除は年収103万円以下が条件。
社会保険の扶養は年収130万円未満が条件。
育休中は社会保険料が免除されているため、基本的に社会保険の扶養には入りません。
配偶者控除だけを受けるケースが多いんです。
税務署から通知が来て青ざめる場合も...
育休中に配偶者控除を受けるデメリット5つ
デメリット①収入制限を超えたら控除が受けられない

育休中でも賞与や給料が支払われる場合、年収が103万円を超えると配偶者控除は受けられません。
例えば、年の前半まで働いていて給料30万円×6ヶ月=180万円。
このケースだと、育休中でも年収が103万円を大きく超えるため対象外です。
年収が103万円超〜201万円以下なら配偶者特別控除が使えますが、控除額は段階的に減っていきます。

え?賞与も年収に含まれるの?それじゃ103万円超えちゃうかも!

賞与も含まれるにゃ!年末に源泉徴収票をもらったら、まず年収を確認するにゃ!
デメリット②手続きが煩雑になる可能性

配偶者控除を受けるには、夫の年末調整で申告が必要。
育休中だけ一時的に配偶者控除を受けて、復帰後は外す…という流れになります。
翌年の年末調整では「配偶者控除なし」に戻す必要があり、手続きが煩雑に感じることも。
また、年の途中で復帰して収入が増えると、年末に「控除対象外だった」と気づくケースもあります。
その場合、修正申告が必要になることもあるんです。
デメリット③将来の年金額への影響は限定的

配偶者控除を受けること自体は、将来の年金額には直接影響しません。
ただし、社会保険の扶養に入った場合は話が別。
厚生年金の加入期間が減るため、将来の年金額が減少する可能性があります。
育休中は社会保険料が免除されているだけで、厚生年金の加入期間としてカウントされるため、基本的には問題ありません。
配偶者控除だけを受けるなら、年金への影響は限定的です。
デメリット④復帰時の収入調整が必要

育休明けで復帰すると、年収が一気に103万円を超えます。
その年は配偶者控除を受けられないため、夫の税金が増えることに。
年の途中で復帰する場合、年収がどのくらいになるか計算して、配偶者控除の対象かどうか確認する必要があります。
うっかり申告してしまうと、後で修正が必要になるので注意してください。
デメリット⑤税制の変動に毎年対応が必要

配偶者控除の制度は、税制改正で条件が変わることがあります。
近年では、配偶者控除の所得制限が設けられるなど、制度が複雑化しています。
夫の年収が1,195万円を超えると、配偶者控除が受けられないケースも。
毎年、自分の年収と夫の年収を確認して、控除対象かどうかチェックする必要があるんです。
配偶者控除の所得制限(2024年現在)
・妻の年収:103万円以下(配偶者控除)
・妻の年収:103万円超〜201万円以下(配偶者特別控除)
・夫の年収:1,195万円超は控除対象外
育休中に配偶者控除を受けるメリット
メリット①夫の税金が安くなる

配偶者控除の最大のメリットは、夫の所得税と住民税が安くなること。
配偶者控除を受けると、夫の課税所得が最大38万円減額されます。
夫の所得税率が20%なら、38万円×20%=約7.6万円の節税。
さらに住民税も約3.3万円減るので、合計で年間10万円程度の節税効果があるんです。

年間10万円も節税できるなら、メリット大きいわね!

そうなんだにゃ!夫の所得税率が高いほど、節税効果も大きくなるにゃ!
メリット②育休中だけの一時的な節税

育休中は給料が減るため、その期間だけ配偶者控除を受けられるチャンス。
復帰後は年収が増えて対象外になりますが、育休中の1〜2年間だけでも節税効果は大きいです。
育休が年をまたぐ場合、2年連続で配偶者控除を受けられることも。
その場合、節税額は合計20万円近くになる可能性があります。
メリット③手続きは年末調整だけ

配偶者控除を受けるための手続きは、夫の年末調整で申告するだけ。
会社から配られる「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記入して提出すればOK。
特別な書類を用意する必要もなく、手続きは簡単です。
自分の年収(源泉徴収票で確認)が103万円以下なら、迷わず申告しましょう。
育休中の配偶者控除。入るべき?判断のポイント
年収103万円以下なら入った方が得

結論から言うと、年収が103万円以下なら配偶者控除を受けた方がお得。
デメリットより節税効果の方が大きいからです。
育休中だけの一時的な措置なので、手続きの煩雑さもそれほど気になりません。
まずは自分の源泉徴収票を確認して、年収が103万円以下かどうかチェックしましょう。
育児休業給付金は含まれないので、給料と賞与だけを確認すればOKです。
賞与がある場合は要注意

育休中でも、賞与(ボーナス)が支払われる場合は年収に注意。
例えば、年の前半に給料60万円、賞与50万円もらっていたら合計110万円。
この場合、配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除は受けられます。
配偶者特別控除は年収103万円超〜201万円以下が対象で、控除額は段階的に減ります。
自分の年収に応じて、どの控除が使えるか確認しましょう。
年収別の控除
・103万円以下:配偶者控除(最大38万円控除)
・103万円超〜150万円以下:配偶者特別控除(38万円控除)
・150万円超〜201万円以下:配偶者特別控除(段階的に減額)
復帰のタイミングも考慮する

年の途中で復帰する場合、復帰後の給料も年収に含まれます。
例えば、10月に復帰して月給20万円×3ヶ月=60万円。
年前半の給料50万円と合わせると110万円になり、配偶者控除は受けられません。
復帰のタイミングによって年収が変わるので、事前にシミュレーションしておきましょう。
年末が近い場合は、翌年1月から復帰する方が配偶者控除を受けやすいこともあります。
育休中配偶者控除のデメリット。賢く判断するまとめ
育休中に配偶者控除を受けることには、デメリットもありますがメリットの方が大きいケースが多いです。
年収103万円以下なら、迷わず配偶者控除を受けるべき。

大切なのは、自分の年収を正確に把握すること。
源泉徴収票で給料と賞与の合計を確認し、103万円以下なら配偶者控除を受けましょう。
育休明けの復帰時期も考慮に入れて、年収がどのくらいになるか計算してください。
不明な点があれば、夫の会社の人事・総務部や税務署に相談すると安心です。
制度を賢く活用して、少しでも家計の負担を減らしましょう。

デメリットもあるけど、メリットの方が大きいってわかったわ!年収を確認してみる!

その調子だにゃ!賢く節税して、育休中の生活を少しでも楽にするにゃ!
「あと数万円稼げたのに…」「扶養を外れた方が実は手元に多く残ったのに…」
数年後にそう気づいても、過ぎた時間は戻ってきません。
今ならオンラインで、「あなたの場合、いくら稼ぐのが一番お金が貯まるか」をプロが無料で試算してくれます。
家計の健康診断だと思って、早めに一度チェックしてみてください。浮いたお金で家族旅行に行けるかもしれませんよ!
👉 【無料】何度でも相談OK!世帯年収を最大化するライフプラン相談はこちら![]()