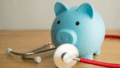「育休に入ったら収入が減る…旦那の扶養に入れるの?」
「給付金もらってるけど、扶養に入ったら損する?」
「一時的に入って、復帰したら抜けられる?」
そんな疑問を抱えていませんか?

実は、育休中に扶養に入るかどうかは、健康保険と税金で扱いが全く違います。
しかも、給付金をもらっているかどうかで判断が変わるんです。
この記事では、育休中に扶養に入る条件から、メリット・デメリット、公務員の特殊ケース、実際の手続き方法まで徹底解説します。
制度を正しく理解して、家計にとって最適な選択をしましょう!
育休中に扶養に入るとはどういうこと?
まず、「扶養に入る」という言葉の意味を整理していきましょう。
実はこの「扶養」、2種類あって混同しやすいんです。
健康保険の扶養と税法上の扶養は別物

「扶養」には、健康保険の扶養と、税法上の扶養という2つの制度があります。
健康保険の扶養は「社会保険の扶養」とも呼ばれ、配偶者の健康保険に加入すること。
一方、税法上の扶養は「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を受けることを指します。
この2つは基準も手続きも全く違うため、それぞれ別に考える必要があるんです。
育休中に「扶養に入る」と言ったとき、どちらの話をしているのかを明確にすることが大切。
2つの扶養の違い
・健康保険の扶養:配偶者の健康保険に加入、保険料負担なし
・税法上の扶養:配偶者控除で配偶者の税金が減る
・判断基準:収入の見込み額と実際の年間所得で異なる
・手続き先:健康保険は会社、税金は年末調整や確定申告

え?扶養って2種類あるの?全然知らなかったわ!

そうなんだにゃ。だから「扶養に入れる?」って聞かれたら、どっちの話かを確認する必要があるんだにゃ
育児休業給付金は扶養の判断にどう影響する?

育休中にもらえる育児休業給付金は、税法上は非課税ですが、健康保険の扶養判定では収入として扱われることがあります。
税金の計算では給付金は所得に含まれないため、給料がなければ配偶者控除を受けられます。
しかし、健康保険の扶養に入れるかどうかは、加入している健康保険組合によって判断が異なるんです。
多くの健保組合では給付金を収入とみなさない一方、一部の組合では収入にカウントします。
この違いが、育休中の扶養を複雑にしている大きな原因なんですよね。
一時的な収入減少は扶養に入れない可能性も

2021年の厚生労働省通達により、育休による収入減少は「一時的なもの」として扱われるようになりました。
つまり、普段は年収が高い人が育休で一時的に収入が減っても、健康保険の扶養には入りにくくなっています。
特に共働きで妻の年収が高い家庭では、育休中でも子どもを妻の扶養に入れるよう指導されることも。
「育休=自動的に扶養に入れる」というわけではないので注意が必要です。
復帰後の収入見込みも考慮されるため、ケースバイケースの判断になります。
税務署から通知が来て青ざめる場合も...
育休中に扶養に入れる条件を徹底解説
では、具体的にどんな条件なら扶養に入れるのでしょうか。
健康保険と税金、それぞれの基準を見ていきましょう。
健康保険の扶養に入る条件

健康保険の扶養に入るには、今後1年間の収入見込みが130万円未満(60歳未満の場合)という条件があります。
さらに、被保険者(配偶者)の収入の半分未満であることも必要。
育児休業給付金を収入に含むかどうかは、加入している健康保険組合の規定によります。
給付金を含めて130万円を超えるなら、扶養には入れません。
また、復帰後の給料が見込まれる場合、その金額も考慮されることがあります。
年収500万円の人が育休で一時的に収入ゼロになっても、「復帰すれば高収入」とみなされて扶養に入れないケースもあるんです。
税法上の扶養に入る条件

税法上の扶養(配偶者控除)に入るには、年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入なら103万円以下)という条件。
育児休業給付金や出産手当金は非課税なので、所得には含まれません。
つまり、育休中に給料をまったくもらっていなければ、配偶者控除の対象になります。
年の途中まで働いていて給料をもらっていた場合、その金額が103万円以下なら控除OK。
103万円を超えても201万円以下なら、配偶者特別控除が受けられます。
年末調整や確定申告で配偶者(夫)が申告することで、夫の税金が減る仕組みです。

給付金は税金の計算に入らないのね!これは助かるわ

そうなんだにゃ!だから育休中は税法上の扶養に入りやすいんだにゃ
給付金が終わった後なら扶養に入りやすい

育児休業給付金の支給が終わった後は、健康保険の扶養に入りやすくなります。
給付金がなくなれば、今後1年間の収入見込みがゼロになるため。
ただし、近いうちに復帰する予定があるなら、その収入見込みも考慮されます。
「あと2ヶ月で復帰して月給30万円」という状況なら、扶養に入れない可能性も。
逆に、育休を延長して当分復帰しないなら、扶養に入れる可能性が高まります。
自分の状況を会社や健保組合に正直に伝えて、判断してもらいましょう。
育休中に扶養に入るメリットとデメリット
扶養に入ることで得られるメリットと、知っておくべきデメリットを整理します。
育休中に扶養に入るメリット

育休中に扶養に入る最大のメリットは、配偶者の税金が減ること。
配偶者控除が適用されれば、配偶者(夫)の所得税と住民税が軽減されます。
年収500万円の夫なら、配偶者控除で年間5万円前後の節税になることも。
健康保険の扶養に入れれば、自分の健康保険料がかからなくなります。
育休中は社会保険料が免除されているため影響は少ないですが、給付金終了後に無給期間があるなら大きなメリット。
また、扶養手当がある会社なら、配偶者分の手当も受け取れる可能性があります。
育休中に扶養に入るデメリット
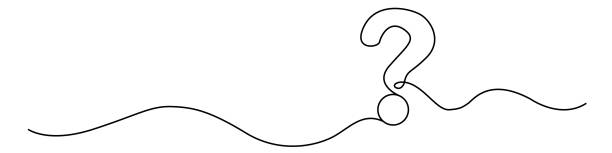
一方で、手続きの手間や将来への影響というデメリットもあります。
扶養に入る際と抜ける際、それぞれ会社への届け出が必要。
復帰のタイミングによっては、短期間で扶養を出入りすることになり面倒です。
また、健康保険の扶養に入っている期間は、厚生年金に加入していません。
その分、将来もらえる年金額が少なくなる可能性があるんです。
育休中は社会保険料免除で厚生年金の記録も残るため、わざわざ扶養に入ると逆に不利になることも。

手続きが面倒なのと、年金が減るのはちょっと気になるわね…

そうなんだにゃ。だから「入れるから入る」じゃなくて、メリットとデメリットを比較して判断するのが大事だにゃ
結局、扶養に入るべき?入らないべき?

扶養に入るべきかどうかは、育休の期間と復帰予定によって変わります。
育休が1年以上と長期で、給付金終了後も無給期間がある場合は、扶養に入るメリットが大きいです。
一方、育休が半年程度で早めに復帰する予定なら、手続きの手間を考えると入らない方が楽かもしれません。
税法上の扶養(配偶者控除)は、年末調整で簡単に申告できるため、条件を満たすなら必ず利用すべき。
健康保険の扶養は、自分の状況と健保組合の規定を確認してから判断しましょう。
公務員の育休中は扶養に入れるのか
公務員の場合、民間とはルールが異なるため注意が必要です。
公務員は健康保険の扶養に入れない

公務員の場合、育休中でも共済組合の被保険者であり続けるため、配偶者の健康保険の扶養には入れません。
民間企業の会社員なら、条件次第で配偶者の健康保険に入れる可能性がありますが、公務員は不可。
公務員は「共済組合」という独自の保険制度に加入しており、育休中でも脱退できないんです。
ただし、育休中は共済組合の掛金(保険料)が免除されるため、負担はありません。
配偶者が会社員でも、公務員本人は共済組合のままです。

公務員は特別なのね。知らなかったら混乱しちゃうところだったわ

そうだにゃ。公務員の場合は共済組合が強制だから、扶養には入れないんだにゃ
公務員でも税法上の扶養には入れる

一方、税法上の扶養(配偶者控除)は公務員でも適用可能です。
育休中の給付金は非課税なので、その年の給料が103万円以下なら配偶者控除が受けられます。
配偶者(夫)が会社員なら、夫の年末調整で配偶者控除を申告すればOK。
公務員だからといって、税金の控除が受けられないわけではありません。
むしろ、健康保険の扶養に入れない分、税法上の控除はしっかり活用すべきです。
公務員の扶養手当はどうなる?

公務員には「扶養手当」という制度があり、配偶者や子どもを扶養している場合に手当が支給されます。
扶養手当の条件は、年収130万円未満などの所得制限があります。
育休中で給料がない場合、配偶者の扶養手当の対象になる可能性も。
ただし、自治体や組織によって規定が異なるため、勤務先の人事担当に確認が必要です。
扶養手当は月額数千円から1万円程度ですが、年間で見ると家計の助けになります。
公務員の育休中の扶養まとめ
・健康保険の扶養:入れない(共済組合のまま)
・税法上の扶養:入れる(配偶者控除)
・扶養手当:条件次第で対象になる
・共済掛金:育休中は免除される
・確認先:勤務先の人事担当、共済組合
育休中の扶養。よくある誤解と注意点
育休中の扶養について、多くの人が誤解しているポイントを整理します。
誤解①育休中は自動的に扶養に入れる

「育休に入れば自動的に扶養に入れる」と思っている人も多いですが、実際には条件を満たす必要があります。
給付金をもらっている間は、収入があるとみなされて扶養に入れないことも。
また、一時的な収入減少では扶養対象にならない場合もあります。
「育休=扶養」と決めつけず、自分の状況を確認してから判断しましょう。
誤解②扶養に入らないと損をする

「扶養に入らないと損」と感じる人もいますが、状況によっては入らない方が良いケースもあります。
育休中は社会保険料が免除されているため、健康保険の扶養に入るメリットは小さいです。
むしろ、厚生年金の記録を残すためにも、扶養に入らず社会保険料免除を活用する方が有利。
税法上の扶養(配偶者控除)は節税になるので活用すべきですが、健康保険の扶養は慎重に判断を。

扶養に入らなきゃ!って焦ってたけど、そうでもないのね

その通りだにゃ!自分の状況に合わせて、ベストな選択をすればいいんだにゃ
扶養に入る・抜ける手続きは忘れずに
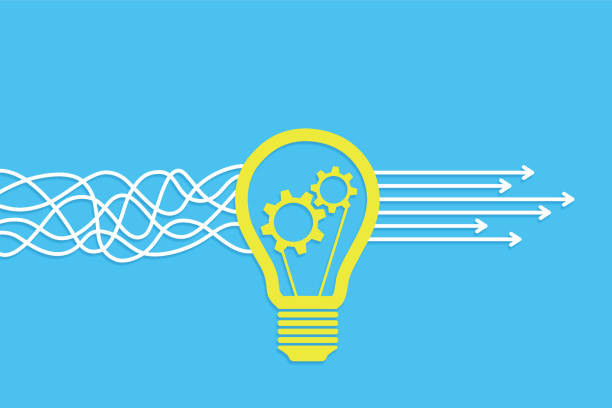
扶養に入る場合も抜ける場合も、必ず配偶者の会社に届け出が必要です。
扶養に入るときは「扶養認定申請書」を提出し、必要書類(給与がない証明など)を添付します。
復帰するときは「扶養削除届」を提出して、扶養から抜ける手続きをします。
この手続きを忘れると、保険証が使えなくなったり、後で精算が必要になったりするため要注意。
特に復帰時の扶養削除は忘れやすいので、事前に配偶者と確認しておきましょう。
育休中に扶養に入る。損しない選択のまとめ
育休中に扶養に入るかどうかは、健康保険と税金で判断が異なります。
自分の状況をしっかり確認して、家計にとって最適な選択をしましょう。

大切なのは、「入れるから入る」ではなく、「入った方が得かどうか」を考えること。
育休期間が長くて給付金終了後も無給期間があるなら、扶養に入るメリットが大きいです。
逆に、短期間で復帰するなら、手続きの手間を考えると入らない方が楽かもしれません。
税法上の扶養(配偶者控除)は、条件を満たすなら必ず活用しましょう。
年末調整で配偶者が申告するだけで、税金が減ります。
健康保険の扶養については、加入している健保組合の規定を確認してから判断を。
不安な場合は、配偶者の会社や健保組合に直接問い合わせるのが確実です。
制度は複雑ですが、正しく理解すれば家計の負担を減らせます。
焦らず、自分のペースで最適な選択を見つけてくださいね。
「扶養に入るか、それとも働き続けるか…」育休後の働き方に迷っているなら、自分に合った選択肢を見つけることが大切です。
しごママでは、主婦の再就職や働き方に関する情報を幅広く発信しています。あなたのライフスタイルに合った働き方を、一緒に探していきましょう。

複雑だったけど、だいぶ整理できたわ!自分の状況に合わせて考えればいいのね

その調子だにゃ!迷ったら専門家や会社に相談するのも忘れずににゃ!
「あと数万円稼げたのに…」「扶養を外れた方が実は手元に多く残ったのに…」
数年後にそう気づいても、過ぎた時間は戻ってきません。
今ならオンラインで、「あなたの場合、いくら稼ぐのが一番お金が貯まるか」をプロが無料で試算してくれます。
家計の健康診断だと思って、早めに一度チェックしてみてください。浮いたお金で家族旅行に行けるかもしれませんよ!
👉 【無料】何度でも相談OK!世帯年収を最大化するライフプラン相談はこちら![]()