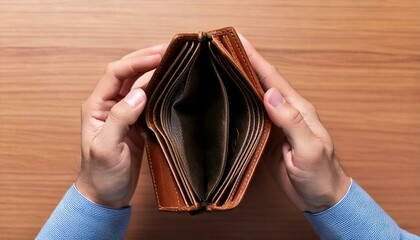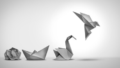「扶養控除と配偶者控除、どっちが得なの?」
「妻を扶養に入れるなら、どっちの控除を使えばいいの?」
「両方使えたら最強なのに…」
税金の控除について調べていると、こんな疑問が湧いてきますよね。

実は、扶養控除と配偶者控除は対象者が違うため、単純に「どっちが得」とは言えません。
しかし、家族構成や年収によっては、控除額に大きな差が出ることもあるんです。
この記事では、扶養控除と配偶者控除の違い、どっちを選ぶべきか、併用はできるのかなど、2025年最新の情報をもとに徹底解説します。
控除額の比較表や具体的なシミュレーションもご紹介しますので、あなたの家庭にピッタリの選び方が見つかりますよ!
扶養控除と配偶者控除の違いを理解しよう
まずは基本から。
扶養控除と配偶者控除は、対象となる家族が違うというのが最大のポイントです。
配偶者控除は「配偶者」だけが対象

配偶者控除は、その名の通り法律上の配偶者(妻または夫)だけが対象となる控除です。
たとえば、夫が会社員で妻がパート主婦の場合、夫の所得税計算の際に「配偶者控除」として妻の分を差し引けるんです。
2025年の税制改正で、これまで「103万円の壁」と言われていた基準が「123万円の壁」に変更されました。
基礎控除の引き上げにより、配偶者の年収が123万円以下であれば配偶者控除が受けられます。
扶養控除は「配偶者以外の家族」が対象

一方、扶養控除は配偶者以外の扶養親族が対象となります。
具体的には、子どもや両親、兄弟姉妹などですね。
注意すべきは、配偶者は扶養控除の対象外ということ。
配偶者については、配偶者控除または配偶者特別控除のどちらかを使うことになります。

えっ?妻は扶養控除の対象じゃないの?

そうなんだにゃ!配偶者は配偶者控除、それ以外は扶養控除って使い分けるんだにゃ!
扶養控除と配偶者控除の違いを比較表でチェック

違いが分かりやすいように、表でまとめてみました。
| 項目 | 配偶者控除 | 扶養控除 |
|---|---|---|
| 対象者 | 配偶者(妻・夫)のみ | 配偶者以外の親族 |
| 年齢要件 | なし(70歳以上は控除額UP) | 16歳以上 |
| 所得要件(対象者) | 年収123万円以下 | 年収103万円以下 |
| 所得要件(納税者) | 所得1,000万円以下 | 制限なし |
| 控除額 | 最大38万円(70歳以上48万円) | 38万円〜63万円(年齢で変動) |
このように、対象者がまず違うため、単純に「どっちが得」とは比較できないのが実情です。
税務署から通知が来て青ざめる場合も...
扶養控除と配偶者控除どっちが得?控除額で比較
では、控除額の面から「どっちが得か」を見ていきましょう。
対象者は違うものの、控除額の大きさは家計への影響に直結します。
配偶者控除の控除額はいくら?

配偶者控除の控除額は、配偶者の年齢と納税者本人の所得によって変わります。
| 配偶者の年齢 | 納税者の所得 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
|---|---|---|---|
| 70歳未満 | 900万円以下 | 38万円 | 33万円 |
| 70歳未満 | 900万円超〜950万円以下 | 26万円 | 22万円 |
| 70歳未満 | 950万円超〜1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 |
| 70歳以上 | 900万円以下 | 48万円 | 38万円 |
基本的には所得税で38万円、住民税で33万円の控除が受けられます。
配偶者が70歳以上の場合は、控除額が10万円アップして最大48万円になるんです。
扶養控除の控除額はいくら?

扶養控除の控除額は、扶養親族の年齢によって変わります。
| 扶養親族の区分 | 年齢 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
|---|---|---|---|
| 一般の扶養親族 | 16歳以上 | 38万円 | 33万円 |
| 特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 63万円 | 45万円 |
| 老人扶養親族(同居) | 70歳以上 | 58万円 | 45万円 |
| 老人扶養親族(別居) | 70歳以上 | 48万円 | 38万円 |
注目すべきは、特定扶養親族(大学生の子ども)の控除額が63万円と非常に大きいこと。
配偶者控除の38万円と比べても、25万円も多く控除されるんです。

えっ!大学生の子どもの方が控除額大きいの!?

そうなんだにゃ!教育費がかかる時期だから、国も税制で支援してくれてるんだにゃ!
控除額だけで見ると扶養控除が有利な場合も

控除額だけで比較すると、こんな傾向があります。
控除額の大きさランキング
1位:特定扶養親族(19〜22歳) → 63万円
2位:老人扶養親族(同居・70歳以上) → 58万円
3位:配偶者控除(70歳以上) → 48万円
4位:老人扶養親族(別居・70歳以上) → 48万円
5位:配偶者控除(70歳未満) → 38万円
5位:一般扶養控除(16歳以上) → 38万円
このように、大学生の子どもや同居の高齢親を扶養している場合、扶養控除の方が控除額は大きいことが分かります。
ただし、対象者が違うため、どちらか一方を選ぶというよりは「どちらも適切に活用する」という考え方が重要ですね。
扶養控除と配偶者控除は併用できる?
「扶養控除と配偶者控除、両方使えたら最強なのに!」
そう思った方も多いはず。
併用できるかどうか、詳しく見ていきましょう。
配偶者に対して両方は使えない

結論から言うと、同じ配偶者に対して配偶者控除と扶養控除の両方を適用することはできません。
配偶者については、配偶者控除または配偶者特別控除のどちらか一方のみ適用されます。
つまり、妻を「配偶者控除」として申告する場合、同時に「扶養控除」として申告することはできないということです。
配偶者以外の家族なら併用できる

ただし、配偶者と配偶者以外の家族がいる場合は、両方の控除を併用できます。
具体例を見てみましょう。
このように、配偶者控除と扶養控除は対象者が違えば併用可能なんです。
むしろ、該当する家族がいれば積極的に両方使うべきでしょう。

なるほど!妻と子どもで別々に控除が使えるのね♪

その通りにゃ!対象者が違えば併用OKだから、該当する家族がいるなら全部使うべきだにゃ!
配偶者特別控除との併用も可能

配偶者の年収が123万円を超えてしまった場合でも、配偶者特別控除が適用される可能性があります。
配偶者特別控除は、配偶者の年収が123万円超〜201.6万円以下の場合に段階的に控除が受けられる制度です。
| 配偶者の年収 | 所得税控除額 |
|---|---|
| 123万円超〜150万円以下 | 38万円 |
| 150万円超〜155万円以下 | 36万円 |
| 155万円超〜160万円以下 | 31万円 |
| 160万円超〜201.6万円以下 | 段階的に減少 |
配偶者特別控除を受けている場合でも、子どもや親に対する扶養控除は併用できます。
家族構成別!どっちが得かシミュレーション
ここからは、具体的な家族構成ごとに「どっちが得か」をシミュレーションしてみましょう。
ケース1:夫婦のみ(妻がパート)

【家族構成】夫(会社員・年収500万円)、妻(パート・年収100万円)
ケース2:夫婦+大学生の子ども

【家族構成】夫(会社員・年収600万円)、妻(パート・年収100万円)、子ども(大学生・20歳)
ケース3:夫婦+高齢の親と同居

【家族構成】夫(会社員・年収700万円)、妻(専業主婦)、夫の母(75歳・年金収入のみ)

わぁ!家族構成によって控除額がこんなに違うのね!

そうなんだにゃ!だから自分の家族構成に合った控除をしっかり使うことが大事なんだにゃ!
扶養控除と配偶者控除で注意すべきポイント
控除を受ける際に、知っておくべき注意点があります。
うっかりミスで控除が受けられなくなったり、後から追徴課税されたりしないよう、しっかり確認しておきましょう。
年収の壁を超えないように注意

配偶者控除や扶養控除を受けるためには、対象者の年収が一定額以下である必要があります。
特に年末にかけてシフトを増やす場合は、年収の見込みをしっかり計算しておきましょう。
重複適用はできない

同じ人を、複数の納税者が扶養親族として申告することはできません。
たとえば、妻を夫の配偶者控除の対象としている場合、妻を別の家族の扶養控除としても申告することはできないんです。
もし重複して申告してしまうと、税務署から指摘を受けて修正申告が必要になるため注意しましょう。
年末調整または確定申告で申告が必要

配偶者控除や扶養控除を受けるためには、年末調整または確定申告で申告する必要があります。
会社員の場合は、勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出します。
自営業やフリーランスの場合は、確定申告時に控除を申告しましょう。

うぅ…年末調整の書類、毎年よくわからなくて困ってたのよね…

大丈夫にゃ!書き方が分からなければ、会社の総務や税務署に相談すれば丁寧に教えてくれるにゃ!
扶養控除と配偶者控除どっちが得?まとめ
扶養控除と配偶者控除、どっちが得かについて解説してきました。

結論をまとめると、対象者が違うため単純に比較はできないものの、家族構成によって最適な使い方があります。
特に、大学生の子どもがいる家庭や高齢の親と同居している家庭は、扶養控除の恩恵が大きいです。
配偶者控除と併用することで、年間100万円以上の控除を受けられる場合もあります。
しごママでは、主婦の働き方や税金・社会保険に関する情報を発信しています。
扶養内で働くコツや年収の壁の攻略法など、役立つ記事が満載ですので、ぜひ他の記事もチェックしてみてください!

やっと違いが分かったわ!今年の年末調整、しっかり書けそう♪

その調子だにゃ!控除をしっかり使って、家計を守るんだにゃ!
「あと数万円稼げたのに…」「扶養を外れた方が実は手元に多く残ったのに…」
数年後にそう気づいても、過ぎた時間は戻ってきません。
今ならオンラインで、「あなたの場合、いくら稼ぐのが一番お金が貯まるか」をプロが無料で試算してくれます。
家計の健康診断だと思って、早めに一度チェックしてみてください。浮いたお金で家族旅行に行けるかもしれませんよ!
👉 【無料】何度でも相談OK!世帯年収を最大化するライフプラン相談はこちら![]()