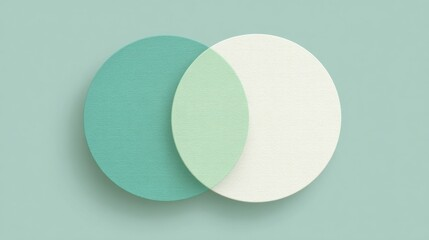「年末調整で、夫婦どちらも子どもを扶養に入れちゃった!」
「16歳未満の扶養親族が重複してるって連絡が来たんだけど…」
「これってまずいの?どうすればいいの?」
年末調整や確定申告で、こんな経験をされた方もいるのではないでしょうか。

実は、16歳未満の扶養親族が重複した場合、税務署や市区町村から指摘を受けることがあるんです。
16歳未満の子どもは所得税の扶養控除対象外ですが、住民税の計算には影響するため、きちんと対処する必要があります。
この記事では、16歳未満の扶養親族が重複した場合に何が起こるのか、どう対処すればいいのか、そもそもなぜ重複がダメなのかを分かりやすく解説します。
税務署からの指摘に慌てないよう、正しい知識を身につけておきましょう!
16歳未満の扶養親族が重複するとはどういうこと?
まずは基本から。
「16歳未満の扶養親族が重複する」とは、具体的にどういう状況なのでしょうか。
16歳未満の扶養親族重複とは?

16歳未満の扶養親族の重複とは、同じ子どもを夫婦の両方が扶養親族として申告してしまうことを指します。
たとえば、夫も妻も年末調整で「子ども(10歳)」を扶養親族欄に記入してしまったような場合ですね。
特に共働き家庭では、夫婦それぞれが自分の会社で年末調整を行うため、コミュニケーション不足で重複が発生しやすいんです。

えっ、夫婦で話し合わずに書類書いちゃうとダメなの?

そうなんだにゃ!同じ子を重複して申告すると、後で税務署から指摘を受けることになるんだにゃ!
16歳未満は所得税の扶養控除対象外
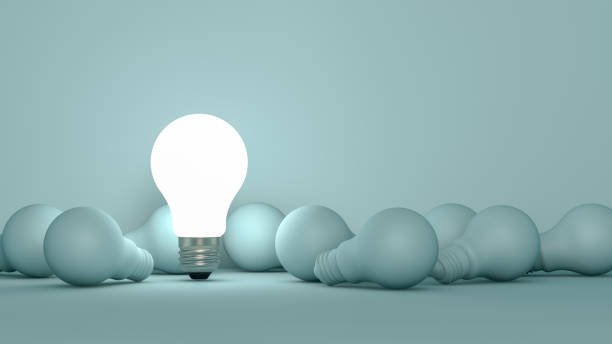
ここで重要なのは、16歳未満の子どもは所得税の扶養控除の対象外ということ。
2011年の税制改正で、児童手当(子ども手当)の導入に伴い、16歳未満の扶養控除は廃止されました。
つまり、16歳未満の子どもを扶養に入れても所得税は安くならないのですが、住民税の計算には影響するため、申告自体は必要なんです。
なぜ重複がダメなの?

「所得税には関係ないなら、重複しても問題ないんじゃない?」
そう思った方もいるかもしれません。
しかし、住民税の計算では扶養親族の人数が影響するため、重複は認められていないんです。
重複がダメな理由
1. 住民税の非課税判定に影響
扶養親族の人数で非課税限度額が変わる
2. 税務データの整合性の問題
同じ子どもが複数の納税者に紐づくとデータが矛盾
3. 不正受給の防止
将来的に控除が復活した場合の二重受給を防ぐ
特に住民税の非課税判定では、扶養親族の人数が重要な判定基準となるため、きちんと一方にまとめる必要があるんです。
税務署から通知が来て青ざめる場合も...
16歳未満の扶養親族が重複した場合どうなる?
では、実際に重複してしまった場合、何が起こるのでしょうか。
税務署や市区町村から連絡が来る

16歳未満の扶養親族が重複した場合、税務署や市区町村から「扶養が重複しています」という連絡が届きます。
年末調整後や確定申告後、数ヶ月経ってから通知が来ることが多いですね。
連絡の内容は、「どちらか一方に修正してください」という指導がほとんどです。
罰則があるわけではありませんが、放置すると住民税の計算に影響が出る可能性があるため、速やかに対応しましょう。
自動的にどちらか一方に調整される
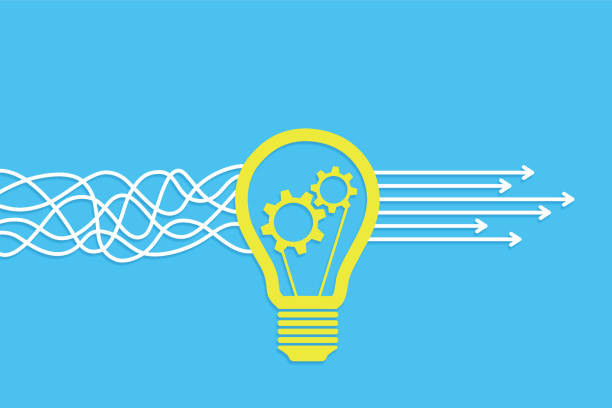
実は、重複が発覚した場合、市区町村側で自動的にどちらか一方に調整されることが多いです。
基本的には、先に申告した方に扶養親族として認められます。
| 調整の基準 | 内容 |
|---|---|
| 申告順 | 先に申告した方に扶養が認められる |
| 所得の高い方 | 市区町村によっては所得の高い方に調整 |
| 生計維持者 | 主に生計を維持している方に調整 |
ただし、自動調整の結果が必ずしも最適とは限らないため、自分で希望する方に修正したい場合は、早めに手続きを行う必要があります。

えっ、勝手に調整されちゃうの!?

そうなんだにゃ!でも、自分で希望する方に修正したいなら、早めに市区町村に連絡すれば変更できるにゃ!
住民税への影響がある場合も

16歳未満の扶養親族は、住民税の非課税判定に影響します。
特に所得が低い方は、扶養親族の人数によって住民税が非課税になる可能性があるため、重複の調整結果によっては税額が変わることもあるんです。
そのため、所得が低い方に扶養を入れた方が有利になるケースが多いですね。
16歳未満の扶養親族が重複した場合の対処法
では、実際に重複してしまった場合、どう対処すればいいのでしょうか。
年末調整の訂正で対処する

重複に気づいたのが年末調整の時期なら、会社に訂正を依頼しましょう。
年末調整の期間内であれば、比較的スムーズに修正できます。
会社によっては書類の再提出を求められることもあるため、早めに対応しましょう。
確定申告で修正する

年末調整の期間を過ぎてしまった場合や、自営業の方は確定申告で修正します。
確定申告での修正は、期限内(通常3月15日まで)なら何度でも訂正可能です。
最新の申告内容が有効となるため、気づいた時点ですぐに訂正しましょう。
市区町村に直接連絡する

税務署や市区町村から連絡が来た場合は、市区町村の住民税課に直接連絡するのが最も確実です。
市区町村によって手続き方法が異なる場合があるため、まずは電話で確認するのが確実です。

うぅ…市役所に電話するの緊張するわ…

大丈夫にゃ!担当者が丁寧に教えてくれるから、心配しなくていいにゃ!
16歳未満の扶養親族はどちらに入れるべき?
重複を防ぐためには、最初からどちらに扶養を入れるか決めておくことが大切です。
所得が低い方に入れると住民税で有利

基本的には、所得が低い方に扶養親族を入れる方が有利です。
住民税の非課税判定では、扶養親族の人数が多いほど非課税になる所得の範囲が広がるためです。
| ケース | おすすめの選択 |
|---|---|
| 夫:年収500万円 妻:年収100万円 | 妻の扶養に入れる → 妻の住民税が非課税になる可能性 |
| 夫:年収600万円 妻:年収300万円 | 妻の扶養に入れる → 妻の方が所得が低いため |
| 夫:年収800万円 妻:専業主婦 | 夫の扶養に入れる → 妻は所得がないため |
ただし、健康保険の扶養とは別なので、税金上の扶養と健康保険の扶養は別々に考える必要があります。
複数の子どもがいる場合は分散も可能

子どもが複数いる場合は、夫婦で分散して扶養に入れることも可能です。
どちらが有利かは、夫婦それぞれの所得や住民税の状況によって変わります。
税理士や市区町村の窓口に相談して、最適な方法を選びましょう。
年末調整前に夫婦で話し合う

最も大切なのは、年末調整の書類を記入する前に、夫婦で話し合っておくことです。
重複を防ぐためのチェックポイント
□ 年末調整の書類が届いたら、夫婦で一緒に確認
□ どちらが誰を扶養に入れるか事前に決める
□ 複数の子どもがいる場合は分け方を決める
□ お互いの記入内容を確認し合う
□ 毎年同じルールで統一する
共働き家庭では、それぞれが別々に書類を書いてしまいがちですが、必ず夫婦で確認し合うことが重複を防ぐ最大のポイントです。

なるほど!最初から話し合っておけば重複しないのね♪

その通りにゃ!毎年同じルールにしておけば、間違えることもないにゃ!
16歳未満の扶養親族が重複した場合の対処法:まとめ
16歳未満の扶養親族が重複した場合の対処法について、詳しく解説してきました。

最後に、重要なポイントをまとめておきます。
16歳未満の扶養親族は所得税には影響しませんが、住民税の計算には影響するため、きちんと一方にまとめることが大切です。
もし重複してしまっても、早めに対処すれば問題ありません。
慌てず、会社や市区町村に相談して修正手続きを進めましょう。
しごママでは、主婦の働き方や税金に関する情報を発信しています。
年末調整の書き方や扶養控除の仕組み、扶養内で働くコツなど、役立つ記事が満載です。ぜひ他の記事もチェックしてみてください!

よく分かったわ!今年の年末調整は、ちゃんと夫と相談して書くわね♪

その調子だにゃ!夫婦で協力して、正しく申告するんだにゃ!
「あと数万円稼げたのに…」「扶養を外れた方が実は手元に多く残ったのに…」
数年後にそう気づいても、過ぎた時間は戻ってきません。
今ならオンラインで、「あなたの場合、いくら稼ぐのが一番お金が貯まるか」をプロが無料で試算してくれます。
家計の健康診断だと思って、早めに一度チェックしてみてください。浮いたお金で家族旅行に行けるかもしれませんよ!
👉 【無料】何度でも相談OK!世帯年収を最大化するライフプラン相談はこちら![]()