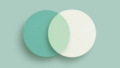「所得税の配偶者控除って何?」
「いくらまで働けば配偶者控除が受けられるの?」
「年末調整でどう書けばいいのか分からない…」
パートで働く主婦にとって、所得税配偶者控除は重要なテーマですよね。

実は、所得税配偶者控除を正しく活用すれば、年間10万円以上の節税になることもあるんです。
しかし、条件や申請方法を理解していないと、せっかくの控除が受けられない可能性も。
この記事では、所得税配偶者控除の基本から条件、控除額の計算方法、年末調整での申請手順まで、主婦が知っておくべき情報を完全網羅します。
2025年の税制改正情報も含めて、分かりやすく解説しますよ!
所得税配偶者控除とは?基本を理解しよう
まずは基本から。
所得税配偶者控除とは何か、しっかり理解しましょう。
所得税配偶者控除の仕組み

所得税配偶者控除とは、配偶者を扶養している納税者の所得税を軽減する制度です。
たとえば、夫が会社員で妻がパート主婦の場合、妻の年収が一定額以下なら、夫の所得税が安くなるという仕組みですね。
「課税所得から差し引く」というのがポイント。
所得税は「課税所得×税率」で計算されるため、課税所得が減れば税金も減るという仕組みなんです。

課税所得から差し引くって、どういうこと?

簡単に言うと、税金を計算する前の金額から38万円を引けるってことだにゃ!だから税金が安くなるんだにゃ!
所得税配偶者控除の対象者

所得税配偶者控除を受けられるのは、配偶者を扶養している納税者です。
つまり、収入が多い方(主に夫)が控除を受けることになります。
| 立場 | 役割 |
|---|---|
| 納税者 (控除を受ける人) | 主に収入が多い方 所得税が安くなる |
| 控除対象配偶者 (扶養される人) | 主に収入が少ない方 年収123万円以下が条件 |
共働き夫婦の場合、どちらが配偶者控除を受けるかは収入で決まります。
収入が多い方が納税者となり、収入が少ない方が控除対象配偶者となるのが一般的ですね。
2025年の税制改正で何が変わった?

2025年には、基礎控除の引き上げに伴い、所得税配偶者控除の基準も変更されました。
つまり、配偶者の年収が123万円以下なら所得税配偶者控除が受けられるようになったんです。
これまでより20万円も基準が上がったため、より多くの主婦が扶養内で働けるようになりました。
税務署から通知が来て青ざめる場合も...
所得税配偶者控除を受けるための条件
次に、所得税配偶者控除を受けるための具体的な条件を見ていきましょう。
配偶者の所得要件

所得税配偶者控除の最も重要な条件が、配偶者の年間所得です。
「合計所得58万円以下」と聞くと難しそうですが、給与収入なら年収123万円以下と覚えておけばOKです。
給与収入から給与所得控除(65万円)を引いた金額が所得となるため、123万円 – 65万円 = 58万円となるんですね。
納税者本人の所得制限

配偶者だけでなく、納税者本人にも所得制限があります。
高所得者の場合、所得税配偶者控除が使えない可能性があるため注意が必要です。
ただし、所得が900万円を超えると控除額が段階的に減少するため、詳しくは次の章で解説します。
その他の要件

所得要件以外にも、いくつかの条件があります。
所得税配偶者控除のその他の要件
✅ 法律上の配偶者であること
内縁関係や事実婚は対象外
✅ 生計を一にしていること
同居または生活費を共有している
✅ 青色事業専従者でないこと
個人事業主の配偶者として給与を受けていない
✅ 白色事業専従者でないこと
白色申告の専従者として申告していない
これらすべての条件を満たして初めて、所得税配偶者控除が受けられます。

わぁ、条件がいろいろあるのね!

でも普通のパート主婦なら、年収123万円以下で働いていれば基本的にOKだにゃ!
所得税配偶者控除の控除額はいくら?
条件を満たした場合、実際にいくら税金が安くなるのでしょうか。
所得税配偶者控除の控除額一覧

所得税配偶者控除の控除額は、配偶者の年齢と納税者の所得によって変わります。
| 配偶者の年齢 | 納税者の所得 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
|---|---|---|---|
| 70歳未満 | 900万円以下 | 38万円 | 33万円 |
| 70歳未満 | 900万円超〜950万円以下 | 26万円 | 22万円 |
| 70歳未満 | 950万円超〜1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 |
| 70歳以上 | 900万円以下 | 48万円 | 38万円 |
| 70歳以上 | 900万円超〜950万円以下 | 32万円 | 26万円 |
| 70歳以上 | 950万円超〜1,000万円以下 | 16万円 | 13万円 |
基本的には所得税で38万円、住民税で33万円の控除が受けられます。
配偶者が70歳以上の場合は、老人控除対象配偶者として控除額が10万円アップするのが特徴です。
実際の節税額を計算してみよう

控除額38万円というのは、課税所得から差し引かれる金額です。
実際の節税額は、納税者の税率によって変わります。
所得税配偶者控除による節税額の例
【夫の年収400万円の場合】
・所得税率:10%
・住民税率:10%
・所得税の節税額:38万円 × 10% = 3.8万円
・住民税の節税額:33万円 × 10% = 3.3万円
合計節税額:約7.1万円
【夫の年収600万円の場合】
・所得税率:20%
・住民税率:10%
・所得税の節税額:38万円 × 20% = 7.6万円
・住民税の節税額:33万円 × 10% = 3.3万円
合計節税額:約10.9万円
【夫の年収800万円の場合】
・所得税率:23%
・住民税率:10%
・所得税の節税額:38万円 × 23% = 8.7万円
・住民税の節税額:33万円 × 10% = 3.3万円
合計節税額:約12万円
このように、年収が高いほど税率が高くなるため、所得税配偶者控除による節税効果も大きくなります。
配偶者特別控除との違い

配偶者の年収が123万円を超えてしまった場合でも、配偶者特別控除が使える可能性があります。
| 項目 | 所得税配偶者控除 | 配偶者特別控除 |
|---|---|---|
| 対象年収 | 123万円以下 | 123万円超〜201.6万円以下 |
| 控除額 | 最大38万円(固定) | 3万円〜38万円(段階的) |
| 70歳以上の優遇 | あり(最大48万円) | なし |
年収150万円までは配偶者特別控除で満額38万円が受けられるため、少し超えても大きな損にはなりません。
所得税配偶者控除の申請方法
条件を満たしていても、申請しなければ控除は受けられません。
正しい申請方法を理解しておきましょう。
年末調整での申請方法

会社員の場合は、年末調整で所得税配偶者控除を申請します。
配偶者の所得見積額は、年収から給与所得控除65万円を引いた金額です。
たとえば、配偶者の年収が120万円なら、120万円 – 65万円 = 55万円が所得見積額となります。
確定申告での申請方法

自営業やフリーランスの方は、確定申告で所得税配偶者控除を申請します。
確定申告書の作成は、国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば、画面の指示に従って入力するだけで自動計算してくれます。
申請時の注意点

所得税配偶者控除を申請する際の注意点をまとめておきます。
特に、配偶者の年収が年末にかけて変動する場合は、年末調整の時点では見積額で申告し、確定後に大きく変わっていたら確定申告で修正しましょう。

うぅ…年末調整の書類、やっぱり難しそうだわ…

大丈夫にゃ!会社の総務の人が丁寧に教えてくれるから、分からなければ遠慮なく聞けばいいんだにゃ!
所得税配偶者控除を活用して賢く節税:まとめ
所得税配偶者控除について、詳しく解説してきました。

最後に、重要なポイントをまとめておきましょう。
所得税配偶者控除は、年間10万円前後の節税効果がある重要な制度です。
条件を満たしているなら、必ず年末調整または確定申告で申請しましょう。
配偶者の年収が123万円を少し超えても、配偶者特別控除でカバーできるケースも多いため、働き控えしすぎないことも大切です。
しごママでは、主婦の働き方や税金・社会保険に関する情報を発信しています。
年収の壁の攻略法や年末調整の書き方、扶養内で働くコツなど、役立つ記事が満載です。ぜひ他の記事もチェックしてみてください!

よく分かったわ!今年の年末調整、ちゃんと書けそうね♪

その調子だにゃ!所得税配偶者控除をしっかり活用して、賢く節税するんだにゃ!
「あと数万円稼げたのに…」「扶養を外れた方が実は手元に多く残ったのに…」
数年後にそう気づいても、過ぎた時間は戻ってきません。
今ならオンラインで、「あなたの場合、いくら稼ぐのが一番お金が貯まるか」をプロが無料で試算してくれます。
家計の健康診断だと思って、早めに一度チェックしてみてください。浮いたお金で家族旅行に行けるかもしれませんよ!
👉 【無料】何度でも相談OK!世帯年収を最大化するライフプラン相談はこちら![]()