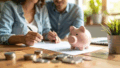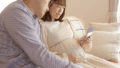「育休中だけど、配偶者控除って受けられるの?」
「年末調整の書類、どう書けばいいかわからない…」
「育児休業給付金も収入に入るの?」
育休中の税金や控除について、わからないことだらけで不安になりますよね。

実は、育休中でも配偶者控除は受けられます!
しかも育児休業給付金は非課税なので、収入に含まれません。
この記事では、育休中の配偶者控除の基本条件から年末調整での書き方、受けられる控除額、注意すべきポイントまで徹底解説!
2025年の税制改正情報も含めて、わかりやすくお伝えします。
育休中でも配偶者控除は受けられる!基本条件を確認
まず最初に知っておきたいのは、育休中でも配偶者控除は問題なく受けられるということです。
「給料がもらえないのに控除なんて…」と思っている方もいるかもしれませんが、実はそこがポイントなんです!
育休中の配偶者控除が認められる理由

育休中は多くの場合、会社からの給与が支給されないか、大幅に減額されます。
代わりに受け取る「育児休業給付金」は、非課税所得として扱われるため、年収の計算には含まれません。
つまり、育休中の1年間で会社からの給与が123万円以下なら、配偶者控除の対象になるわけです。
2025年改正で123万円に!配偶者控除の基本要件

2025年の税制改正により、配偶者控除の年収上限が大きく変わりました。
従来の「103万円の壁」から「123万円の壁」へと引き上げられたんです!
これにより、パート収入がある方も、より柔軟に働きながら控除を受けられるようになりました。
配偶者控除の基本要件(2025年版)
✓ 配偶者の年間給与収入が123万円以下(所得58万円以下)
✓ 納税者本人(配偶者の扶養者)の所得が1,000万円以下
✓ 配偶者が青色申告の事業専従者でないこと
✓ 配偶者が他の人の扶養親族でないこと
✓ 民法上の配偶者であること(内縁関係は対象外)

えっ!?123万円まで増えたの!?それってすごいことなのかしら?

そうだにゃ!20万円も上限が上がったから、パートで少し多めに働いても控除が受けられるようになったにゃ!
育児休業給付金は非課税。収入に含まれない

ここが一番大事なポイントです!
育児休業給付金は所得税法上の非課税所得として扱われます。
つまり、いくら給付金を受け取っても、配偶者控除の年収計算には一切含まれないんです。
例えば、育休中に育児休業給付金を100万円受け取っていても、会社からの給与が50万円だけなら、年収は「50万円」として計算されます。
税務署から通知が来て青ざめる場合も...
育休中の配偶者控除で受けられる控除額
それでは、実際にどのくらいの控除が受けられるのか見ていきましょう。
控除額は配偶者の年収と本人の所得によって変わります。
配偶者の年収別・控除額の一覧表

配偶者控除と配偶者特別控除の控除額を、わかりやすく表にまとめました。
| 配偶者の年収 | 配偶者の所得 | 控除の種類 | 控除額(本人所得900万円以下) |
|---|---|---|---|
| 123万円以下 | 58万円以下 | 配偶者控除 | 38万円 |
| 123万円超~160万円 | 58万円超~105万円 | 配偶者特別控除 | 38万円~3万円 |
| 160万円超~201万円 | 105万円超~133万円 | 配偶者特別控除 | 3万円~1万円 |
| 201万円超 | 133万円超 | 控除なし | 0円 |
育休中で会社からの給与がほとんどない場合、多くの方が配偶者控除38万円を満額受けられます。
これは、所得税の計算上、課税所得から38万円が差し引かれるということです。
本人の所得で変わる控除額

配偶者控除の金額は、納税者本人(配偶者を扶養する側)の所得によっても変わります。
| 本人の合計所得金額 | 配偶者控除額 | 配偶者特別控除額(最大) |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 | 38万円 |
| 900万円超~950万円以下 | 26万円 | 26万円 |
| 950万円超~1,000万円以下 | 13万円 | 13万円 |
| 1,000万円超 | 0円 | 0円 |
一般的な会社員の場合、年収が1,195万円以下であれば所得900万円以下に該当し、満額の38万円控除が受けられます。

えっと…38万円控除されるってことは、38万円もらえるってこと?

ちょっと待つにゃ!38万円が直接もらえるわけじゃないにゃ。課税所得から38万円引かれるから、税金が安くなるってことだにゃ!
配偶者特別控除との違いを理解する

配偶者控除と配偶者特別控除、名前が似ていて混乱しやすいですよね。
簡単に言うと、配偶者の年収が123万円を超えたら配偶者特別控除に切り替わるというイメージです。
配偶者控除と配偶者特別控除の違い
【配偶者控除】
・配偶者の年収123万円以下
・控除額は38万円(満額)
・条件がシンプル
【配偶者特別控除】
・配偶者の年収123万円超~201万円以下
・控除額は年収に応じて段階的に減少
・年収160万円までは満額38万円
2025年の改正で、配偶者特別控除の満額適用範囲も「年収160万円以下」に拡大されました。
育休明けにパート勤務を始める場合でも、年収160万円以下なら満額38万円の控除が受けられるわけです!
年末調整での配偶者控除申告書の書き方
ここからは、実際に年末調整で提出する書類の書き方を見ていきましょう。
難しそうに見えますが、ポイントを押さえれば誰でも記入できますよ!
記入が必要な書類と基本情報欄の書き方

配偶者控除を受けるために記入する書類は、正式には以下の名称です。
基本情報欄には、以下の項目を記入します。
記入する基本情報
✓ 配偶者の氏名(フルネーム)
✓ 配偶者の個人番号(マイナンバー)
✓ 配偶者の生年月日
✓ 配偶者の住所または居所(同居なら「同上」でOK)
✓ 令和7年中の配偶者の所得の見積額
マイナンバーは初回のみ記入が必要で、2回目以降は省略できる場合もあります。
会社の指示に従って記入しましょう。
配偶者の所得見積額の計算方法

ここが一番つまずきやすいポイントです!
「所得の見積額」は収入ではなく所得を記入します。
給与収入から給与所得控除を引いた金額が「所得」になります。
具体的な計算例を見てみましょう。
| 給与収入(年収) | 給与所得控除 | 所得金額 |
|---|---|---|
| 100万円 | 65万円 | 35万円 |
| 123万円 | 65万円 | 58万円 |
| 150万円 | 65万円 | 85万円 |
| 160万円 | 65万円 | 95万円 |
| 180万円 | 66万円 | 114万円 |
育休中で会社からの給与が50万円だけだった場合は、「50万円 − 65万円 = 0円」となり、所得は0円です。
この場合、申告書には「0円」または「0」と記入します。

うぅ…計算が難しくて頭がこんがらがっちゃう…

大丈夫にゃ!育休中なら給与がほとんどないから、所得はゼロか少額になるはずにゃ。育児休業給付金は計算に入れなくていいにゃ!
「育休中だけど、配偶者控除って受けられるの?」
「年末調整の書類、どう書けばいいかわからない…」
「育児休業給付金も収入に入るの?」
育休中の税金や控除について、わからないことだらけで不安になりますよね。

実は、育休中でも配偶者控除は受けられます!
しかも育児休業給付金は非課税なので、収入に含まれません。
この記事では、育休中の配偶者控除の基本条件から年末調整での書き方、受けられる控除額、注意すべきポイントまで徹底解説!
2026年の税制改正情報も含めて、わかりやすくお伝えします。
育休中でも配偶者控除は受けられる!基本条件を確認
まず最初に知っておきたいのは、育休中でも配偶者控除は問題なく受けられるということです。
「給料がもらえないのに控除なんて…」と思っている方もいるかもしれませんが、実はそこがポイントなんです!
育休中の配偶者控除が認められる理由

育休中は多くの場合、会社からの給与が支給されないか、大幅に減額されます。
代わりに受け取る「育児休業給付金」は、非課税所得として扱われるため、年収の計算には含まれません。
つまり、育休中の1年間で会社からの給与が123万円以下なら、配偶者控除の対象になるわけです。
2025年改正で123万円に!配偶者控除の基本要件

2025年の税制改正により、配偶者控除の年収上限が大きく変わりました。
従来の「103万円の壁」から「123万円の壁」へと引き上げられたんです!
これにより、パート収入がある方も、より柔軟に働きながら控除を受けられるようになりました。
配偶者控除の基本要件(2025年版)
✓ 配偶者の年間給与収入が123万円以下(所得58万円以下)
✓ 納税者本人(配偶者の扶養者)の所得が1,000万円以下
✓ 配偶者が青色申告の事業専従者でないこと
✓ 配偶者が他の人の扶養親族でないこと
✓ 民法上の配偶者であること(内縁関係は対象外)

えっ!?123万円まで増えたの!?それってすごいことなのかしら?

そうだにゃ!20万円も上限が上がったから、パートで少し多めに働いても控除が受けられるようになったにゃ!
育児休業給付金は非課税。収入に含まれない

ここが一番大事なポイントです!
育児休業給付金は所得税法上の非課税所得として扱われます。
つまり、いくら給付金を受け取っても、配偶者控除の年収計算には一切含まれないんです。
例えば、育休中に育児休業給付金を100万円受け取っていても、会社からの給与が50万円だけなら、年収は「50万円」として計算されます。
育休中の配偶者控除で受けられる控除額
それでは、実際にどのくらいの控除が受けられるのか見ていきましょう。
控除額は配偶者の年収と本人の所得によって変わります。
配偶者の年収別・控除額の一覧表

配偶者控除と配偶者特別控除の控除額を、わかりやすく表にまとめました。
| 配偶者の年収 | 配偶者の所得 | 控除の種類 | 控除額(本人所得900万円以下) |
|---|---|---|---|
| 123万円以下 | 58万円以下 | 配偶者控除 | 38万円 |
| 123万円超~160万円 | 58万円超~105万円 | 配偶者特別控除 | 38万円~3万円 |
| 160万円超~201万円 | 105万円超~133万円 | 配偶者特別控除 | 3万円~1万円 |
| 201万円超 | 133万円超 | 控除なし | 0円 |
育休中で会社からの給与がほとんどない場合、多くの方が配偶者控除38万円を満額受けられます。
これは、所得税の計算上、課税所得から38万円が差し引かれるということです。
本人の所得で変わる控除額

配偶者控除の金額は、納税者本人(配偶者を扶養する側)の所得によっても変わります。
| 本人の合計所得金額 | 配偶者控除額 | 配偶者特別控除額(最大) |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 | 38万円 |
| 900万円超~950万円以下 | 26万円 | 26万円 |
| 950万円超~1,000万円以下 | 13万円 | 13万円 |
| 1,000万円超 | 0円 | 0円 |
一般的な会社員の場合、年収が1,195万円以下であれば所得900万円以下に該当し、満額の38万円控除が受けられます。

えっと…38万円控除されるってことは、38万円もらえるってこと?

ちょっと待つにゃ!38万円が直接もらえるわけじゃないにゃ。課税所得から38万円引かれるから、税金が安くなるってことだにゃ!
配偶者特別控除との違いを理解する

配偶者控除と配偶者特別控除、名前が似ていて混乱しやすいですよね。
簡単に言うと、配偶者の年収が123万円を超えたら配偶者特別控除に切り替わるというイメージです。
配偶者控除と配偶者特別控除の違い
【配偶者控除】
・配偶者の年収123万円以下
・控除額は38万円(満額)
・条件がシンプル
【配偶者特別控除】
・配偶者の年収123万円超~201万円以下
・控除額は年収に応じて段階的に減少
・年収160万円までは満額38万円
2025年の改正で、配偶者特別控除の満額適用範囲も「年収160万円以下」に拡大されました。
育休明けにパート勤務を始める場合でも、年収160万円以下なら満額38万円の控除が受けられるわけです!
年末調整での配偶者控除申告書の書き方
ここからは、実際に年末調整で提出する書類の書き方を見ていきましょう。
難しそうに見えますが、ポイントを押さえれば誰でも記入できますよ!
記入が必要な書類と基本情報欄の書き方

配偶者控除を受けるために記入する書類は、正式には以下の名称です。
基本情報欄には、以下の項目を記入します。
記入する基本情報
✓ 配偶者の氏名(フルネーム)
✓ 配偶者の個人番号(マイナンバー)
✓ 配偶者の生年月日
✓ 配偶者の住所または居所(同居なら「同上」でOK)
✓ 令和7年中の配偶者の所得の見積額
マイナンバーは初回のみ記入が必要で、2回目以降は省略できる場合もあります。
会社の指示に従って記入しましょう。
配偶者の所得見積額の計算方法

ここが一番つまずきやすいポイントです!
「所得の見積額」は収入ではなく所得を記入します。
給与収入から給与所得控除を引いた金額が「所得」になります。
具体的な計算例を見てみましょう。
| 給与収入(年収) | 給与所得控除 | 所得金額 |
|---|---|---|
| 100万円 | 65万円 | 35万円 |
| 123万円 | 65万円 | 58万円 |
| 150万円 | 65万円 | 85万円 |
| 160万円 | 65万円 | 95万円 |
| 180万円 | 66万円 | 114万円 |
育休中で会社からの給与が50万円だけだった場合は、「50万円 − 65万円 = 0円」となり、所得は0円です。
この場合、申告書には「0円」または「0」と記入します。

うぅ…計算が難しくて頭がこんがらがっちゃう…

大丈夫にゃ!育休中なら給与がほとんどないから、所得はゼロか少額になるはずにゃ。育児休業給付金は計算に入れなくていいにゃ!
区分Ⅰ・区分Ⅱの判定と記入例

申告書には「区分Ⅰ」「区分Ⅱ」という欄があり、ここで控除額が決まります。
区分Ⅰは納税者本人(配偶者を扶養する側)の所得区分です。
| 本人の合計所得金額 | 区分Ⅰに記入する記号 |
|---|---|
| 900万円以下 | A |
| 900万円超~950万円以下 | B |
| 950万円超~1,000万円以下 | C |
区分Ⅱは配偶者の所得区分です。
| 配偶者の合計所得金額 | 区分Ⅱに記入する記号 |
|---|---|
| 58万円以下 | ① |
| 58万円超~95万円以下 | ② |
| 95万円超~105万円以下 | ③ |
| 105万円超~133万円以下 | ④ |
育休中で配偶者の所得が0円なら、区分Ⅱには「①」と記入します。
そして、区分ⅠとⅡの交点で控除額が決まります。
育休中の年末調整で注意すべきポイント
配偶者控除以外にも、育休中の年末調整で注意すべきことがあります。
知らないと損をすることもあるので、しっかり確認しましょう!
住民税は免除されない。前年分の納税義務

育休中に気をつけたいのが住民税です。
「今年は収入がないから住民税も払わなくていいのかな?」と思いがちですが、実は違うんです!
住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、育休中でも納税義務があります。
給料から天引きできない場合は、自治体から納付書が送られてくるので、忘れずに納付しましょう。
滞納すると延滞金が発生してしまいます。
社会保険料免除の申請も忘れずに

育休中は、健康保険料と厚生年金保険料が免除される制度があります。
これは配偶者控除とは別の制度ですが、非常に重要なので必ず申請しましょう!
育休中の社会保険料免除制度
✓ 健康保険料と厚生年金保険料が免除される
✓ 本人負担分も会社負担分も両方免除
✓ 免除期間中も年金額は減らない
✓ 会社を通じて申請が必要
✓ 育休開始月から育休終了月の前月まで免除
この制度を利用すれば、育休中の経済的負担が大きく軽減されます。
必ず会社の人事担当者に申請しましょう。

わぁ!社会保険料が免除されるなんて知らなかったわ!これは絶対申請しないと♪

そうだにゃ!しかも免除されても将来の年金額は減らないから、すごくお得な制度にゃ!
申告漏れや記入ミスが多い箇所

年末調整の申告書は、記入ミスや申告漏れが起きやすいです。
特に育休中の方がつまずきやすいポイントをまとめました。
記入が終わったら、必ず以下のポイントを確認しましょう。
提出前の最終チェックリスト
□ 配偶者の氏名・生年月日は正しいか
□ マイナンバーは記入したか(初回のみ)
□ 所得の見積額は「所得」で記入したか
□ 育児休業給付金を含めていないか
□ 区分ⅠとⅡの記号は正しいか
□ 提出期限は守れるか
わからないことがあれば、会社の人事担当者や税務署に確認するのが確実です。
恥ずかしがらずに質問しましょう!
育休中の配偶者控除と年末調整。まとめ
育休中でも配偶者控除は問題なく受けられます。
育児休業給付金は非課税なので、年収の計算には含まれません。

2025年の税制改正により、配偶者控除の年収上限が123万円に引き上げられました。
配偶者特別控除の満額適用範囲も160万円に拡大されたので、育休明けにパート勤務を始める場合でも控除を受けやすくなっています。
年末調整の申告書は、一見複雑に見えますが、ポイントを押さえれば誰でも記入できます。
育休中は収入が少ないからこそ、配偶者控除をしっかり活用して税金の負担を軽減しましょう。
わからないことがあれば、会社の人事担当者や税務署に相談するのが一番確実です。
制度をうまく活用して、育休中の経済的な不安を少しでも減らしていきましょう!

なるほど!育休中でも配偶者控除が受けられるってわかって安心したわ♪

その調子にゃ!制度をしっかり理解して、賢く活用していこうにゃ!
区分Ⅰ・区分Ⅱの判定と記入例

申告書には「区分Ⅰ」「区分Ⅱ」という欄があり、ここで控除額が決まります。
区分Ⅰは納税者本人(配偶者を扶養する側)の所得区分です。
| 本人の合計所得金額 | 区分Ⅰに記入する記号 |
|---|---|
| 900万円以下 | A |
| 900万円超~950万円以下 | B |
| 950万円超~1,000万円以下 | C |
区分Ⅱは配偶者の所得区分です。
| 配偶者の合計所得金額 | 区分Ⅱに記入する記号 |
|---|---|
| 58万円以下 | ① |
| 58万円超~95万円以下 | ② |
| 95万円超~105万円以下 | ③ |
| 105万円超~133万円以下 | ④ |
育休中で配偶者の所得が0円なら、区分Ⅱには「①」と記入します。
そして、区分ⅠとⅡの交点で控除額が決まります。
育休中の年末調整で注意すべきポイント
配偶者控除以外にも、育休中の年末調整で注意すべきことがあります。
知らないと損をすることもあるので、しっかり確認しましょう!
住民税は免除されない。前年分の納税義務

育休中に気をつけたいのが住民税です。
「今年は収入がないから住民税も払わなくていいのかな?」と思いがちですが、実は違うんです!
住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、育休中でも納税義務があります。
給料から天引きできない場合は、自治体から納付書が送られてくるので、忘れずに納付しましょう。
滞納すると延滞金が発生してしまいます。
社会保険料免除の申請も忘れずに

育休中は、健康保険料と厚生年金保険料が免除される制度があります。
これは配偶者控除とは別の制度ですが、非常に重要なので必ず申請しましょう!
育休中の社会保険料免除制度
✓ 健康保険料と厚生年金保険料が免除される
✓ 本人負担分も会社負担分も両方免除
✓ 免除期間中も年金額は減らない
✓ 会社を通じて申請が必要
✓ 育休開始月から育休終了月の前月まで免除
この制度を利用すれば、育休中の経済的負担が大きく軽減されます。
必ず会社の人事担当者に申請しましょう。

わぁ!社会保険料が免除されるなんて知らなかったわ!これは絶対申請しないと♪

そうだにゃ!しかも免除されても将来の年金額は減らないから、すごくお得な制度にゃ!
申告漏れや記入ミスが多い箇所

年末調整の申告書は、記入ミスや申告漏れが起きやすいです。
特に育休中の方がつまずきやすいポイントをまとめました。
記入が終わったら、必ず以下のポイントを確認しましょう。
提出前の最終チェックリスト
□ 配偶者の氏名・生年月日は正しいか
□ マイナンバーは記入したか(初回のみ)
□ 所得の見積額は「所得」で記入したか
□ 育児休業給付金を含めていないか
□ 区分ⅠとⅡの記号は正しいか
□ 提出期限は守れるか
わからないことがあれば、会社の人事担当者や税務署に確認するのが確実です。
恥ずかしがらずに質問しましょう!
育休中の配偶者控除と年末調整。まとめ
育休中でも配偶者控除は問題なく受けられます。
育児休業給付金は非課税なので、年収の計算には含まれません。

2025年の税制改正により、配偶者控除の年収上限が123万円に引き上げられました。
配偶者特別控除の満額適用範囲も160万円に拡大されたので、育休明けにパート勤務を始める場合でも控除を受けやすくなっています。
年末調整の申告書は、一見複雑に見えますが、ポイントを押さえれば誰でも記入できます。
育休中は収入が少ないからこそ、配偶者控除をしっかり活用して税金の負担を軽減しましょう。
わからないことがあれば、会社の人事担当者や税務署に相談するのが一番確実です。
制度をうまく活用して、育休中の経済的な不安を少しでも減らしていきましょう!

なるほど!育休中でも配偶者控除が受けられるってわかって安心したわ♪

その調子にゃ!制度をしっかり理解して、賢く活用していこうにゃ!
「あと数万円稼げたのに…」「扶養を外れた方が実は手元に多く残ったのに…」
数年後にそう気づいても、過ぎた時間は戻ってきません。
今ならオンラインで、「あなたの場合、いくら稼ぐのが一番お金が貯まるか」をプロが無料で試算してくれます。
家計の健康診断だと思って、早めに一度チェックしてみてください。浮いたお金で家族旅行に行けるかもしれませんよ!
👉 【無料】何度でも相談OK!世帯年収を最大化するライフプラン相談はこちら![]()