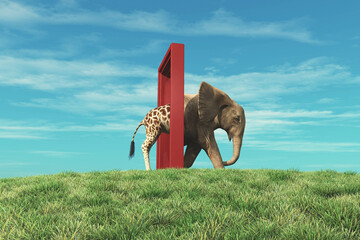「正社員で働いてるのに扶養に入れるの?」
「共働きなのに扶養って矛盾してない?」
「2026年の改正で何が変わるの?」
こんな疑問を持っている方、実はとても多いんです。

実は、正社員として働いていても条件次第で扶養に入れます!
しかも2026年の改正で、扶養のルールが大きく変わるんです。
この記事では、共働きで妻が正社員の場合の扶養制度について、2026年改正の内容を中心に徹底解説!
税制上の扶養と社会保険上の扶養の違い、パターン別の賢い活用方法、具体的な手続きまで分かりやすくお伝えします。
共働きで妻が正社員でも扶養に入れるって本当?
まず結論から言うと、正社員でも扶養に入ることは可能です!
「正社員=扶養に入れない」というイメージを持っている方が多いのですが、これは大きな誤解なんです。
扶養に入るってどういうこと?

「扶養に入る」には、実は2種類あります。
この2つを混同している人がとても多いので、まずはここをしっかり理解しましょう。
扶養の2つの種類
①税制上の扶養
夫の所得税・住民税が安くなる制度。配偶者控除や配偶者特別控除が該当します。
②社会保険上の扶養
妻が夫の健康保険・厚生年金に加入し、自分で保険料を払わなくていい制度。
この2つはそれぞれ条件が異なります。
税制上の扶養に入っていても、社会保険上は扶養から外れているというケースもあるんです。
正社員でも扶養対象になる条件とは

正社員でも扶養に入れる条件を見ていきましょう。
雇用形態(正社員・パート・派遣など)は関係なく、収入と勤務時間が判断基準になります。
| 扶養の種類 | 2025年現在の条件 | 2026年以降の条件 |
|---|---|---|
| 税制上の扶養 | 年収123万円以下 | 年収123万円以下(変更なし) |
| 社会保険上の扶養 | 年収106万円または130万円未満 | 週20時間未満の勤務(収入要件撤廃) |
注目すべきは、2026年から社会保険の扶養要件が大きく変わることです!
これまでの「年収○○万円」という基準から、「週○○時間」という勤務時間ベースの基準に変わります。
多くの人が誤解している「扶養」の真実

扶養について、よくある誤解をいくつか紹介します。
特に「103万円の壁」については、2025年に既に123万円に引き上げられています。
古い情報のまま働き方を制限している人も多いので、最新の制度をしっかり把握することが大切です。

えっ!?正社員でも扶養に入れるの!?知らなかったわ!

そうなんだにゃ!雇用形態じゃなくて、収入と勤務時間が重要なんだにゃ!
税務署から通知が来て青ざめる場合も...
2026年改正で大きく変わる扶養のルール。共働き正社員妻への影響
2026年から、扶養制度が大きく変わります。
特に社会保険の扶養要件が劇的に変化するので、共働き世帯は必ずチェックしてください!
所得税の配偶者控除が123万円に引き上げ済み

まず税制面では、2025年から既に変更が適用されています。
従来の「103万円の壁」が123万円に引き上げられました。
配偶者控除・配偶者特別控除の新基準
年収123万円以下
→ 配偶者控除が満額適用(夫の所得税から38万円控除)
年収123万円超〜201万円
→ 配偶者特別控除が段階的に適用
年収201万円超
→ 控除なし
つまり、正社員でも年収123万円以下に抑えられれば、夫の税金が安くなる恩恵を受けられます。
ただし、123万円を超えても201万円までは段階的に控除が適用されるので、「絶対に123万円以下にしなきゃ!」と焦る必要はありません。
2026年から社会保険の扶養要件が大幅変更

そして、最も大きな変更が2026年10月からの社会保険の扶養要件です。
これまでの「年収106万円」「年収130万円」という基準が撤廃され、週の勤務時間だけが判断基準になります。
| 項目 | 2025年まで | 2026年10月以降 |
|---|---|---|
| 判断基準 | 年収106万円または130万円未満 | 週20時間未満の勤務 |
| 従業員数要件 | 従業員51人以上の事業所 | 全事業所(従業員数不問) |
| 学生の扱い | 適用除外あり | 適用除外なし |
この変更により、週20時間以上働くと自動的に社会保険加入となり、扶養から外れます。
逆に言えば、週20時間未満なら年収がいくらでも扶養に入れるということです。
収入要件が撤廃されて週20時間が新基準に

2026年改正の最大のポイントは、収入額ではなく勤務時間が基準になること。
これまでは「年収を○○万円以内に抑えよう」と調整していた人も多かったですが、今後は「週○時間働くか」が重要になります。
例えば時給3,000円で週15時間働けば月収18万円、年収216万円になります。
これまでなら年収130万円を超えているので扶養から外れていましたが、2026年以降は週20時間未満なので扶養に入れるんです。

えっ?年収200万円超えても扶養に入れるの?すごい!

ちょっと待つにゃ!それは社会保険の扶養だけで、税制上の扶養は123万円までだにゃ!
共働きで妻が正社員の場合の扶養パターン別解説
ここからは、共働きで妻が正社員として働く場合の具体的なパターンを見ていきましょう。
自分がどのパターンに当てはまるか、ぜひチェックしてみてください!
パターン1:年収123万円以下で働く正社員妻

正社員でも、短時間勤務や時短勤務で年収123万円以下に抑えている場合です。
このパターンなら、税制上も社会保険上も扶養に入れる可能性が高いです。
ただし注意点として、2026年以降は週20時間以上働くと社会保険加入が必須になります。
年収123万円以下でも週20時間以上なら、自分で健康保険・厚生年金に加入し、保険料を払うことになります。
パターン2:産休・育休中の正社員妻

正社員として働いていても、産休・育休中は収入が減少します。
このタイミングで一時的に夫の扶養に入ることができるんです!
産休・育休中の扶養のポイント
税制上の扶養
その年の年収見込みが123万円以下なら、配偶者控除が適用可能。年末調整で申告すれば夫の税金が還付されます。
社会保険上の扶養
育休中で給付金のみの収入なら、夫の健康保険の扶養に入れる場合があります。ただし会社の健康保険組合によって判断が異なるので要確認。
特に育休が1年以上にわたる場合、その年の収入が大幅に減るので、扶養に入ることで家計の負担を軽減できます。
復職したら扶養から外れることになりますが、一時的でも活用する価値は大きいです。
パターン3:時短勤務中の正社員妻

育児や介護で時短勤務を選択している正社員の方も多いですよね。
時短勤務の場合、勤務時間と年収次第で扶養に入れる可能性があります。
例えば、フルタイム(週40時間)から時短勤務(週20時間未満)に変更した場合を見てみましょう。
| 項目 | フルタイム | 時短勤務(週16時間) |
|---|---|---|
| 週の勤務時間 | 40時間 | 16時間 |
| 月収(時給2,000円で計算) | 約32万円 | 約13万円 |
| 年収 | 約384万円 | 約156万円 |
| 社会保険の扶養 | ×(自分で加入) | ◯(2026年以降も扶養OK) |
| 税制上の扶養 | ×(控除なし) | △(特別控除のみ) |
週16時間の時短勤務なら、2026年以降も社会保険の扶養に入れます。
ただし年収156万円なので、税制上の配偶者控除(123万円以下)は受けられず、配偶者特別控除の対象になります。

時短勤務なら扶養に入れるのね!これは助かるわ♪

週20時間未満がポイントにゃ!会社に時短の相談をするときは、この時間を意識するといいにゃ!
正社員妻が扶養に入るメリットとデメリット
扶養に入ることには、メリットもデメリットもあります。
どちらが自分にとって得なのか、しっかり比較して判断しましょう。
扶養に入るメリットは税金と社会保険料の節約

扶養に入る最大のメリットは、家計全体での手取りが増えることです。
社会保険の扶養に入れば、年間で20万円〜30万円もの保険料負担がなくなります。
これは手取り収入として考えると、かなり大きな金額ですよね。
デメリットは将来の年金額と収入の制限

一方で、扶養に入ることのデメリットも理解しておく必要があります。
特に将来の年金額は大きなポイント。
厚生年金に加入していれば、老後にもらえる年金は月額15万円〜20万円になりますが、国民年金のみだと月額6.5万円程度です。
この差は、老後の生活に大きく影響します。
どちらがお得?世帯収入で考えるべき理由

「扶養に入るべきか、外れるべきか」は、世帯全体の収入で考えることが大切です。
個人の手取りだけでなく、家族全体でどれだけお金が残るかを計算してみましょう。
判断の目安
扶養に入ったほうがお得なケース
・妻の年収が150万円以下
・子育てや介護で長時間働けない
・夫の収入が高く、扶養控除の節税効果が大きい
扶養を外れて働いたほうがお得なケース
・妻の年収が180万円以上見込める
・キャリアを重視したい
・将来の年金額を増やしたい
一般的に、妻の年収が150万円〜180万円の間は「中途半端ゾーン」と言われています。
扶養を外れて社会保険料を払うと、手取りが減ってしまうことがあるんです。
ただし、長期的に見れば厚生年金に加入することで将来の年金が増えるので、「今の手取り」だけでなく「将来の安心」も含めて考えましょう。

うぅ…目先の手取りか、将来の年金か…悩むわ〜

家族の状況や将来の計画によって正解は違うにゃ。迷ったらファイナンシャルプランナーに相談するのもありだにゃ!
共働き正社員妻の扶養。実際の手続きと注意点
扶養に入ると決めたら、次は具体的な手続きです。
難しそうに見えますが、手順を押さえれば意外とシンプルですよ!
扶養に入るための具体的な手続き方法

扶養に入る手続きは、税制上の扶養と社会保険上の扶養で異なります。
税制上の扶養に入る手続き
①年末調整で申告
夫の会社で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出。妻の氏名・マイナンバー・所得見込額を記入します。
②必要書類
・妻のマイナンバーカードまたは通知カード
・妻の源泉徴収票(年収確認用)
・産休・育休の場合は給付金の明細
③期限
年末調整の時期(11月〜12月)に会社から案内があります。年の途中で扶養に入った場合も、年末調整で申告すればOK。
社会保険上の扶養に入る手続き
①会社の人事部に申し出る
夫の勤務先の人事部または総務部に「妻を健康保険の扶養に入れたい」と申し出ます。
②必要書類を提出
・健康保険被扶養者(異動)届
・妻の収入証明書(源泉徴収票や給与明細)
・妻の年金手帳
・戸籍謄本(必要な場合あり)
③審査
健康保険組合が妻の収入や勤務時間を確認し、扶養認定の可否を判断します。認定されると、妻の健康保険証が発行されます。
社会保険の扶養は、健康保険組合によって審査基準が微妙に異なります。
事前に夫の会社の人事部に「うちの健保組合では、どんな条件なら扶養に入れますか?」と確認しておくと安心です。
年末調整で忘れてはいけない申告書類

税制上の扶養を活用するには、年末調整での申告が必須です。
ここで申告漏れがあると、せっかくの控除を受けられません!
産休・育休中の方は、給付金の額を正しく把握しておくことが大切です。
出産手当金や育児休業給付金は非課税なので、年収に含めなくてOK!
つまり、給与収入が少なくても給付金で生活している場合、年収123万円以下になりやすいんです。
扶養から外れるタイミングの見極め方
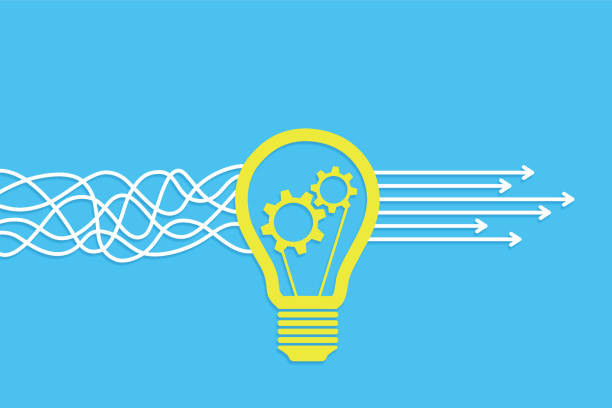
扶養に入ったあとも、いつ扶養から外れるべきかを見極めることが重要です。
扶養から外れるタイミングを誤ると、保険料の二重払いや追徴課税が発生することもあります。
扶養から外れるべきタイミング
税制上の扶養
・年収が123万円を超える見込みになったとき
・年の途中でも外れる必要はなく、年末調整で正しく申告すればOK
社会保険上の扶養
・週20時間以上働くようになったとき(2026年以降)
・年収130万円を超える見込みになったとき(2025年まで)
・外れるタイミングは、勤務条件が変わった月から
特に注意が必要なのは、育休明けで復職するときです。
育休中に夫の扶養に入っていた場合、復職したらすぐに扶養から外れる手続きをしましょう。
手続きが遅れると、健康保険証が使えなかったり、保険料の計算がややこしくなったりします。

年末調整の書類、毎年よく分からずに出してたわ…

年末調整で正しく申告しないと、数万円損することもあるにゃ!しっかり確認するにゃ!
共働き妻が正社員で扶養を活用する賢い働き方。まとめ
共働きで妻が正社員として働く場合でも、条件次第で扶養に入ることは十分可能です。
特に2026年からは社会保険の扶養要件が大きく変わり、週20時間未満の勤務なら収入に関わらず扶養に入れるようになります。

扶養に入るべきか、外れて働くべきかは、家庭の状況や将来の計画によって変わります。
今の家計だけでなく、将来のライフプランも含めて考えることが大切です。
2026年の改正は、働く女性にとって大きな転換期になります。
「週20時間未満」という新しい基準を理解して、自分に合った働き方を見つけてください!
迷ったときは、夫の会社の人事部や税理士、ファイナンシャルプランナーに相談するのもおすすめです。
一人で悩まず、専門家の力も借りながら、賢く扶養制度を活用していきましょう。

正社員でも扶養に入れるって分かって安心したわ!2026年の改正も理解できた♪

その調子にゃ!自分に合った働き方を見つけて、賢く制度を活用していくにゃ!
「あと数万円稼げたのに…」「扶養を外れた方が実は手元に多く残ったのに…」
数年後にそう気づいても、過ぎた時間は戻ってきません。
今ならオンラインで、「あなたの場合、いくら稼ぐのが一番お金が貯まるか」をプロが無料で試算してくれます。
家計の健康診断だと思って、早めに一度チェックしてみてください。浮いたお金で家族旅行に行けるかもしれませんよ!
👉 【無料】何度でも相談OK!世帯年収を最大化するライフプラン相談はこちら![]()