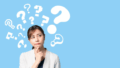「病気で仕事を辞めざるを得なくなった…」
「これから治療費もかかるのに、国民健康保険料まで高額で払えない…」
病気による退職は、体調面だけでなく経済面でも大きな不安を抱えることになります。
でも安心してください。病気で退職した場合、国民健康保険料の減免を受けられる制度があるんです。

この記事では、病気で退職した方が利用できる国民健康保険料の減免制度について、条件や申請方法まで詳しく解説します。
少しでも経済的負担を減らして、治療に専念できる環境を整えましょう。
病気で退職した場合の国民健康保険料減免制度とは
病気で退職した場合に使える減免制度は、主に2つあります。
あなたの状況に応じて、どちらか、または両方を利用できる可能性があります。
特定理由離職者としての減免制度

病気で退職した場合、「特定理由離職者」として国民健康保険料の軽減を受けられます。
これは、病気など正当な理由がある自己都合退職を、会社都合退職と同じように扱う制度です。
この制度を使えば、前年の給与所得を30%として計算してもらえるため、保険料が大幅に安くなります。
生活困難による減免制度

病気で働けず収入が著しく減少した場合や、治療費の負担が大きい場合は、生活困難による減免制度も利用できます。
これは、特定理由離職者の軽減とは別の制度で、現在の生活状況を考慮して保険料を減免してもらえるものです。
自治体によって基準は異なりますが、疾病や負傷で就労不能な場合、保険料の一部または全額が免除される可能性があります。

えっ?病気で退職しても保険料を安くしてもらえるの?

そうにゃ!病気という正当な理由がある退職は、減免の対象になるにゃ!
どちらの制度を使えばいいか

基本的には、まず特定理由離職者の軽減を申請しましょう。
こちらは雇用保険受給資格者証があれば比較的簡単に申請できます。
その上で、特定理由離職者の軽減だけでは生活が苦しい場合は、生活困難による減免も追加で申請できます。
どちらを申請すべきか
・雇用保険に加入していた→まず特定理由離職者の軽減を申請
・雇用保険未加入だった→生活困難による減免を申請
・両方の条件を満たす→両方申請することも可能
税務署から通知が来て青ざめる場合も...
病気で退職した場合の国民健康保険料減免の条件
ここからは、それぞれの制度を利用するための具体的な条件を見ていきましょう。
特定理由離職者の軽減を受ける条件

特定理由離職者として軽減を受けるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
特定理由離職者の条件
・離職時の年齢が65歳未満
・雇用保険の受給資格者である
・離職理由コードが23、33、34のいずれか
・国民健康保険に加入している
病気で退職した場合、離職理由コードは通常33または34になります。
33は「体力不足、心身の障害、疾病、負傷等により離職した者」、34は「妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた者」を指します。
生活困難による減免を受ける条件

生活困難による減免を受けるには、以下のような条件があります。
生活困難による減免の対象例
・疾病や負傷により就労が困難
・収入が前年より著しく減少した(30%以上減など)
・医療費の負担が大きく生活が困難
・障害により働けない
・生活保護に準ずる状況
ただし、具体的な基準は自治体によって異なります。
「生活が苦しい」と感じたら、まずは市区町村の窓口で相談してみることをおすすめします。

えぇっ!?両方の制度を使えることもあるの!?

そうにゃ!条件を満たせば、両方申請してさらに負担を減らせる可能性があるにゃ!
軽減期間と減免率

それぞれの制度の軽減期間と減免率は以下の通りです。
| 制度 | 軽減・減免の内容 | 期間 |
|---|---|---|
| 特定理由離職者の軽減 | 前年の給与所得を30%として計算 | 離職日の翌日から翌年度末まで(最大約2年) |
| 生活困難による減免 | 所得や状況に応じて一部または全額免除 | 自治体により異なる(通常は1年ごとに更新) |
特定理由離職者の軽減は期間が決まっていますが、生活困難による減免は状況が続く限り更新できる場合があります。
病気で退職した場合の国民健康保険料減免の申請方法
ここからは、実際に減免を受けるための申請方法を詳しく解説します。
特定理由離職者の軽減申請の手順

特定理由離職者の軽減を申請する手順は以下の通りです。
申請の流れ
1. ハローワークで失業保険の手続きをする
2. 雇用保険受給資格者証を受け取る
3. 離職理由コードを確認する(33または34であることを確認)
4. 市区町村の国民健康保険担当窓口へ行く
5. 雇用保険受給資格者証を提示して申請書を記入
6. 審査後、軽減が適用される
必要書類は以下の通りです。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 雇用保険受給資格者証(原本) | ハローワークで発行 |
| 国民健康保険証 | 既に加入している場合 |
| マイナンバーカード | または通知カード |
| 本人確認書類 | 運転免許証など |
| 印鑑 | 自治体により不要な場合も |
生活困難による減免申請の手順

生活困難による減免を申請する手順は以下の通りです。
申請の流れ
1. 市区町村の国民健康保険担当窓口に相談する
2. 減免申請書をもらう
3. 必要書類を準備する
4. 申請書と必要書類を提出する
5. 審査(通常1〜2か月)
6. 承認されれば減免が適用される
必要書類は、自治体や状況によって異なりますが、一般的には以下のようなものが求められます。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 減免申請書 | 窓口でもらえる |
| 医師の診断書 | 病名、就労困難であることの証明 |
| 所得証明書 | 前年と今年の見込み |
| 離職票または退職証明書 | 退職理由を証明 |
| 通帳のコピー | 収入状況の確認用 |

診断書が必要なのね。病院に行かないと…

そうにゃ。治療中の病院で診断書を書いてもらえるにゃ。先生に相談してみてにゃ!
申請時の注意点とポイント

減免申請をする際の注意点とポイントをまとめます。
申請のポイント
・申請は自動では適用されない。必ず自分で手続きが必要
・申請した月からの適用なので、早めに行動する
・分からないことは窓口で遠慮なく質問する
・郵送申請に対応している自治体もある
・減免が承認されない場合でも、分割納付の相談ができる
特に、「申請しないと自動では適用されない」という点は重要です。
病気で体調が悪い中での手続きは大変ですが、経済的負担を減らすためにも、ぜひ申請してください。
病気で退職した場合に他に使える制度
国民健康保険料の減免以外にも、病気で退職した方が利用できる制度があります。
傷病手当金の継続受給

会社の健康保険に加入していた期間が1年以上あれば、退職後も傷病手当金を継続して受け取れる場合があります。
傷病手当金とは、病気やけがで働けなくなったときに、給料の約3分の2を受け取れる制度です。
退職日の前日まで継続して受給していれば、退職後も引き続き受給できます。最長で1年6か月間受け取れるため、大きな経済的支援になります。
国民年金保険料の免除

病気で働けず収入が減った場合、国民年金保険料の免除も申請できます。
所得が一定以下であれば、全額免除または一部免除が受けられます。
免除された期間も、将来の年金受給資格には含まれるため(受給額は減りますが)、納付が困難な場合は必ず申請しましょう。
高額療養費制度

医療費が高額になった場合は、高額療養費制度を利用しましょう。
この制度を使えば、1か月の医療費が一定額を超えた分が払い戻されます。
所得に応じて自己負担限度額が決まっており、たとえば年収約370万円以下の方なら、月の自己負担は約5万7千円が上限です。

わぁ!他にも使える制度がいろいろあるのね♪

そうにゃ!困ったときに使える制度はたくさんあるにゃ!どんどん活用してにゃ!
病気で退職した場合の国民健康保険減免。諦めずに申請しよう:まとめ
病気で退職した場合、経済的な不安は大きいですよね。
でも、国民健康保険料の減免制度をしっかり活用すれば、負担を大きく軽減できます。

大切なのは、自分から申請すること。
制度は自動では適用されないため、必ず窓口で手続きを行いましょう。
この記事のポイント
・病気で退職した場合、2つの減免制度が利用できる
・特定理由離職者の軽減:前年の給与所得を30%として計算
・生活困難による減免:現在の状況に応じて一部または全額免除
・離職理由コードが33または34なら特定理由離職者の対象
・申請は自動適用されない。必ず自分で手続きが必要
・傷病手当金や国民年金免除など、他の制度も併用できる
病気の治療は長期戦になることもあります。
経済的な負担を少しでも減らして、治療に専念できる環境を整えましょう。
分からないことがあれば、市区町村の窓口で相談すれば丁寧に教えてもらえます。
一人で抱え込まず、使える制度はしっかり活用してくださいね。

よく分かったわ!病気で大変だけど、減免の申請をしてみるわね♪

その調子にゃ!制度をしっかり使って、まずは体を治すことに集中してにゃ!応援してるにゃ!
「あと数万円稼げたのに…」「扶養を外れた方が実は手元に多く残ったのに…」
数年後にそう気づいても、過ぎた時間は戻ってきません。
今ならオンラインで、「あなたの場合、いくら稼ぐのが一番お金が貯まるか」をプロが無料で試算してくれます。
家計の健康診断だと思って、早めに一度チェックしてみてください。浮いたお金で家族旅行に行けるかもしれませんよ!
👉 【無料】何度でも相談OK!世帯年収を最大化するライフプラン相談はこちら![]()