「国民健康保険料の請求書を見たけど、この金額ってどうやって決まってるの?」
「前年と収入変わってないのに、なんで保険料が上がってるの?」
「家族4人だと、こんなに高くなるの?」
国民健康保険料の金額を見て、疑問に思ったことはありませんか。

実は、国民健康保険料は前年の所得・世帯の加入者数・年齢などをもとに複雑な計算式で決まっています。
「なんでこんなに高いの?」と感じるのは、計算の仕組みを知らないからかもしれません。
この記事では、国民健康保険料がどうやって決まるのか、計算方法をわかりやすく解説します。
仕組みを理解すれば、「なぜこの金額になるのか」が納得できるはずです。さらに、保険料を抑える方法や、払えないときの対処法もご紹介します。
国民健康保険料はどうやって決まる?3つの構成要素
国民健康保険料は、3つの要素を合計して計算されます。
この3つの構成要素を理解することが、保険料の仕組みを知る第一歩です。
医療分・後期高齢者支援金分・介護分の3つ

国民健康保険料は、以下の3つの部分に分かれています。
国民健康保険料の3つの構成要素
・医療分:実際の医療費に充てられる部分
・後期高齢者支援金分:75歳以上の高齢者医療を支える部分
・介護分:介護保険に充てられる部分(40歳~64歳のみ)
この3つがそれぞれ計算され、合計した金額があなたの年間保険料になるんです。
ちなみに、介護分は40歳から64歳までの人だけが負担します。
だから、40歳になると突然保険料が跳ね上がったように感じるわけです。
39歳までは医療分と後期高齢者支援金分の2つだけでしたが、40歳の誕生日を迎えると介護分が追加されるため、月に数千円の負担増となります。

えっ!?40歳から介護分も払うの!?知らなかった!

そうなんだにゃ。だから40歳の誕生日を迎えると保険料が上がるんだにゃ
所得割・均等割・平等割の3つの計算方式

さらに、医療分・後期高齢者支援金分・介護分のそれぞれが、以下の3つの方式で計算されます。
つまり、保険料は「あなたの所得」と「世帯の人数」の両方で決まるということなんです。
収入が高い人ほど所得割が高くなり、家族が多い人ほど均等割が高くなります。
たとえば、年収500万円の単身者と、年収300万円の4人家族では、総保険料が逆転することもあるんです。
所得は低くても、加入者が多ければ均等割が積み重なって高額になるためです。
自治体によって計算方法が違う

国民健康保険料は、市区町村ごとに計算方法が違います。
同じ所得・同じ家族構成でも、住んでいる自治体が違えば保険料が数万円も変わることがあるんです。
たとえば、東京23区では平等割を採用していないところが多いですが、地方自治体では平等割を採用しているところもあります。
また、所得割の料率も自治体によって異なるため、保険料に地域差が生まれるわけです。
実際、年収400万円・夫婦2人世帯の場合、東京都内でも区によって年間保険料が5万円以上違うこともあります。
税務署から通知が来て青ざめる場合も...
国民健康保険料の所得割はどうやって計算される?
それでは、保険料の中で最も金額が大きくなる所得割の計算方法を詳しく見ていきましょう。
所得割を理解すれば、「なんでこんなに高いの?」という疑問が解消されるはずです。
前年の所得から基礎控除を引いた金額が基準

所得割は、前年の総所得金額-基礎控除を基準に計算されます。
基礎控除は2025年現在、43万円です。
たとえば、前年の総所得が300万円だった場合。
300万円-43万円=257万円
この257万円が、所得割の計算のベースになるんです。
ここで注意したいのは、「所得」と「収入」は違うということ。
サラリーマンの場合、収入から給与所得控除を引いた金額が「所得」になります。
たとえば年収400万円の場合、給与所得控除後の所得は約276万円。
ここから基礎控除43万円を引くと、233万円が所得割の計算ベースになります。

基礎控除って何?43万円引けるってこと?

そうだにゃ。誰でも43万円は控除されるから、その分だけ保険料の計算ベースが下がるんだにゃ
自治体ごとの料率を掛けて所得割額が決まる

基礎控除後の所得に、自治体ごとの料率を掛けると所得割額が計算できます。
料率は自治体によって違いますが、だいたい以下のような目安です。
たとえば、基礎控除後の所得が257万円の場合。
医療分:257万円×7.32%=約18.8万円
後期高齢者支援金分:257万円×2.22%=約5.7万円
介護分(40歳以上):257万円×1.64%=約4.2万円
合計で約28.7万円が所得割として計算されるわけです。
これはあくまで所得割だけの金額なので、ここに均等割や平等割が加算されると、年間保険料は30万円を超えることもあります。
収入が高いほど所得割も高くなる
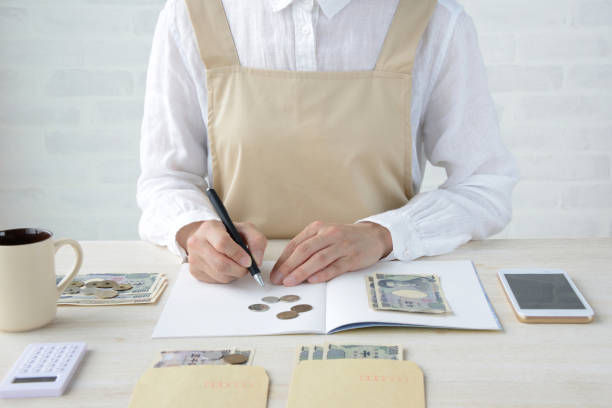
所得割は所得に比例するため、収入が高いほど保険料も高くなります。
前年に年収500万円だった人と、年収200万円だった人では、所得割の金額が倍以上違うこともあるんです。
これが「国民健康保険料は高い」と感じる理由の一つ。
会社員時代は会社が半分負担してくれていたのに、国民健康保険では全額自己負担だからです。
たとえば会社員時代に月2万円の保険料を払っていたとしたら、実は会社も2万円負担していたので、実質負担は4万円分だったということ。
退職して国民健康保険に切り替えると、その4万円を全額自分で払うことになるため、負担が倍に感じられるんです。
国民健康保険料の均等割と平等割はどう決まる?
所得割の次に大きな金額を占めるのが、均等割と平等割です。
この2つは、世帯の人数によって決まります。
均等割は加入者1人あたりの定額

均等割は、国民健康保険に加入している人の人数に応じて決まります。
たとえば、東京23区では1人あたり以下のような金額が設定されています。
均等割の金額の目安(東京23区の例)
・医療分:年間約4万円
・後期高齢者支援金分:年間約1.3万円
・介護分(40歳~64歳):年間約1.7万円
つまり、夫婦2人で加入していれば、均等割だけで年間約10万円~14万円かかるということなんです。
子どもが2人いれば、さらに倍になります。
4人家族で全員が国民健康保険に加入している場合、均等割だけで年間20万円~28万円の負担になることもあるわけです。
これに所得割が加わるため、家族が多い世帯ほど保険料の負担が重くなります。

えっ!家族が多いと、それだけで保険料が跳ね上がるの!?

そうなんだにゃ。国民健康保険には扶養という概念がないから、家族全員分の保険料がかかるんだにゃ
平等割は世帯ごとの定額

平等割は、世帯単位で一定額が加算される仕組みです。
ただし、平等割を採用していない自治体も多く、特に東京23区ではほとんどの区が平等割を廃止しています。
平等割がある自治体では、世帯あたり年間数千円~数万円が加算されることがあります。
平等割は世帯の人数に関係なく一定額なので、単身世帯にとっては負担感が大きく、逆に大家族にとっては相対的に負担が軽くなる仕組みです。
所得が低い世帯には軽減制度がある

所得が低い世帯には、均等割と平等割が自動的に軽減される制度があります。
世帯全体の所得が一定以下なら、2割・5割・7割の軽減が適用されるんです。
この軽減は申請不要で自動適用されますが、所得の申告をしていないと適用されないので注意が必要です。
特に無職の方や収入が少ない方は、必ず住民税の申告(収入がなかったという申告)をしておきましょう。
申告をしないと「所得不明」として軽減が適用されず、満額請求されてしまうことがあります。
国民健康保険料を抑える方法はある?
計算の仕組みはわかったけど、やっぱり高い…。
そう感じる方のために、国民健康保険料を少しでも抑える方法をご紹介します。
会社都合退職なら非自発的失業者の軽減制度を使う
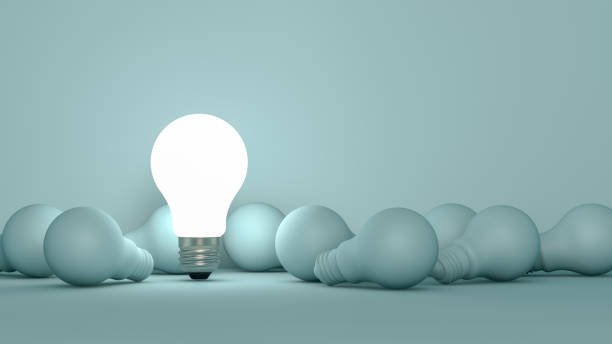
会社都合で退職した方は、非自発的失業者の軽減制度を必ず申請しましょう。
これは、前年所得を30%として計算してくれる制度です。
たとえば前年所得が300万円だった場合、90万円として計算されるため、保険料が大幅に安くなります。
この制度を使えば、年間で10万円以上保険料が安くなることも珍しくありません。
申請には雇用保険受給資格者証が必要なので、ハローワークで手続きをした後、市区町村の窓口で申請してください。
世帯分離で保険料が下がるケースもある

同居している家族と世帯分離をすることで、保険料が下がることがあります。
国民健康保険料は世帯単位で計算されるため、高所得の家族と同じ世帯だと、その所得も合算されて計算されてしまうからです。
ただし、世帯分離にはデメリットもあるので、事前に市区町村の窓口でよく相談してから判断しましょう。
払えないときは減免制度や分割納付を相談

どうしても払えないときは、減免制度や分割納付の相談をしましょう。
収入が大幅に減少した場合や、災害・病気などで生活が困窮している場合は、保険料の一部または全額が免除されることがあります。
また、一括では払えなくても、分割なら払えるという場合は、窓口で相談すれば無理のない支払いプランを組んでくれます。
絶対にやってはいけないのは、払えないからといって放置すること。
滞納すると延滞金が発生し、保険証が使えなくなり、最悪の場合は財産の差し押さえにまで発展します。
国民健康保険料はどうやって決まる?計算の仕組みを理解しよう:まとめ
国民健康保険料がどうやって決まるのか、理解できましたか?

保険料は、前年の所得・世帯の加入者数・年齢という3つの要素で決まります。
そして、医療分・後期高齢者支援金分・介護分のそれぞれに、所得割・均等割・平等割という3つの計算方式が適用されるんです。
「なんでこんなに高いの?」と感じていた理由も、仕組みを知れば納得できたのではないでしょうか。
国民健康保険料は、前年の所得で計算されるため、今は収入がなくても高額になることがあります。
また、会社員時代と違って全額自己負担なので、負担が重く感じるのも当然です。
もし保険料が払えないときは、減免制度や分割納付の相談ができます。
市区町村の窓口に相談すれば、あなたの状況に合わせた対処法を一緒に考えてくれますよ。
まずは保険料の計算の仕組みを理解して、納得した上で支払っていきましょう。

なるほど!計算の仕組みがわかったら、納得できたわ!

その調子だにゃ!仕組みを理解すれば、払えないときの対処法も見えてくるにゃ!
「あと数万円稼げたのに…」「扶養を外れた方が実は手元に多く残ったのに…」
数年後にそう気づいても、過ぎた時間は戻ってきません。
今ならオンラインで、「あなたの場合、いくら稼ぐのが一番お金が貯まるか」をプロが無料で試算してくれます。
家計の健康診断だと思って、早めに一度チェックしてみてください。浮いたお金で家族旅行に行けるかもしれませんよ!
👉 【無料】何度でも相談OK!世帯年収を最大化するライフプラン相談はこちら![]()


