「配偶者特別控除って、いくらまで受けられるの?」
「私の年収でもまだセーフ?それともアウト?」
「どこまで働いたら損するの?」
年末調整の時期になると、こんな疑問を抱える方が多いですよね。

結論から言います。
配偶者特別控除は、配偶者の年収が201万円以下なら受けられます。
ただし、年収が増えるほど控除額は段階的に減っていき、201万円を超えるとゼロになります。
この記事では、配偶者特別控除がいくらまで受けられるのか、年収別の控除額早見表と税金軽減の目安額を分かりやすく解説します。
「自分の年収は大丈夫?」「いくら得するの?」という疑問に、表と数字で即答していきますね。
配偶者特別控除はいくらまで?上限は年収201万円
まず最初に、配偶者特別控除の上限をハッキリさせておきましょう。
年収201万円が上限です。
201万円を超えると控除はゼロ

配偶者の年収が201万円を超えた瞬間、配偶者特別控除は完全にゼロになります。
200万円なら控除がわずかに受けられますが、201万円を1円でも超えたら対象外です。
この「201万円」という数字が、配偶者特別控除の絶対的な上限なんですね。
ただし、201万円までずっと同じ控除額が受けられるわけではありません。
年収が増えるほど控除額は少しずつ減っていきます。
2025年改正で160万円まで満額に

2025年の改正で、配偶者特別控除に大きな変更がありました。
年収160万円まで満額の38万円控除が受けられるようになったんです。
以前は150万円までが満額でしたが、10万円引き上げられました。
つまり、年収123万円でも160万円でも、同じ38万円の控除が受けられるということ。
これは働く主婦にとって、かなり大きなメリットですよね。

えっ!201万円まで大丈夫なの!?

そうにゃ!201万円が上限にゃ。ただし年収が増えるほど控除額は減るから、その仕組みを理解するのが大事にゃ!
夫の年収が1195万円を超えると対象外

もう一つ大事な条件があります。
扶養する側(多くの場合は夫)の年収が1195万円を超えると、配偶者特別控除は使えません。
2025年の改正で、以前の1000万円以下から引き上げられました。
普通のサラリーマン家庭なら、ほとんどがこの条件をクリアしていますよ。
年収が1195万円を超える高所得者は対象外になるので、注意が必要です。
税務署から通知が来て青ざめる場合も...
配偶者特別控除の控除額早見表・いくらまで満額か一目で確認
「自分の年収だと、いくら控除が受けられるの?」
これが一番知りたいところですよね。
年収別の控除額を表で確認しましょう。
年収別控除額と税金軽減の目安

配偶者の年収別に、控除額と実際の税金軽減額をまとめました。
税金軽減額は、夫の年収が500万円前後の場合の目安です。
| 配偶者の年収 | 控除額 | 税金軽減の目安 |
|---|---|---|
| 123万円以下 | 38万円(満額) | 約7〜8万円 |
| 130万円 | 38万円(満額) | 約7〜8万円 |
| 150万円 | 38万円(満額) | 約7〜8万円 |
| 160万円 | 38万円(満額) | 約7〜8万円 |
| 170万円 | 約26万円 | 約5〜6万円 |
| 180万円 | 約16万円 | 約3〜4万円 |
| 190万円 | 約6万円 | 約1〜2万円 |
| 200万円 | 約3万円 | 約6千円〜1万円 |
| 201万円超 | 0円 | 対象外 |
この表を見ると、年収160万円までは満額の38万円控除が受けられることが分かります。
160万円を超えると段階的に減っていき、201万円でゼロになります。
ポイント整理
・年収160万円まで:満額38万円控除
・年収160万円超〜201万円:段階的に減る
・年収201万円超:控除ゼロ
夫の年収が高いと控除額が減る

配偶者特別控除の控除額は、夫の年収によっても変わります。
夫の年収が900万円以下なら満額の控除が受けられますが、年収が増えるごとに控除額は減ります。
| 夫の年収 | 妻の年収160万円の場合の控除額 |
|---|---|
| 900万円以下 | 38万円(満額) |
| 900万円超〜950万円以下 | 26万円 |
| 950万円超〜1000万円以下 | 13万円 |
| 1195万円超 | 0円(対象外) |
このように、夫の年収が高いと控除額は段階的に減っていきます。
でも、普通のサラリーマン家庭なら満額の控除が受けられますよ。
詳細な年収別控除額一覧表

より詳しく知りたい方のために、5万円刻みでの詳細な控除額一覧表を掲載します。
この表を見れば、自分の年収でいくら控除が受けられるか正確に分かります。
| 配偶者の年収 | 夫の年収900万円以下 | 夫の年収900〜950万円 | 夫の年収950〜1000万円 |
|---|---|---|---|
| 123万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 123万円超〜160万円 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 160万円超〜165万円 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| 165万円超〜170万円 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 170万円超〜175万円 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 175万円超〜180万円 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 180万円超〜185万円 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 185万円超〜190万円 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 190万円超〜195万円 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 195万円超〜201万円 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
| 201万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
この表から分かるように、配偶者の年収が160万円を超えると5万円刻みで控除額が減っていきます。
また、夫の年収が高いほど控除額も少なくなる仕組みです。
201万円を超えた瞬間、夫の年収に関わらず控除はゼロになることが一目瞭然ですね。

年収別で見ると分かりやすいわね!

そうにゃ!自分の年収を確認すれば、いくら控除が受けられるか一目瞭然にゃ!
配偶者特別控除はいくらまで?具体例でシミュレーション
「表を見てもピンとこない」という方のために、具体的なケースでシミュレーションしてみましょう。
実際の家庭でいくら得するのかを見ていきます。
ケース1・妻の年収150万円の場合

佐藤さん(仮名)の家庭を例にしてみましょう。
夫:年収500万円(会社員)
妻:年収150万円(パート)
この場合、妻の年収が150万円なので、配偶者特別控除で満額の38万円控除が受けられます。
夫の所得税率が10%なら、所得税で約3.8万円、住民税で約3.8万円、合計で約7〜8万円の減税効果があります。
年末調整で約3.8万円が還付され、翌年の住民税が月額約3,000円ずつ安くなる計算です。
ケース2・妻の年収180万円の場合

田中さん(仮名)の家庭はどうでしょうか。
夫:年収600万円(会社員)
妻:年収180万円(パート)
この場合、妻の年収が180万円なので、控除額は約16万円です。
夫の所得税率が10%なら、所得税で約1.6万円、住民税で約1.6万円、合計で約3〜4万円の減税効果があります。
160万円の満額ラインと比べると控除額は減りますが、それでも年間3〜4万円も税金が安くなるのは助かりますよね。
妻の収入が増えた分、世帯全体の収入はしっかり増えています。
ケース3・妻の年収195万円の場合

鈴木さん(仮名)の家庭はギリギリラインです。
夫:年収550万円(会社員)
妻:年収195万円(パート)
この場合、妻の年収が195万円なので、控除額は約3万円です。
夫の所得税率が10%なら、所得税で約3千円、住民税で約3千円、合計で約6千円〜1万円の減税効果があります。
控除額は少なくなりましたが、それでも201万円以内なら少しでも税金の優遇が受けられます。
もし年収が201万円を超えてしまうと、この優遇もゼロになるので要注意です。

具体例で見ると分かりやすいわね♪

そうにゃ!自分の家庭に当てはめて考えると、いくら得するか実感できるにゃ!
配偶者特別控除はいくらまで?注意すべき3つのポイント
配偶者特別控除の上限は分かりましたが、いくつか注意すべきポイントがあります。
よくある勘違いを確認しておきましょう。
注意点1・130万円の壁とは別の制度

「130万円を超えたら扶養から外れる」という話、聞いたことがありますよね。
でも、これは社会保険の扶養の話です。
配偶者特別控除とは全く別の制度なんです。
配偶者特別控除は201万円まで使えますが、社会保険の扶養は130万円未満が基準。
この2つを混同しないように注意しましょう。
注意点2・年収見込みで判断される

年末調整で配偶者特別控除を申告する際、配偶者の年収は「年収見込み」で判断されます。
12月の給与をもらう前に申告書を提出するため、その時点での見込み額で記入します。
でも、実際の年収が見込みと大きくずれた場合は要注意。
例えば、見込みでは190万円と申告したのに、年末のボーナスで201万円を超えてしまった場合、控除額が変わります。
この場合は、翌年の確定申告で修正する必要があります。
注意点3・自動では適用されない

配偶者特別控除は、必ず申告が必要です。
年末調整や確定申告で申告しないと、控除は受けられません。
「妻がパートで働いているから自動で適用される」と思っている方がいますが、それは間違いです。
毎年きちんと「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出しないと、控除額はゼロになってしまいます。
数万円の減税を受け損ねないように、必ず申告しましょう。

あっ、申告しないとダメなのね!

そうにゃ!申告しないと控除ゼロになるから、毎年忘れずに書類を出すにゃ!
配偶者特別控除の申告方法・いつどうやって申告する?
配偶者特別控除を受けるには、きちんと申告が必要です。
申告のタイミングと方法を確認しておきましょう。
年末調整で申告する

会社員の夫が配偶者特別控除を受ける場合、年末調整で申告します。
10〜11月頃に勤務先から「給与所得者の配偶者控除等申告書」という書類が配られます。
この書類に、妻の名前、生年月日、年収見込みを記入して提出すればOKです。
難しい計算は必要ありません。
妻の年収を書けば、会社が自動的に控除額を計算してくれます。
確定申告でも申告できる
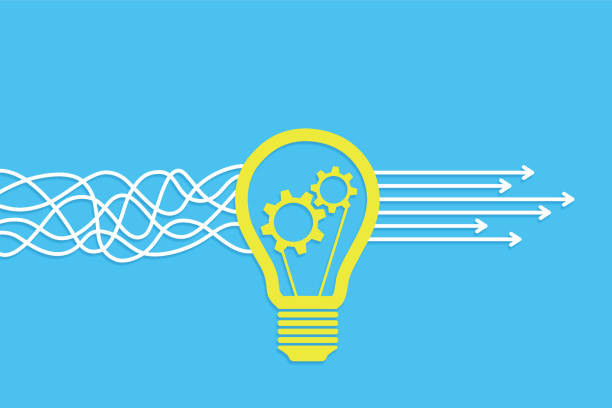
年末調整で申告を忘れた場合や、自営業の方は確定申告で申告できます。
確定申告書の「配偶者(特別)控除」の欄に、配偶者の情報を記入すればOKです。
確定申告の期間は2月16日から3月15日までですが、還付申告なら1月から受け付けてもらえます。
過去5年分まで遡って申告できるので、忘れていた方も今からでも間に合いますよ。
申告を忘れると数万円の損

配偶者特別控除の申告を忘れると、年間で数万円も税金を多く払うことになります。
年収160万円なら約7〜8万円、年収180万円でも約3〜4万円の減税効果があるのに、申告しないとその恩恵を受けられません。
毎年忘れずに申告することが、家計を守る第一歩です。
しごママで扶養内の働き方をもっと詳しく
配偶者特別控除がいくらまで受けられるか理解できても、「結局、自分はどう働くのが一番いいの?」と悩む方も多いはず。
160万円まで働くべきか、それとも201万円まで働くべきか、ライフスタイルに合った選択が大切です。

「しごママ」では、主婦の働き方に関する情報を分かりやすく発信しています。
年収の壁ごとのメリット・デメリット、社会保険の加入条件、パートと派遣の違い、履歴書の書き方まで、再就職に必要な情報を網羅的に掲載しています。
「何から始めればいいか分からない」という方は、ぜひ他の記事もチェックしてみてくださいね。

いくらまで働けるか分かってスッキリしたわ♪

その調子にゃ!しごママの他の記事で、年収別の働き方も詳しく解説してるから見てみるといいにゃ!
配偶者特別控除はいくらまで?201万円が上限。まとめ
配偶者特別控除はいくらまで受けられるのか、詳しく解説してきました。
最後にもう一度、大事なポイントをおさらいしましょう。

配偶者特別控除の上限は年収201万円です。
201万円を1円でも超えると、控除はゼロになります。
2025年の改正で、年収160万円まで満額の38万円控除が受けられるようになりました。
これは働く主婦にとって、かなり大きなメリットです。
103万円の壁を気にせず、もっと働けるようになったんですね。
ただし、申告を忘れると控除はゼロになってしまいます。
毎年きちんと「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出することが大切です。
難しく考えなくて大丈夫。
配偶者特別控除は「年収201万円まで段階的に控除が受けられる」と覚えておけばOKです。
年末調整の書類が来たら、妻の年収を記入して提出する。
たったこれだけで、家計が数万円楽になりますよ。

201万円まで大丈夫って分かって安心したわ♪ありがとう!

どういたしましてにゃ!毎年忘れずに申告して、家計を守るにゃ!
「あと数万円稼げたのに…」「扶養を外れた方が実は手元に多く残ったのに…」
数年後にそう気づいても、過ぎた時間は戻ってきません。
今ならオンラインで、「あなたの場合、いくら稼ぐのが一番お金が貯まるか」をプロが無料で試算してくれます。
家計の健康診断だと思って、早めに一度チェックしてみてください。浮いたお金で家族旅行に行けるかもしれませんよ!
👉 【無料】何度でも相談OK!世帯年収を最大化するライフプラン相談はこちら![]()


