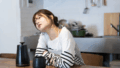「育休に入って収入が減ったけど、夫の扶養に入れるのかな?」
「配偶者控除の申請って、どこで何をすればいいの?」
「育児休業給付金をもらってるけど、控除の対象になる?」
育休中に配偶者控除を受けたいけれど、申請方法が分からず困っていませんか。

実は、育休中の配偶者控除申請は思ったより簡単なんです。
条件を確認して、夫の会社に書類を出すだけで手続きは完了します。
この記事では、育休中の配偶者控除申請方法を3ステップで徹底解説します。
いつ・どこで・誰が手続きするのか、必要書類や注意点、配偶者特別控除との違いも分かりやすくお伝えしますので、安心して申請してくださいね。
育休中の配偶者控除とは?基本を理解しよう
まずは、配偶者控除の基本を理解しましょう。
制度の仕組みを知ることで、申請方法もスムーズに理解できます。
配偶者控除は夫側の所得税が軽減される制度
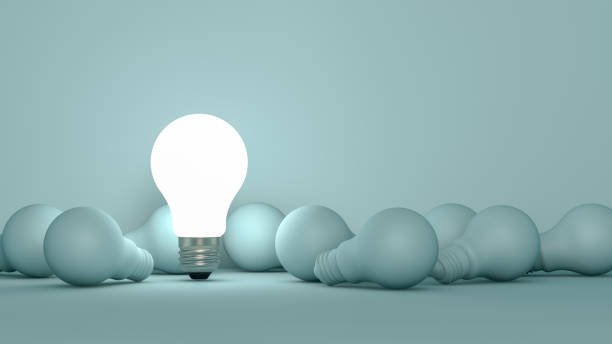
配偶者控除とは、収入が一定以下の配偶者がいる場合に、夫側の所得税や住民税が軽減される制度です。
育休中は給与がなくなるため、年間所得が基準を満たしやすくなります。
つまり、育休に入ったことで配偶者控除の対象になるケースが増えるんですね。
配偶者控除を受けることで、年間で数万円から十数万円の節税効果が期待できます。
育休中で収入が減っている時期だからこそ、この制度をしっかり活用しましょう。
育児休業給付金は収入に含まれない

ここで重要なのが、育児休業給付金や出産手当金は非課税所得なので収入に含まれないという点です。
つまり、給付金をもらっていても、その金額は配偶者控除の判定基準に影響しません。
育休中で給与がゼロなら、給付金の額に関係なく配偶者控除の対象になる可能性が高いんです。
例えば、育児休業給付金を月20万円もらっていても、それは所得として計算されません。
給与収入がゼロなら、所得もゼロとして扱われるので、配偶者控除の対象になります。

えっ!給付金をもらっていても配偶者控除を受けられるの!?

そうにゃ!給付金は非課税だから、収入としてカウントされないんだにゃ!
健康保険の扶養とは別の制度

よく混同されるのが、税金上の扶養(配偶者控除)と健康保険の扶養です。
これらはまったく別の制度なので、それぞれ個別に手続きが必要になります。
健康保険の扶養は会社の健康保険組合、配偶者控除は税務署や会社の年末調整担当が窓口です。
また、健康保険の扶養では育児休業給付金も収入に含まれる場合があるので注意が必要です。
健康保険組合によって基準が異なるため、所属する健康保険組合に確認しましょう。
税務署から通知が来て青ざめる場合も...
育休中の配偶者控除申請方法:3ステップで完了
それでは、具体的な申請方法を3ステップで解説します。
難しい手続きではないので、安心してくださいね。
ステップ1:配偶者控除の条件を確認する

まずは、あなたが配偶者控除の対象になるか確認しましょう。
配偶者控除を受けるには、年間の合計所得金額が48万円以下である必要があります。
給与収入で換算すると103万円以下です。
育休中で給与がゼロなら、ほとんどの場合この条件を満たします。
ただし、年の途中まで働いていた場合は、その期間の給与も含めて計算する必要があります。
例えば、5月まで働いて給与が50万円、6月から育休でゼロなら、年間所得は50万円です。
この場合は配偶者控除ではなく、配偶者特別控除の対象になります。
配偶者控除の対象条件
・年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入103万円以下)
・納税者と生計を一にしている
・青色申告専従者や白色申告専従者でない
・他の人の扶養親族になっていない
・夫の合計所得金額が1,000万円以下
ステップ2:必要書類を準備する

条件を満たしていることが確認できたら、必要書類を準備します。
必要なのは、「給与所得者の配偶者控除等申告書」です。
この書類は、会社から年末調整の時期に配布されます。
書類には、配偶者の氏名・生年月日・マイナンバー・年間収入見込みなどを記入します。
記入の際、育休中で給与がゼロなら、所得金額の欄は「0」と記入します。
育児休業給付金は所得に含まれないので、計算に入れないように注意しましょう。

年間の合計所得金額って、育休中ならゼロで書いていいのよね?

その通りにゃ!給与がゼロなら所得もゼロだにゃ。給付金は含めないから注意にゃ!
ステップ3:夫の会社に書類を提出する

書類の記入が終わったら、夫の会社の人事・給与担当に提出します。
提出時期は、年末調整の時期(通常11月~12月)です。
会社から指定された期限内に提出すれば、年末調整で配偶者控除が適用されます。
もし年末調整に間に合わなかった場合でも、翌年の確定申告で申請可能なので安心してください。
確定申告なら5年前まで遡って申請できるので、過去の分も諦めずに手続きしましょう。
配偶者控除と配偶者特別控除の違いを理解しよう
配偶者控除とよく似た制度に、配偶者特別控除があります。
この2つの違いを理解しておくことが大切です。
配偶者特別控除は所得48万円超133万円以下が対象

配偶者特別控除は、年間所得が48万円超133万円以下の場合に適用される制度です。
配偶者控除の対象からは外れるけれど、一定の控除を受けられる仕組みです。
年の途中まで働いていて、育休に入った場合は、この配偶者特別控除の対象になることが多いです。
例えば、6月まで働いて給与が70万円、7月から育休でゼロなら、年間所得は70万円です。
この場合、配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除は受けられます。
どちらの控除を受けるかは自動で判定される

配偶者控除と配偶者特別控除、どちらを受けるかは自動で判定されます。
あなたがする必要があるのは、「給与所得者の配偶者控除等申告書」に正しい所得額を記入するだけです。
所得額に応じて、配偶者控除か配偶者特別控除のどちらかが適用されます。
どちらの控除になっても、申請書類は同じなので安心してください。

あっ!どっちの控除になるか自分で選ばなくていいのね!

そうにゃ!所得額を正しく書けば、あとは自動で判定してくれるにゃ!
年の途中で育休に入った場合の計算例

年の途中で育休に入った場合の所得計算を、具体例で見てみましょう。
ケース1:5月末まで働いて6月から育休
1月~5月の給与:月25万円×5ヶ月=125万円
6月~12月:育休で給与ゼロ、育児休業給付金は月18万円(所得に含まれない)
年間の給与収入:125万円
年間の所得:125万円−55万円(給与所得控除)=70万円
→配偶者特別控除の対象
ケース2:1年間まるまる育休
1月~12月:育休で給与ゼロ、育児休業給付金は月18万円(所得に含まれない)
年間の給与収入:0円
年間の所得:0円
→配偶者控除の対象
このように、育休に入ったタイミングによって、適用される控除が変わります。
育休中の配偶者控除申請でよくある誤解と注意点
配偶者控除の申請には、いくつかの注意点があります。
見落としやすいポイントを確認しておきましょう。
年の途中で収入が変わった場合の対応

年の途中まで働いていて、途中から育休に入った場合は注意が必要です。
配偶者控除の判定は1年間の合計所得で行われます。
例えば、6月まで働いて給与が60万円、7月以降は育休で収入ゼロなら、年間所得は60万円です。
この場合、48万円を超えているので配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除の対象になる可能性があります。
年末調整の書類を記入する際は、その年の1月~12月までの給与総額を正しく記入しましょう。
夫の所得制限にも注意

配偶者控除を受けるには、夫側の所得にも制限があります。
夫の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除は適用されません。
給与収入で換算すると年収1,195万円を超える場合です。
該当する可能性がある場合は、事前に確認しておきましょう。
また、夫の所得が900万円を超えると、配偶者控除の控除額が段階的に減額されます。
所得900万円以下なら38万円、900万円超950万円以下なら26万円、950万円超1,000万円以下なら13万円となります。

夫の収入が高いと、控除を受けられないのね…

そうにゃ。でも年収1,195万円を超える家庭は少ないから、ほとんどの人は大丈夫にゃ!
申請書類の提出時期を逃さない

年末調整の書類提出期限は、会社によって異なります。
通常は11月中旬~12月上旬に設定されていることが多いです。
期限を過ぎてしまった場合は、翌年の確定申告で申請しましょう。
確定申告なら5年前まで遡って申請できるので、諦めずに手続きしてくださいね。
また、育休中で会社から書類が届かない場合もあります。
その場合は、夫から会社の担当者に連絡して、書類を送ってもらうように依頼しましょう。
確定申告で配偶者控除を申請する方法
年末調整に間に合わなかった場合や、過去の分を遡って申請したい場合は、確定申告で手続きします。
確定申告の方法も確認しておきましょう。
確定申告に必要な書類

確定申告で配偶者控除を申請する場合、以下の書類が必要です。
確定申告に必要な書類
・夫の源泉徴収票
・配偶者のマイナンバーカード(または通知カード+身分証明書)
・還付金を受け取る銀行口座の情報
・配偶者の収入が分かる書類(源泉徴収票など)
これらの書類を準備して、確定申告書を作成します。
確定申告書は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で簡単に作成できます。
e-Taxなら自宅から申請できる

確定申告は、e-Taxを使えば自宅からオンラインで申請できます。
マイナンバーカードとスマホがあれば、税務署に行かずに手続きが完了します。
育休中で外出が難しい時期でも、自宅で手続きできるのは便利ですね。
e-Taxでの申請方法は、国税庁のサイトに詳しく解説されているので、参考にしてください。

税務署に行かなくても申請できるのね!これなら私にもできそう♪

その調子にゃ!育休中だからこそ使える制度を賢く活用してにゃ!
5年前まで遡って申請できる

確定申告なら、5年前まで遡って配偶者控除を申請できます。
過去に育休を取っていて、配偶者控除の申請をしていなかった場合でも、諦めずに手続きしましょう。
例えば、2020年に育休を取っていて、配偶者控除を申請していなかった場合、2025年3月15日までなら遡って申請できます。
還付金が受け取れる可能性があるので、該当する方はぜひ確認してみてください。
育休中 配偶者控除 申請方法:安心して手続きを完了させよう
育休中の配偶者控除申請は、3ステップで簡単に完了します。
条件を確認して、必要書類を準備し、夫の会社に提出するだけです。

育児休業給付金は非課税所得なので、給付金をもらっていても配偶者控除の対象になります。
年末調整の時期に「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出すれば、夫の所得税や住民税が軽減されます。
申請書類の提出期限は会社によって異なるので、早めに確認しておきましょう。
もし年末調整に間に合わなくても、翌年の確定申告で申請できるので安心してください。
配偶者控除を受けることで、家計の負担が軽くなります。
育休中だからこそ使える制度をしっかり活用して、賢く節税してくださいね。
年間で数万円から十数万円の節税効果が期待できるので、忘れずに申請しましょう。
育休中のお金の手続きで困ったことがあれば、また「しごママ」をチェックしてくださいね。

思ったより簡単だったわ!早速夫に書類を書いてもらうように伝えなきゃ♪

その調子にゃ!育休中のお金の手続きで困ったら、また「しごママ」をチェックしてにゃ!
「あと数万円稼げたのに…」「扶養を外れた方が実は手元に多く残ったのに…」
数年後にそう気づいても、過ぎた時間は戻ってきません。
今ならオンラインで、「あなたの場合、いくら稼ぐのが一番お金が貯まるか」をプロが無料で試算してくれます。
家計の健康診断だと思って、早めに一度チェックしてみてください。浮いたお金で家族旅行に行けるかもしれませんよ!
👉 【無料】何度でも相談OK!世帯年収を最大化するライフプラン相談はこちら![]()