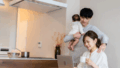「育休に入って数カ月。収入が減って、社会保険料の通知にびっくりした…」
「夫の扶養に入れるって聞いたけど、どうやって手続きすればいいの?」
「そもそも私、扶養に入れるの?」
育休中のお金の不安、よくわかります。

実は、育休中でも条件を満たせば夫の扶養に入ることができます。
手続きをすれば、夫の所得税や住民税が軽減されて、家計の負担が減るんです。
でも、「手続きが面倒そう」「書類がよくわからない」「損したくない」と感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、育休中に夫の扶養に入る条件、具体的な手続きの流れ、注意すべきポイントまで徹底解説します。
「損したくない」「手続きで失敗したくない」という方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
育休中に夫の扶養に入れる条件とは
まずは、育休中に夫の扶養に入れる条件を確認しましょう。
「扶養」には税法上の扶養と健康保険の扶養がありますが、ここでは税法上の扶養について解説します。
税法上の扶養に入れば、夫の所得税や住民税が軽減される配偶者控除または配偶者特別控除を受けられます。
税法上の扶養に入れる年収の基準

育休中に夫の扶養に入るには、妻の年収が201万6千円以下(所得133万円以下)である必要があります。
この基準を満たせば、配偶者控除または配偶者特別控除を受けられます。
育休中は給与収入がほとんどない方が多いので、多くの場合この基準をクリアできるんです。
具体的には、年収150万円以下なら配偶者特別控除を満額で受けられます。
年収が150万円を超えても201万6千円以下なら、段階的に控除が受けられる仕組みです。
配偶者控除・配偶者特別控除の年収基準
・年収103万円以下:配偶者控除(最大38万円)
・年収150万円以下:配偶者特別控除(満額38万円)
・年収201万6千円以下:配偶者特別控除(段階的に減額)
・年収が少ないほど控除額が大きくなる
育休中で給与収入がゼロまたはごく少額の場合、ほとんどの方が最大控除を受けられます。

えっ?201万円以下なら扶養に入れるの?

その通りにゃ!育休中は給料がないから、ほとんどの人が基準内に収まるにゃ!
育児休業給付金は収入に含まれない

ここで重要なのが、育児休業給付金は収入に含まれないという点です。
育児休業給付金は非課税の手当なので、年収の計算には入りません。
つまり、育児休業給付金を毎月受け取っていても、給与収入がなければ扶養に入れるんです。
例えば、育休中に毎月15万円の育児休業給付金を受け取っていたとしても、給与収入がゼロであれば年収はゼロとして扱われます。
これは大きなメリットですよね。
これらはすべて非課税なので、年収の計算には影響しません。
安心して扶養の手続きができますね。
ただし、給与収入がある月があれば、その分は年収に含まれるので注意が必要です。
健康保険の扶養とは別物である点に注意
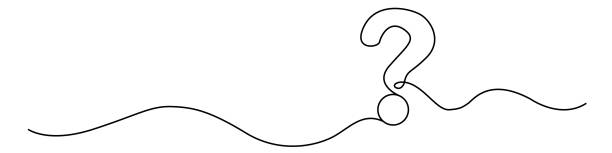
混同しやすいのが、税法上の扶養と健康保険の扶養は別物だということです。
税法上の扶養は年収201万6千円以下が基準ですが、健康保険の扶養は年収見込み130万円未満が基準になります。
また、健康保険の扶養の場合、育児休業給付金も収入に含まれる場合があるので注意が必要です。
この2つの扶養制度は全く別の制度なので、それぞれ個別に判断されます。
税法上の扶養に入れても、健康保険の扶養には入れない場合もあるんです。

えぇっ!? 扶養って2種類あるの!?

そうなんだにゃ!税金の扶養と健康保険の扶養は全く別の制度だから注意するにゃ!
税務署から通知が来て青ざめる場合も...
育休中に夫の扶養に入る手続きの流れ
条件を確認したら、次は具体的な手続きの流れを見ていきましょう。
手続きは年末調整または確定申告で行います。
どちらの方法でも扶養控除を受けられますが、タイミングや必要書類が少し異なります。
年末調整での手続き方法

育休中に夫の扶養に入る手続きは、主に夫の勤務先での年末調整で行います。
年末調整は毎年10月中旬から11月上旬にかけて行われることが多いです。
夫の勤務先から「扶養控除等申告書」や「給与所得者の配偶者控除等申告書」が配布されるので、必要事項を記入して提出します。
年末調整での手続きは、確定申告に比べて簡単で手間がかかりません。
夫の勤務先が書類のチェックや税務署への提出まで代行してくれるので、書類の記入と提出だけで完了します。
年末調整での手続きの流れ
1. 夫の勤務先から申告書を受け取る(10月中旬~11月上旬)
2. 申告書に配偶者の氏名、住所、マイナンバー、所得見込みを記入
3. 妻の勤務先から「給与収入の見込み証明書」を取得
4. 記入済みの申告書と証明書を夫の勤務先に提出(11月中旬まで)
5. 勤務先が年末調整を実施(12月の給与で還付または調整)
この流れに沿って手続きすれば、夫は配偶者控除または配偶者特別控除を受けられます。
年末調整が終われば、翌年1月の給与で還付金が戻ってくることもあるんです。
還付金の額は、夫の年収や妻の年収によって変わりますが、数万円から十数万円になることもあります。
確定申告での手続き方法

年末調整の時期に間に合わなかった場合でも、確定申告で扶養の手続きができます。
確定申告は毎年2月16日から3月15日までの期間に行います。
過去5年以内であれば、遡って控除の申告や還付申請ができるので、「年末調整で申告し忘れた」という方も安心してください。
確定申告は少し手間がかかりますが、自分で計算して申告するので、制度への理解が深まるというメリットもあります。
確定申告は税務署で行いますが、最近はe-Taxを使えば自宅からオンラインで申告できます。
国税庁のホームページから確定申告書等作成コーナーにアクセスして、画面の指示に従って入力するだけです。
マイナンバーカードとスマートフォンがあれば、パソコンがなくてもスマホだけで申告できます。

忘れてても大丈夫なのね!安心したわ♪

その調子にゃ!確定申告なら過去5年分まで遡れるから、気づいたときに申告すればいいにゃ!
必要書類と提出先を整理しよう

育休中に夫の扶養に入る手続きで必要な書類を整理しておきましょう。
年末調整の場合と確定申告の場合で、少し異なります。
事前に必要書類を準備しておけば、スムーズに手続きが進みます。
年末調整で必要な書類
・扶養控除等申告書(夫の勤務先から入手)
・給与所得者の配偶者控除等申告書(夫の勤務先から入手)
・給与収入の見込み証明書(妻の勤務先で発行)
・本人確認書類のコピー(勤務先による)
・マイナンバーカードまたは通知カードのコピー
確定申告で必要な書類
・給与所得の源泉徴収票(夫と妻の両方)
・給与収入の見込み証明書または実際の給与明細
・本人確認書類(マイナンバーカードなど)
・還付先の口座情報
・印鑑(認印でOK、e-Taxなら不要)
提出先は、年末調整なら夫の勤務先の総務部や人事部、確定申告なら税務署またはe-Taxです。
書類に不備があると再提出になるので、事前にしっかり確認しておきましょう。
特に、マイナンバーの記入漏れや配偶者の所得金額の計算ミスが多いので注意してください。
育休中の扶養手続きで注意すべきポイント
育休中に夫の扶養に入る手続きで、注意すべきポイントがいくつかあります。
知らないと損してしまうこともあるので、しっかり確認しておきましょう。
特に、復帰時期や給付金の扱いについては、多くの方が迷いやすいポイントです。
出産手当金がある場合の注意点

出産手当金は、育児休業給付金と同じく非課税の手当です。
税法上の扶養を考える際には、出産手当金は収入に含まれません。
ただし、健康保険の扶養の場合は出産手当金も収入としてカウントされることがあります。
税法上の扶養と健康保険の扶養は別物なので、混同しないように注意してください。
出産手当金は産休中に支給される手当で、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。
産休後に育休に入る場合、出産手当金と育児休業給付金の両方を受け取ることになりますが、どちらも非課税なので税法上の扶養判定には影響しません。
復帰予定がある場合の判断基準

育休後に職場復帰する予定がある場合、その年の年収見込みで判断します。
例えば、12月に職場復帰する予定なら、復帰後の給与も含めて年収を計算しなければなりません。
復帰後の給与を含めると年収が201万6千円を超えてしまう場合は、扶養に入れないので注意が必要です。
特に、年末近くに復帰する場合は、復帰後の給与が年収に影響するかどうかを慎重に確認しましょう。
復帰時期によっては、翌年1月まで復帰を延ばした方が税制上有利になる場合もあります。
年収の見込みが微妙なラインの場合は、夫の勤務先や税理士に相談してみましょう。
復帰時期を調整できる場合は、税制面も考慮して検討するのがおすすめです。

うぅ…復帰の予定があると計算が複雑になるのね…

そうなんだにゃ。でも安心して。迷ったら夫の勤務先に相談すれば教えてもらえるにゃ!
迷ったら夫の勤務先に確認するのが確実

育休中の扶養手続きで迷ったら、まずは夫の勤務先に確認するのが確実です。
勤務先の総務部や人事部は、扶養の手続きに慣れているので、的確なアドバイスをくれます。
「こういう場合はどうすればいいですか?」と聞けば、必要な書類や手続きの流れを教えてもらえるんです。
また、勤務先によっては独自の扶養手当制度がある場合もあります。
税法上の扶養とは別に、会社独自の扶養手当が支給されることもあるので、併せて確認しておきましょう。
一人で悩んで手続きを間違えるよりも、専門家に聞いてしまう方が確実で安心です。
遠慮せずにどんどん質問しましょう。
育休中に夫の扶養に入る手続き。損しない方法を徹底解説:まとめ
育休中に夫の扶養に入る手続きは、年末調整または確定申告で行います。
妻の年収が201万6千円以下なら扶養に入れて、夫の所得税や住民税が軽減されます。

育児休業給付金や出産手当金は非課税なので、収入に含まれません。
給与収入がほとんどない育休中なら、多くの方が扶養に入れます。
手続きは一見複雑に見えますが、必要書類を揃えて夫の勤務先に提出すれば大丈夫です。
分からないことがあれば、遠慮せずに勤務先に質問しましょう。
「損したくない」「手続きで失敗したくない」という気持ち、よくわかります。
でも安心してください。
正しい情報をもとに手続きすれば、必ず節税効果が得られます。
配偶者控除または配偶者特別控除を受けることで、年間で数万円から十数万円の税金が軽減されることもあります。
この金額は家計にとって大きな助けになりますよね。
育休中は収入が減って不安になることも多いですが、使える制度をしっかり活用すれば家計の負担を減らせます。
一人で悩まず、専門家の力を借りながら、安心して子育てに専念できる環境を整えていきましょう。
扶養の手続きは毎年行う必要があるので、一度やり方を覚えてしまえば来年以降もスムーズに手続きできます。

なんだか自信が出てきたわ!私にもできそう♪

その調子にゃ!一歩ずつでいいから、前に進んでいこうにゃ!
「あと数万円稼げたのに…」「扶養を外れた方が実は手元に多く残ったのに…」
数年後にそう気づいても、過ぎた時間は戻ってきません。
今ならオンラインで、「あなたの場合、いくら稼ぐのが一番お金が貯まるか」をプロが無料で試算してくれます。
家計の健康診断だと思って、早めに一度チェックしてみてください。浮いたお金で家族旅行に行けるかもしれませんよ!
👉 【無料】何度でも相談OK!世帯年収を最大化するライフプラン相談はこちら![]()