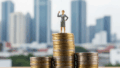「育休を取ってそのまま辞めるなんて、ずるいって思われるかな…」
「職場に迷惑をかけるのは分かってるけど、子育てと両立できる自信がない」
「復帰を期待されてたのに退職するなんて、裏切り者みたいで罪悪感がある」
育休後の退職について、周囲の目や言葉が気になって不安を感じていませんか。

「ずるい」という言葉は、誰に向けられてもつらいものです。
でも、育休後の退職は法的に何も問題なく、あなたの正当な権利なんです。
この記事では、育休後の退職がずるいと思われる理由と、円満に退職するための具体的な方法を解説します。
職場との関係を壊さず、罪悪感なく次のステップへ進むためのヒントをお伝えしますので、最後まで読んでくださいね。
育休退職はずるいと思われる3つの理由
まずは、なぜ育休後の退職がずるいと思われるのかを理解しましょう。
理由が分かれば、対策も見えてきます。
育休は復職前提で認められる制度だから

育休後の退職がずるいと思われる最大の理由は、育休が復職を前提とした制度だからです。
育児休業は、育児と仕事を両立したい人を支えるための制度として設計されています。
復帰する意思がないまま制度を利用したと受け取られると、「育児休業給付金だけもらって辞めた」と誤解されることがあります。
実際には、育休中に状況が変わって退職を決める人も多いのですが、周囲からは「最初から辞めるつもりだったのでは」と疑われがちです。
厚生労働省のデータによると、育休後に退職する人は一定数存在しており、2023年の調査では女性の6.8%が育休終了後に退職しています。

最初は復帰するつもりだったのに、状況が変わっちゃうこともあるのよね…

そうにゃ。育休中に気持ちが変わることは誰にでもあるにゃ。でも職場には理解されにくいんだにゃ。
職場に業務のしわ寄せが残るから

育休後の退職がずるいと思われるもうひとつの理由は、職場に業務のしわ寄せが残るからです。
育休中は同僚が業務をカバーしており、復職後にまた担当してもらえると期待しています。
しかし退職となると、一時的にカバーしていた業務の負担がそのまま残ってしまうんです。
また、新しい人材を採用して育成するまでには時間もコストもかかります。
業務の引き継ぎが不十分だと、クレームにつながったり、残された同僚の負担が増えて時間外労働が発生したりすることもあります。
復職を前提に人員配置していたから

多くの会社では、育休中の社員を「一時的に休んでいる人」としてカウントしています。
そのため、新しい人材を採用せず、復職を前提に人員配置を考えているケースが多いんです。
退職となると急遽人材を確保する必要があり、会社側の負担も大きくなります。
このような事情から、「復職すると思っていたのに裏切られた」という感情が生まれやすいのです。
求人掲載や紹介料などの採用費用、新人研修や教育のための時間、業務習得までの生産性の低下など、企業側のコストは決して小さくありません。
今の職場で、損し続けているかもしれません。
育休後に退職したくなる理由は誰にでもある
では、なぜ育休後に退職したくなるのかを考えてみましょう。
実は、多くのママが同じ悩みを抱えています。
仕事と子育ての両立が想像以上に大変

育休後に退職したくなる最大の理由は、仕事と子育ての両立が想像以上に大変だからです。
保育園の送り迎え、子どもの急な発熱、家事との両立など、想定外の負担が続きます。
睡眠時間も確保できず、心身ともに疲弊してしまうケースも少なくありません。
特に保育園に入園した直後から1年間は風邪をもらいやすく、急なお迎え要請は日常茶飯事です。
仕事を休まなければならない日が続けば業務がたまり、仕事への影響も増えます。
仕事と子育て両立の大変さ
・保育園の送り迎えで時間に余裕がない
・子どもの急な発熱で仕事を休む日が増える
・家事をする時間がなく部屋が散らかる
・睡眠時間が削られて体調を崩しやすい
・外食が増えて食費がかさむ
・朝の準備が間に合わずストレス
職場の理解が得られず居心地が悪い

育休後の退職を考える理由に、職場の理解不足もあります。
時短勤務への嫌味、急な休みへの白い目、子育て支援制度の不備など、職場環境が育児との両立に適していない場合があります。
育児中の社員が少なく相談相手がいない職場では、孤立感を抱きやすくなります。
復帰後に居場所がないと感じてしまうと、退職を考えるのは自然な流れです。
復帰前と同じ仕事量で帰れなかったり、逆に復帰後の仕事量が極端に少なくてやりがいを感じられなかったりするケースもあります。

職場で理解してもらえないと、本当につらいわよね…

そうにゃ…。制度はあっても、実際の職場で使いづらい雰囲気があるのは問題にゃ。
子育てに専念したい気持ちが強くなる

育休中に子どもと過ごす時間が増えると、子育てに専念したい気持ちが強くなることがあります。
発達の変化が早い乳幼児期の成長を、そばで見守りたいと思うのは自然な感情です。
保育園に預けることへの迷いや、仕事との両立による負担感から、家庭を優先したいと考える人も多いでしょう。
子どもと過ごす時間を優先したいと感じたとき、退職が現実的な選択肢に見えるのは当然のことです。
特に一人目の子どもの場合、初めての経験ばかりで不安も大きく、そばにいてあげたいという思いが強くなります。
育休退職でずるいと思われないための伝え方
育休後の退職を決めたら、伝え方が重要になります。
円満に退職するためのコツを押さえましょう。
前向きな退職理由を伝える

育休後に退職してずるいと思われないためには、前向きな退職理由を伝えることが大切です。
個人的な不満や感情ではなく、将来を見据えた意思を示しましょう。
退職の理由が明確で前向きであれば、職場の人も応援しやすくなります。
退職後に何をしたいか、どう成長したいかなど、前向きな意思が伝わる言い方にするのが大切です。
上司に早めに相談する
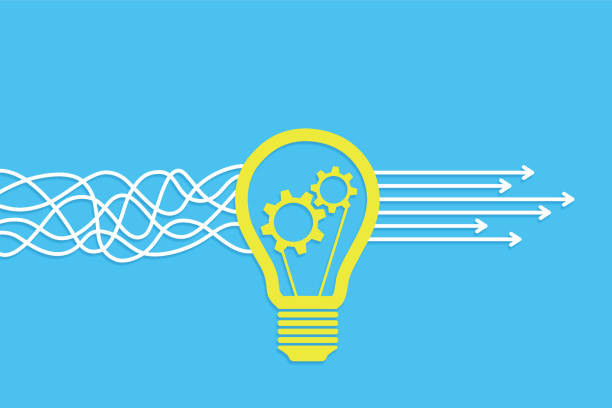
退職の意思は、直属の上司に早めに相談しましょう。
同僚に先に話してしまい、本人以外の口から上司の耳に入ると信頼を損ねます。
まず上司に相談し、今後の動き方や報告の仕方について指示を仰ぐのが正しい手順です。
早めに相談することで、引き継ぎや人員配置の調整にも余裕が生まれます。
上司への報告や相談が後回しになると、信頼を損ねるおそれがあるため、退職を決めたらすぐに行動しましょう。

上司に伝えるのって、すごく勇気がいるわよね…

そうにゃ。でも早めに伝えることで、職場への配慮を示せるにゃ。誠実さが大事にゃ!
感謝の気持ちを忘れずに伝える

育休後に退職する場合、同僚や上司への感謝の気持ちを忘れずに伝えることが大切です。
育休中に業務をカバーしてくれた同僚、サポートしてくれた上司に対して、心からの感謝を伝えましょう。
感謝の気持ちが伝われば、退職後も良好な関係を保ちやすくなります。
特に、育休中にサポートを受けた相手には、心を込めた言葉があると印象が変わります。
育休後の退職で知っておくべきデメリット
育休後の退職を決める前に、デメリットも理解しておきましょう。
後悔しないための情報をお伝えします。
キャリアにブランクが生まれる

育休後に退職すると、キャリアにブランクが生まれるデメリットがあります。
再就職を考えたときに、応募先の企業から「即戦力で活躍できるか」「仕事の感覚が鈍っていないか」「すぐに辞めてしまわないか」といった不安を持たれる可能性があります。
特に業界の変化が早い職種では、知識やスキルのアップデートが遅れやすくなるのも現実です。
将来のキャリアを見据えたうえで、慎重に判断しましょう。
業界によっては、就業条件が限られる場合や、希望する職種に就きにくくなることもあります。
経済的に不安定になる可能性

退職すると毎月の収入がなくなるため、経済的に不安定になる可能性があります。
住宅ローンや教育費など、大きな固定出費がある家庭では生活にゆとりがなくなる場合も。
配偶者の収入だけで生活を支えるには、事前の資金計画が必要です。
退職を決める前に、家計やライフプランを見直し、将来の収支をシミュレーションしましょう。
子育てには想定外の支出も多く、急な出費に対応できないことも考えられます。
保育園を退園する必要がある

育休後に退職すると、保育園を退園する必要があります。
保育園に通うには保護者の就労が条件になっている場合が多いからです。
子どもの預け先がなくなると、在宅ワークや再就職の選択肢も狭まります。
ただし、子どもが4歳になる年には幼稚園に通わせる選択肢もあるので、長期的な視点で考えましょう。
近年では、預かり保育や給食を提供する幼稚園も増えてきているため、働くママも無理なく通える環境が整いつつあります。
育休後に円満退職するための具体的な手順
育休後に退職する場合、具体的な手順を踏むことが大切です。
円満に退職するためのステップを確認しましょう。
就業規則を確認する

まずは、会社の就業規則を確認しましょう。
退職の申し出期限、退職届の提出期限、フォーマットの有無などを確認します。
育休中の退職に特別なルールを設けている会社もあるので、トラブルを避けるためにも事前に確認が必要です。
例えば、退職届の提出期限が1か月前までと明記されている場合、その期限を過ぎるとトラブルに発展する場合があります。
就業規則で確認すべき項目
・退職の申し出期限(1か月前、2か月前など)
・退職届の提出期限
・退職届のフォーマット
・退職金の有無と支給条件
・育休中の退職に関する特別ルール
引き継ぎを漏れなく行う

担当していた業務を漏れなく引き継ぐことが、円満退職の鍵です。
業務内容や手順、担当者しか分からない細かなポイントまで、できるだけ明確に伝えましょう。
ドキュメントにまとめておくと、引き継がれた人が後で確認しやすくなります。
引き継ぐ相手に直接説明すると、認識のずれが減ります。
社会保険や失業保険の手続きを忘れずに

退職後は、社会保険や失業保険の手続きが必要になります。
健康保険の切り替え、年金の種別変更、失業保険の受給申請など、必要な手続きを確実に進めましょう。
手続きをしないまま放置すると保障を受けられない場合があるため、早めに行動してください。
会社を退職すると、これまで勤務先が対応していた保険や年金の扱いが変わります。
育休退職はずるい?自分らしい選択をするために
育休後の退職は、法的には何も問題なく、あなたの正当な権利です。
ずるいと思われる理由は、制度と現場のギャップや職場の負担感にあります。

でも、仕事と子育ての両立が想像以上に大変だったり、職場の理解が得られなかったり、子育てに専念したい気持ちが強くなったりするのは、誰にでもあることです。
大切なのは、伝え方と誠実な対応。
退職は人生の大きなターニングポイントです。
キャリアのブランクや経済的な不安、保育園の退園など、デメリットもありますが、それでも家庭を優先したいという選択は尊重されるべきものです。
罪悪感を抱える必要はありません。
あなたの人生、あなたの選択です。
職場との関係を大切にしながら、自分らしい働き方を選んでくださいね。
育休後に退職したからといって、人生が終わりではありません。
自分の正直な気持ちに向き合い、将来を見越した最適な選択をしてください。

罪悪感を感じなくていいって分かって、ちょっと楽になったわ♪

その調子にゃ!自分らしい選択をして、前に進んでいくにゃ!
もし明日、シフトを減らされたり、理不尽なことを言われたりしたら…。
そんな時のために、「今の職場より好条件で、いつでも移れる場所」を持っておくことは、最強の保険になります。
転職を強要されることはありません。
まずは登録して、「自分の近所にどんな好条件の仕事が隠れているか」を3分でスマホからチェックするだけでOKです。
良い求人は早い者勝ちなので、見る権利だけは確保しておきましょう。
👉 【無料登録】一般非公開の「好条件・社保完備」求人を見てみる|アデコ![]()