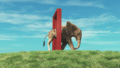「結婚したら扶養に入るべき?」
「共働きでも扶養って関係あるの?」
「正社員同士なら扶養はどうすればいい?」
結婚を控えた方、新婚さん、こんな疑問を抱えていませんか?

実は、共働きでも扶養について考えることはとても重要なんです!
結婚後の扶養の選択次第で、年間数十万円もの差が出ることもあります。
この記事では、結婚後の扶養について共働き夫婦がどう判断すべきか徹底解説!
税制上の扶養と社会保険上の扶養の違い、正社員同士の場合の考え方、具体的な手続き方法まで分かりやすくお伝えします。
結婚したら扶養に入るべき?共働きでも関係あるの?
結婚すると「扶養に入る」という言葉をよく聞きますよね。
でも、共働きの場合は扶養って関係あるのでしょうか?
扶養には2種類ある。税金と社会保険

まず知っておきたいのが、扶養には2種類あるということ。
この2つを混同している人がとても多いので、しっかり理解しておきましょう。
| 扶養の種類 | 管轄 | 主なメリット |
|---|---|---|
| 税制上の扶養 | 税務署・国税庁 | 配偶者控除・配偶者特別控除で所得税・住民税が安くなる |
| 社会保険上の扶養 | 健康保険組合・年金事務所 | 健康保険料・年金保険料を払わなくていい |
それぞれ条件も管轄も全く違うので、別々に考える必要があります。
税制上は扶養に入っているけど、社会保険上は扶養から外れているというケースもよくあるんです。
共働きなら扶養は関係ない?それは大きな誤解

「共働きだから扶養なんて関係ないでしょ」と思っていませんか?
実は、それは大きな誤解なんです!
共働きでも、収入のバランスや働き方によって扶養を活用できることは多いんです。
特に年収150万円以下で働いている方は、扶養に入ることで家計全体のメリットが大きくなります。
結婚したらまず確認すべき3つのこと

結婚したら、まずは以下の3つを確認してください。
結婚後に確認すべき3つのポイント
①夫婦それぞれの年収
手取りではなく、額面の年収を確認しましょう。税制上の扶養判断に必要です。
②それぞれの雇用形態と勤務時間
正社員、パート、派遣、フリーランスなど。社会保険の扶養判断に必要です。
③勤務先の扶養手当や福利厚生
会社によっては配偶者手当や家族手当があります。どちらの会社の手当が手厚いかチェック!
この3つが分かれば、どちらの扶養に入るのが得か判断しやすくなります。

えっ!?共働きでも扶養って関係あるの!?知らなかった!

大いに関係あるにゃ!扶養を賢く使えば、年間で数十万円も違うことがあるにゃ!
税務署から通知が来て青ざめる場合も...
結婚後の扶養。税制上と社会保険上の違いを理解しよう
ここからは、税制上の扶養と社会保険上の扶養について、それぞれ詳しく見ていきます。
この違いを理解することが、賢い選択の第一歩です!
税制上の扶養は年収123万円以下が目安

税制上の扶養とは、配偶者控除や配偶者特別控除のことを指します。
2025年から基準が変わり、年収123万円以下なら配偶者控除の対象になります。
| 配偶者の年収 | 控除の種類 | 控除額(配偶者側) |
|---|---|---|
| 123万円以下 | 配偶者控除 | 38万円(所得税) |
| 123万円超〜201万円 | 配偶者特別控除 | 1万円〜38万円(段階的) |
| 201万円超 | 控除なし | 0円 |
例えば、夫の年収が500万円で妻が年収100万円の場合。
妻を夫の扶養に入れることで、夫の所得税が約7万円、住民税が約3.3万円安くなります。
合計で年間約10万円の節税効果があるわけです。
社会保険上の扶養は収入が多い方に入る

社会保険上の扶養は、税制上の扶養とは全く別の制度です。
こちらは健康保険と年金に関する扶養で、2021年からルールが変わっています。
社会保険上の扶養の基準(2021年以降)
扶養に入れる条件
・年収130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)
・週の勤務時間が20時間未満
・扶養する側の年収の2分の1未満
どちらの扶養に入るか
・原則として「今後1年間の収入見込みが多い方」の扶養に入る
・夫婦で自由に選べない(収入で自動的に決まる)
社会保険の扶養に入れば、自分で保険料を払わなくていいのが最大のメリット。
健康保険料と厚生年金保険料で、年間20万円〜30万円の負担が0円になります!
ただし、国民年金の3号被保険者になるため、将来もらえる年金は基礎年金のみになります。
夫婦の収入が同じくらいならどうする?
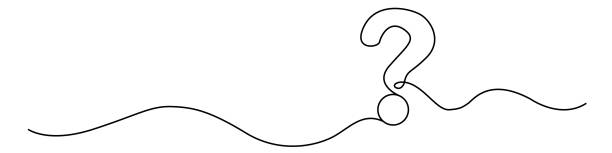
共働きで夫婦の収入が同じくらいの場合、迷いますよね。
そんなときの判断基準を見てみましょう。
また、会社の扶養手当も忘れずにチェック!
月額5,000円〜20,000円の配偶者手当がある会社も多いので、手当が手厚い方の扶養に入れるのが得策です。

なるほど!税制は選べるけど、社会保険は収入で自動的に決まるのね!

その通りにゃ!2つは別の制度だから、それぞれ別に判断する必要があるにゃ!
共働きで正社員同士の結婚。扶養はどうすべき?
正社員同士で結婚した場合、扶養について悩む方は多いです。
ここからは、正社員の共働き夫婦に焦点を当てて解説していきます!
正社員同士なら基本的に扶養には入らない

正社員同士の結婚なら、基本的にはお互いに扶養には入りません。
なぜなら、正社員の年収は通常130万円を超えているからです。
正社員同士の場合
社会保険
・それぞれ自分の会社の社会保険に加入
・健康保険料・厚生年金保険料をそれぞれ支払う
・将来の年金は2人とも厚生年金を受け取れる
税制
・年収が高い場合は配偶者控除の対象外
・お互いに扶養控除を受けない
・それぞれ自分の収入で税金を払う
正社員同士だと扶養のメリットは受けられませんが、その分2人とも厚生年金に加入できるのが大きなメリット。
将来、夫婦で月額30万円〜40万円の年金を受け取れる計算になります。
時短勤務や産休育休なら扶養に入れる可能性大

ただし、正社員でも時短勤務や産休・育休中なら話は別です!
一時的に収入が減るタイミングで、扶養に入ることができます。
特に育休中は、給付金があっても年収123万円以下になりやすいです。
このタイミングで配偶者の扶養に入れば、年間10万円以上の節税になることも!
子どもはどちらの扶養に入れるべき?

正社員同士の共働き夫婦で子どもが生まれたら、どちらの扶養に入れるかも重要な判断ポイントです。
子どもの扶養の判断基準
社会保険上の扶養
・原則として年収が高い方の扶養に入れる
・夫婦の年収差が1割以内なら、主に家計を担う方でOK
・健康保険組合によって基準が異なるので要確認
税制上の扶養
・どちらの扶養に入れても自由に選べる
・所得が高い方(税率が高い方)に入れるのがお得
・扶養控除で所得税・住民税が年間約12万円安くなる
また、会社の家族手当も忘れずチェック!
子ども1人につき月額5,000円〜10,000円の手当がある会社も多いです。
年収・税率・手当の3つを総合的に判断して、最もメリットが大きい方の扶養に入れましょう。

育休中は扶養に入れるのね!これは知らなかったわ♪

育休中は収入が減るから扶養のチャンスにゃ!年末調整で忘れずに申告するにゃ!
結婚後の扶養手続き。いつ、何をすればいい?
扶養に入ると決めたら、具体的な手続きが必要です。
いつ、何をすればいいのか見ていきましょう!
結婚後すぐにやるべき扶養の手続き

結婚後、扶養に入る場合はできるだけ早く手続きを始めましょう。
結婚後の扶養手続きの流れ
①婚姻届提出後すぐ(2週間以内)
・社会保険の扶養手続き
・扶養する側の会社に「健康保険被扶養者(異動)届」を提出
・必要書類:戸籍謄本、マイナンバーカード、収入証明書
②年末調整の時期(11月〜12月)
・税制上の扶養手続き
・「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出
・配偶者の所得見込み額を記入
③年度途中で結婚した場合
・年末調整で遡って申告できる
・結婚日から年末までの期間で控除適用
社会保険の扶養手続きは、結婚後すぐに行うのがポイント。
遅れると、その間の医療費が全額自己負担になったり、保険料の計算が複雑になったりします。
必要書類と提出先をチェック

扶養の手続きに必要な書類を整理しておきましょう。
| 手続きの種類 | 必要書類 | 提出先 |
|---|---|---|
| 社会保険の扶養 | ・健康保険被扶養者(異動)届 ・戸籍謄本(発行3ヶ月以内) ・マイナンバーカード ・収入証明書(源泉徴収票等) | 扶養する側の会社の人事部 |
| 税制上の扶養 | ・給与所得者の扶養控除等申告書 ・配偶者の収入証明書 ・マイナンバー | 扶養する側の会社(年末調整) |
| 会社の扶養手当 | ・扶養手当申請書 ・戸籍謄本 ・住民票 | 扶養する側の会社の人事部 |
会社によって必要書類が異なる場合があるので、事前に人事部に確認しておくと安心です。
扶養から外れるタイミングも把握しておこう
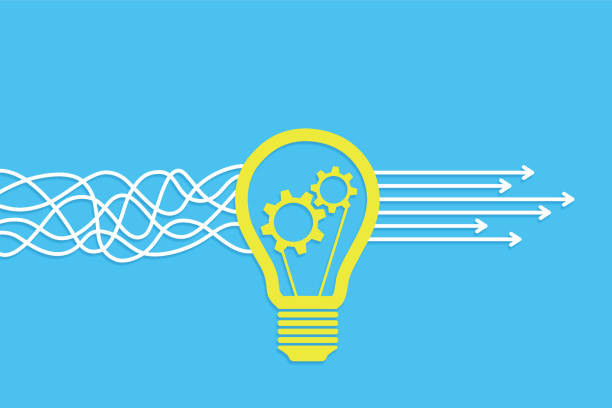
扶養に入った後も、いつ外れるべきかを知っておくことは大切です。
扶養から外れるタイミング
社会保険上の扶養
・年収が130万円を超える見込みになったとき
・週20時間以上働くようになったとき
・就職して自分の社会保険に加入したとき
→ 14日以内に届け出が必要
税制上の扶養
・年収が201万円を超えたとき
→ 年末調整で申告すればOK(年の途中で外れる必要なし)
特に育休明けで復職するときは要注意!
復職と同時に扶養から外れる手続きをしないと、二重加入になったり、保険証が使えなくなったりします。

うぅ…手続きが多くて大変そう…

大丈夫にゃ!会社の人事部が丁寧に教えてくれるから、分からないことは遠慮なく聞くにゃ!
結婚後の扶養と共働き。賢い選択でお得に暮らそう。まとめ
結婚後の扶養について、共働き夫婦がどう判断すべきか詳しく見てきました。
税制上の扶養と社会保険上の扶養は別物であり、それぞれの条件やメリットを理解することが大切です。

結婚は人生の大きな節目です。
扶養制度を賢く活用すれば、年間で10万円〜30万円もの節約になることもあります。
夫婦の収入、働き方、将来のライフプランを総合的に考えて、最適な選択をしてください。
迷ったときは、会社の人事部や税理士、ファイナンシャルプランナーに相談するのもおすすめです。
専門家の力も借りながら、お二人にとってベストな働き方・暮らし方を見つけていきましょう!

結婚後の扶養、ちゃんと理解できたわ!夫とも相談してみる♪

その調子にゃ!夫婦でしっかり話し合って、お二人にとってベストな選択をするにゃ!
「あと数万円稼げたのに…」「扶養を外れた方が実は手元に多く残ったのに…」
数年後にそう気づいても、過ぎた時間は戻ってきません。
今ならオンラインで、「あなたの場合、いくら稼ぐのが一番お金が貯まるか」をプロが無料で試算してくれます。
家計の健康診断だと思って、早めに一度チェックしてみてください。浮いたお金で家族旅行に行けるかもしれませんよ!
👉 【無料】何度でも相談OK!世帯年収を最大化するライフプラン相談はこちら![]()