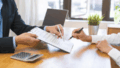「夫の社会保険の扶養に入っていないから、配偶者控除も受けられないよね…」
「自分で健康保険に加入してるし、年末調整の配偶者控除等申告書は関係ないはず」
「扶養を外れたら、税金の優遇も全部なくなっちゃうの?」
そんなふうに思っていませんか?

実は、これは大きな誤解なんです!
社会保険の扶養に入っていなくても、税金の配偶者控除は受けられる場合があります。
この記事では、「扶養」の2つの意味をスッキリ整理!
配偶者控除が受けられる条件から、よくある誤解、年末調整での手続き方法まで、わかりやすく解説します。
扶養には2つの種類がある。混同しないことが大切
「扶養に入っていない」と聞くと、すべての優遇制度が使えないと思ってしまいがち。
でも実は、扶養には2種類あって、それぞれ別のルールで決まっているんです。
社会保険上の扶養は年収130万円が基準

まず1つ目が社会保険上の扶養。
これは、配偶者の健康保険証を使えて、年金も第3号被保険者として保険料がかからない制度です。
この社会保険の扶養に入るには、年収130万円未満という基準があります。
年収130万円を超えると、自分で健康保険と年金に加入することになり、「社会保険の扶養を外れる」状態になります。
税金上の扶養は年収103万円が基準

2つ目が税金上の扶養で、これが「配偶者控除」に関わるもの。
配偶者控除は、配偶者の年収が103万円以下なら受けられる税金の優遇制度です。
重要なのは、この配偶者控除は社会保険の扶養とは完全に別のルールで決まっているということ!

え?扶養って2種類もあるの?全然知らなかったわ!

そうにゃ!ここを混同すると損しちゃうから、しっかり理解するにゃ!
2つの扶養の違いを表で比較

2つの扶養の違いを整理してみましょう。
| 項目 | 社会保険上の扶養 | 税金上の扶養 |
|---|---|---|
| 年収の基準 | 130万円未満 | 103万円以下 |
| 制度 | 健康保険・年金 | 配偶者控除 |
| メリット | 保険料が不要 | 税金が安くなる |
| 関係性 | 互いに独立した制度 | 互いに独立した制度 |
この表を見れば一目瞭然ですよね。
社会保険の扶養に入っていなくても、税金の配偶者控除は別枠で判定されるんです!
税務署から通知が来て青ざめる場合も...
配偶者控除を受けられる条件は扶養とは別
それでは、配偶者控除を受けるための具体的な条件を見ていきましょう。
社会保険の扶養に入っているかどうかは、まったく関係ありません!
配偶者控除の4つの条件

配偶者控除を受けるための条件は、次の4つです。
配偶者控除を受けられる条件
・法律上の配偶者であること(内縁関係はNG)
・納税者と生計を一にしていること
・配偶者の年収が103万円以下であること
・納税者本人の年収が1,120万円以下であること
ここで重要なのは、「社会保険の扶養に入っているか」という条件がないことです。
たとえば、年収100万円で自分で国民健康保険と国民年金に加入している場合でも、配偶者控除は受けられるんです。
生計を一にするとはどういう意味か

「生計を一にする」とは、日常の生活費を共有しているということ。
必ずしも同居している必要はなく、単身赴任などで離れて暮らしていても、生活費を送金していれば「生計を一にする」と認められます。
逆に、同居していても生活費が完全に別なら「生計を一にする」とは認められないこともあるんです。
配偶者控除の控除額はいくら?

配偶者控除を受けると、納税者(夫)の所得税と住民税が安くなります。
控除額は納税者の年収によって変わるので、確認してみましょう。
| 納税者の年収 | 控除額(所得税) | 控除額(住民税) |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 | 33万円 |
| 900万円超~950万円以下 | 26万円 | 22万円 |
| 950万円超~1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 |
| 1,000万円超~1,120万円以下 | 適用なし | 適用なし |
納税者の年収が900万円以下なら、所得税で38万円、住民税で33万円の控除が受けられます。
実際の節税効果は、税率によって異なりますが、年間で5万円~10万円程度になることも珍しくありません。

えぇっ!こんなに税金が安くなるの!?知らなかったわ!

そうにゃ!だから申告を忘れると大損なんだにゃ!
扶養に入っていない場合でも配偶者控除が受けられるケース
具体的なケースを見ながら、どんな場合に配偶者控除が受けられるのか確認しましょう。
実際の状況に当てはめて考えるとわかりやすいです!
ケース1:自分で国民健康保険に加入している場合

年収100万円のパート主婦が、自分で国民健康保険と国民年金に加入している場合。
この場合、社会保険の扶養には入っていませんが、年収103万円以下なので配偶者控除の対象になります。
年末調整で「配偶者控除等申告書」を提出すれば、夫の税金が安くなるんです。
ケース2:フリーランスで働いている場合

フリーランスとして年収80万円を得ている場合。
フリーランスは社会保険の扶養に入れないケースが多いですが、年収103万円以下なら配偶者控除の対象です。
ただし、フリーランスの場合は収入から経費を引いた「所得」が58万円以下であることが条件になります。
| 項目 | 給与所得者 | フリーランス |
|---|---|---|
| 判定基準 | 年収103万円以下 | 所得58万円以下 |
| 計算方法 | 給与収入で判定 | 収入-経費で判定 |
ケース3:パート勤務で社会保険に加入している場合

年収90万円でパート勤務し、勤務先の社会保険に加入している場合。
社会保険の扶養には入っていませんが、年収103万円以下なので配偶者控除が受けられます。
勤務先の社会保険に入っているかどうかは、税金の配偶者控除には一切関係ないんです。

なるほど!社会保険と税金は別々に考えればいいのね♪

その通りにゃ!2つは完全に別物だから、混同しないようにするにゃ!
年収103万円を超えたら配偶者特別控除がある
「年収が103万円を超えちゃったから、もう控除は受けられない…」と諦めていませんか?
実は、103万円を超えても配偶者特別控除という制度があるんです!
配偶者特別控除は年収201万円まで対象

配偶者特別控除は、年収が103万円を超えた場合のセーフティネット。
年収123万円超~201万円以下なら、段階的に控除が受けられます。
もちろん、この配偶者特別控除も社会保険の扶養に入っているかどうかは関係ありません。
年収別の控除額一覧

配偶者特別控除の控除額を見てみましょう(納税者の年収が900万円以下の場合)。
| 配偶者の年収 | 控除額(所得税) |
|---|---|
| 103万円以下 | 38万円(配偶者控除) |
| 123万円超~150万円以下 | 38万円 |
| 150万円超~155万円以下 | 36万円 |
| 155万円超~160万円以下 | 31万円 |
| 160万円超~167万円以下 | 26万円 |
| 167万円超~175万円以下 | 21万円 |
| 175万円超~183万円以下 | 16万円 |
| 183万円超~190万円以下 | 11万円 |
| 190万円超~197万円以下 | 6万円 |
| 197万円超~201万円以下 | 3万円 |
年収150万円までは、配偶者控除と同じ38万円の控除が受けられるんです。
その後は段階的に控除額が減っていきますが、年収201万円までは何らかの控除が受けられます。
103万円の壁を意識しすぎないことも大切

「103万円を超えたら損する」と思って、働く時間を調整している方も多いですよね。
でも、配偶者特別控除があるので、150万円までは満額の控除が受けられます。
もちろん、社会保険料や手取り額との兼ね合いもありますが、「103万円を超えたら全部ダメ」ではないことを覚えておきましょう。
年末調整での配偶者控除の申告方法
配偶者控除を受けるには、年末調整での申告が必要です。
自動では適用されないので、必ず手続きしましょう!
配偶者控除等申告書の記入方法

年末調整では「配偶者控除等申告書」という用紙に記入します。
会社から配られるこの用紙に、配偶者の情報と収入を記入して提出すればOK。
記入が必要な項目
・配偶者の氏名・生年月日
・配偶者のマイナンバー
・配偶者の今年の収入見込額
・配偶者の所得金額
・自分(納税者)の所得金額
配偶者の収入は、1月1日から12月31日までの見込額を記入します。
給与明細を見ながら計算すれば、それほど難しくありません。
年末調整を忘れたら確定申告で対応
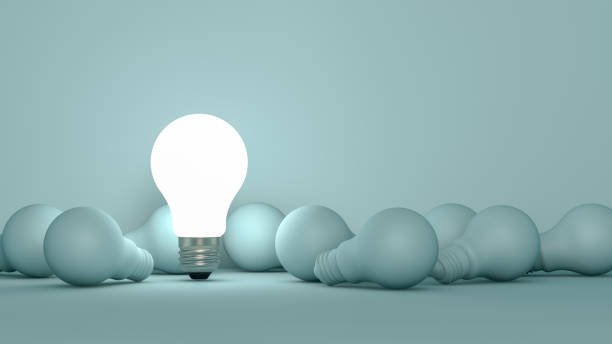
もし年末調整で申告を忘れてしまっても、大丈夫。
翌年の確定申告で配偶者控除を申告すれば、払いすぎた税金が戻ってきます。
確定申告の期間は2月16日から3月15日までですが、還付申告なら1月から受け付けています。
e-Taxなら自宅から簡単に申告できる

確定申告はe-Taxを使えば、自宅から簡単に手続きできます。
マイナンバーカードとスマホがあれば、税務署に行かなくても申告完了。
還付金も、紙で申告するより早く振り込まれるのでおすすめです。

年末調整の書類、ちゃんと出せるか心配だわ…

大丈夫にゃ!給与明細があれば簡単に計算できるにゃ!わからなかったら会社の人に聞いてもいいにゃ!
よくある誤解を解消。扶養と配偶者控除の正しい理解
最後に、配偶者控除についてよくある誤解を整理しましょう。
ここをクリアにすれば、もう迷うことはありません!
誤解1:扶養を外れたら控除は一切受けられない

これは完全に間違いです。
社会保険の扶養と税金の配偶者控除は別物なので、社会保険の扶養を外れても配偶者控除は受けられます。
誤解2:配偶者控除は自動で適用される

これも大きな誤解。
配偶者控除は年末調整または確定申告で申告しないと適用されません。
「条件を満たしているから自動的に控除される」と思っていると、数万円も損してしまいます。
誤解3:103万円を1円でも超えたら控除ゼロ

これも違います。
103万円を超えても、配偶者特別控除が201万円まで段階的に適用されます。
特に150万円までは満額の控除が受けられるので、「103万円を超えたら全部ダメ」ではないんです。

今まで思い込んでたことが、全部間違ってたのね!スッキリしたわ♪

その調子にゃ!正しい知識で、しっかり節税するにゃ!
配偶者控除は扶養に入っていなくても受けられる。正しく理解して賢く節税
配偶者控除は、社会保険の扶養に入っていなくても受けられる税金の優遇制度です。
扶養には2種類あることを理解すれば、もう迷うことはありません。

「社会保険の扶養に入っていないから、税金の控除も使えない」と思い込んでいた方は、ぜひ今年の年末調整で申告してみてください。
年収103万円以下なら配偶者控除、103万円超でも201万円までなら配偶者特別控除が使えます。
この2つの制度を知らないと、年間5万円~10万円も税金を多く払うことになってしまうかもしれません。
配偶者控除は自動では適用されないので、必ず年末調整か確定申告で申告しましょう。
もし今年の年末調整を逃してしまっても、来年の確定申告で取り戻せるので大丈夫。
正しい知識を持って、賢く節税していきましょう!

これで自信を持って年末調整できるわ!ありがとう♪

その意気だにゃ!正しい知識で賢く節税、しっかり応援してるにゃ!
「あと数万円稼げたのに…」「扶養を外れた方が実は手元に多く残ったのに…」
数年後にそう気づいても、過ぎた時間は戻ってきません。
今ならオンラインで、「あなたの場合、いくら稼ぐのが一番お金が貯まるか」をプロが無料で試算してくれます。
家計の健康診断だと思って、早めに一度チェックしてみてください。浮いたお金で家族旅行に行けるかもしれませんよ!
👉 【無料】何度でも相談OK!世帯年収を最大化するライフプラン相談はこちら![]()