「国民健康保険料、高すぎる…」
「毎月こんなに払えない!生活が苦しい…」
「社会保険の時より、なんでこんなに高いの?」
こんな悩みを抱えている方、本当に多いんです。

実は、国民健康保険料が高額になるのには明確な理由があります。
そして、知っていれば使える軽減制度もたくさんあるんです。
この記事では、国民健康保険料が高すぎる理由と、保険料を安くする具体的な方法を徹底解説します。
減免制度や扶養制度の活用法、個人事業主の節約テクニックまで、今すぐ使える情報をお伝えしますので、最後までご覧ください!
国民健康保険料が高すぎる理由
まずは、なぜ国民健康保険料がこんなに高いのか、その理由を見ていきましょう。
保険料の全額を自己負担しなければならない

国民健康保険料が高い最大の理由は、保険料の全額を自分で負担しなければならないことです。
会社員の場合、社会保険料は会社と折半(半分ずつ)で負担します。
つまり、実際の保険料の半分だけを自分が払えばよいんです。
しかし、国民健康保険は全額自己負担のため、同じ所得でも実質的な負担が約2倍になってしまいます。
この負担の差が、「国保は高すぎる」と感じる大きな要因なんです。

えぇっ!会社員の時は半分払ってもらってたのね…知らなかった!

そうにゃ…会社員時代は恵まれてたんだにゃ…
前年の所得を基に計算されるため収入が減っても高い

国民健康保険料は、前年の所得を基に計算されるため、タイムラグが発生します。
例えば、前年は会社員として高収入だったけど、今年は退職して収入が減った場合でも、保険料は前年の高い所得で計算されてしまうんです。
「今は収入が少ないのに、なんでこんなに高いの!」と感じるのは、このためなんですね。
このタイムラグが、生活を圧迫する大きな原因になっています。
ただし、後述する減免制度を使えば、この負担を軽減できる可能性があります。
扶養の概念がなく家族全員分の保険料がかかる

社会保険には「扶養」という制度がありますが、国民健康保険には扶養の概念がありません。
つまり、家族一人ひとりが被保険者として保険料を支払う必要があるんです。
夫婦と子ども2人の4人家族なら、4人分の保険料がかかります。
家族が多い世帯ほど、国保の負担感は重くなってしまいます。
「子どもの分まで保険料がかかるなんて!」と驚く方も多いんです。
40歳以上は介護保険料が加算される

40歳以上の方は、国民健康保険料に介護保険料が加算されます。
この介護保険料も、決して安くはありません。
健康保険料だけでも高いのに、介護保険料まで上乗せされるため、40歳になった途端に保険料が跳ね上がったと感じる方が多いんです。
介護保険料は所得によって異なりますが、年間数万円から十数万円になることもあります。
これが、40代以降の方が「保険料が高すぎる」と感じる要因の一つなんです。

もう無理…生活できないわ…どうすればいいの?

落ち着くにゃ!これから保険料を安くする方法を教えるにゃ!
税務署から通知が来て青ざめる場合も...
国民健康保険料を安くする方法
「高すぎて払えない…」と諦める前に、保険料を安くする方法を知っておきましょう。
実は、使える制度や工夫がいくつもあるんです。
減免・免除制度を利用する
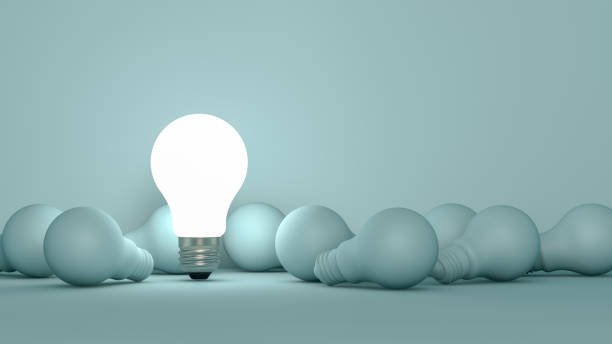
最も効果的なのが、減免・免除制度の利用です。
多くの自治体では、所得が一定以下の場合や、特別な事情がある場合に、保険料の減額や免除を受けられる制度があります。
減免・免除が認められる主なケース
・失業や廃業により収入が大幅に減少した
・世帯の所得が一定基準以下である
・災害により住宅や家財に損害を受けた
・世帯主が死亡、または重度の障害を負った
・新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した
減免制度は自治体によって条件が異なるため、まずはお住まいの市区町村の窓口に相談してみましょう。
申請すれば、保険料が2割〜7割減額されることもあるんです。
「知らなかった」という理由で損をしている方が本当に多いんです。
まずは市区町村に問い合わせてみることをおすすめします。
家族の社会保険の扶養に入る
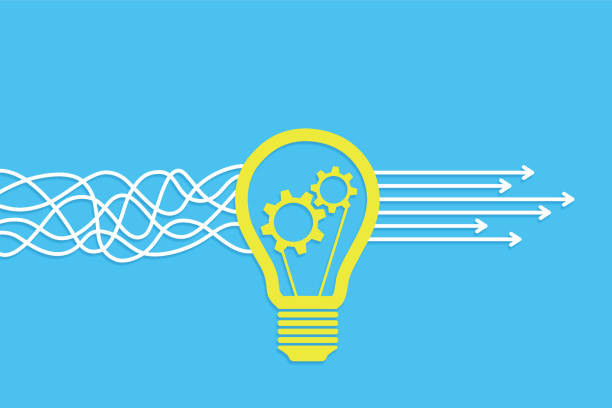
配偶者や親など、社会保険に加入している家族の扶養に入ることで、保険料の負担をゼロにできます。
扶養に入るための主な条件は、年収130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)です。
パート勤務の主婦の方などは、この扶養制度を活用することで、大幅に負担を減らせるんです。
ただし、扶養に入ると年収に制限がかかるため、収入を増やしたい方には向きません。
自分のライフスタイルに合わせて、判断することが大切です。

え!夫の扶養に入れば保険料ゼロになるの?

そうにゃ!年収130万円未満なら扶養に入れるにゃ!
青色申告特別控除で所得を抑える(個人事業主向け)

個人事業主の方は、青色申告特別控除を活用することで、所得を抑えることができます。
青色申告をすると、最大65万円の特別控除が受けられるため、その分所得が減り、保険料の計算基礎額も下がるんです。
青色申告には事前の届出が必要ですが、保険料だけでなく所得税や住民税も減るため、個人事業主の方には強くおすすめします。
法人化して社会保険に加入する(個人事業主向け)

収入が一定以上ある個人事業主の方は、法人化して社会保険に加入することで、保険料を抑えられる場合があります。
法人化すると、自分自身が会社の代表者として社会保険に加入できます。
報酬額を調整することで、国保よりも安い保険料に抑えられることもあるんです。
法人化は、年収が500万円以上ある方に特にメリットがあると言われています。
税理士に相談して、シミュレーションしてもらうとよいでしょう。
国民健康保険料が払えない時の対処法
「どうしても払えない…」という時は、放置せずに必ず対処しましょう。
市区町村の窓口で分割納付を相談する

保険料が払えない場合は、市区町村の窓口で分割納付を相談しましょう。
一括では払えなくても、月々の支払額を減らして、分割で納めることができる場合があります。
放置して滞納すると、督促や差し押さえに発展する可能性があるため、早めに相談することが重要です。
「払えない」ということは恥ずかしいことではありません。
多くの方が同じ悩みを抱えています。
勇気を出して相談してみましょう。
短期被保険者証や資格証明書が交付される可能性

滞納が続くと、短期被保険者証や資格証明書が交付されることがあります。
短期被保険者証は有効期間が短い保険証で、頻繁に更新が必要になります。
さらに滞納が続くと、資格証明書が交付され、医療費が一時的に10割自己負担になってしまうんです。
このような事態を避けるためにも、払えない場合は必ず窓口に相談しましょう。
絶対に放置してはいけない理由

保険料を滞納し続けると、最終的には財産の差し押さえに発展します。
国民健康保険料は税金と同じように、強制徴収の対象なんです。
給与や預貯金、不動産などが差し押さえられる可能性があるため、絶対に放置してはいけません。

うぅ…どうしよう…本当に払えないのよ…

だからこそ、一人で抱え込まずに市役所に相談するにゃ!必ず解決策はあるにゃ!
国民健康保険料が高すぎる。負担を減らす方法を知って対策しよう:まとめ
国民健康保険料が高いのには、明確な理由があります。

しかし、減免制度や扶養制度、青色申告など、負担を減らす方法はいくつもあるんです。
「高すぎて払えない」と諦める前に、まずは市区町村の窓口に相談してみましょう。
減免制度や分割納付など、必ず何かしらの対策があります。
一人で悩まず、勇気を出して相談することが、解決への第一歩です。
この記事で紹介した方法を参考に、自分に合った対策を見つけてくださいね。

なるほど!まずは減免制度が使えるか、市役所に聞いてみるわ♪

その調子にゃ!知識があれば、必ず道は開けるにゃ!
「あと数万円稼げたのに…」「扶養を外れた方が実は手元に多く残ったのに…」
数年後にそう気づいても、過ぎた時間は戻ってきません。
今ならオンラインで、「あなたの場合、いくら稼ぐのが一番お金が貯まるか」をプロが無料で試算してくれます。
家計の健康診断だと思って、早めに一度チェックしてみてください。浮いたお金で家族旅行に行けるかもしれませんよ!
👉 【無料】何度でも相談OK!世帯年収を最大化するライフプラン相談はこちら![]()


