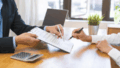「配偶者控除で38万円もらえるって聞いたけど、本当?」
「38万円がそのまま戻ってくるの?」
「うちは条件を満たしてるのかな?」
そんな疑問を持っていませんか?

実は、配偶者控除の「38万円」というのは、38万円が戻ってくるわけではありません。
これは「控除額」であって、実際に安くなる税金は所得税率によって変わるんです。
この記事では、配偶者控除38万円の正しい意味から、実際にいくら税金が安くなるのか、満額もらえる条件まで、わかりやすく解説します!
配偶者控除38万円の正しい意味。もらえるのは控除額
まず最初に、配偶者控除の「38万円」が何を意味するのか、正しく理解しましょう。
ここを間違えると、期待していた金額と違う…なんてことになってしまいます。
配偶者控除38万円は所得控除の金額

配偶者控除の「38万円」は、所得控除の金額です。
これは、税金を計算する前の「所得」から38万円を差し引くという意味なんです。
つまり、38万円がそのまま戻ってくるわけではなく、38万円×税率の金額だけ税金が安くなる仕組み。
実際にもらえる金額は税率によって変わる

実際に安くなる税金は、納税者(夫)の所得税率によって変わります。
所得税率は、年収が高いほど高くなる累進課税制度なんです。
| 年収の目安 | 所得税率 | 実際の節税額(所得税) |
|---|---|---|
| 300万円~500万円 | 10% | 約3.8万円 |
| 500万円~700万円 | 20% | 約7.6万円 |
| 700万円~900万円 | 23% | 約8.7万円 |
| 900万円以上 | 23%~33% | 約8.7万円~12.5万円 |
たとえば、年収500万円の夫なら、所得税率は10%なので、38万円×10%=3.8万円の節税になります。

えっ?38万円もらえるわけじゃないの?

そうにゃ!38万円は控除額で、実際の節税額は税率次第なんだにゃ!
住民税の控除も含めると7万円~12万円の節税

配偶者控除は、所得税だけでなく住民税も安くなります。
住民税の配偶者控除額は33万円で、税率は一律10%なので、約3.3万円の節税になるんです。
| 年収の目安 | 所得税の節税額 | 住民税の節税額 | 合計節税額 |
|---|---|---|---|
| 300万円~500万円 | 約3.8万円 | 約3.3万円 | 約7.1万円 |
| 500万円~700万円 | 約7.6万円 | 約3.3万円 | 約10.9万円 |
| 700万円~900万円 | 約8.7万円 | 約3.3万円 | 約12.0万円 |
所得税と住民税を合わせると、年間7万円~12万円程度の節税効果があるんです!
税務署から通知が来て青ざめる場合も...
配偶者控除38万円を満額もらえる条件
配偶者控除で38万円の満額控除を受けるには、いくつかの条件があります。
すべての条件を満たす必要があるので、しっかり確認しましょう!
条件① 配偶者の年収が103万円以下

配偶者控除38万円をもらえる最も重要な条件は、配偶者の年収が103万円以下であること。
給与所得の場合は年収103万円以下、自営業などの場合は所得58万円以下が基準です。
収入の種類別基準
・給与所得(パート・アルバイト):年収103万円以下
・事業所得(自営業・フリーランス):所得58万円以下
・年金所得(65歳未満):年収108万円以下
・年金所得(65歳以上):年収158万円以下
この基準を1円でも超えると、配偶者控除ではなく配偶者特別控除の対象になります。
条件② 納税者本人の年収が900万円以下

配偶者控除38万円の満額を受けるには、納税者本人(夫)の年収が900万円以下という条件もあります。
夫の年収が900万円を超えると、控除額が段階的に減っていくんです。
| 納税者(夫)の年収 | 配偶者控除額 |
|---|---|
| 900万円以下 | 38万円(満額) |
| 900万円超~950万円以下 | 26万円 |
| 950万円超~1,000万円以下 | 13万円 |
| 1,000万円超~1,195万円以下 | 0円(対象外) |
夫の年収が1,000万円(所得1,000万円)を超えると、配偶者控除は一切受けられません。

夫の年収にも条件があるのね!満額もらうには900万円以下なのね!

そうにゃ!夫婦両方の年収をチェックする必要があるにゃ!
条件③ その他の必須条件も確認

年収以外にも、配偶者控除を受けるための条件があります。
これらの条件をすべて満たして初めて、配偶者控除38万円が受けられるんです。
配偶者控除38万円をもらうための具体的な手続き
条件を満たしていても、申告しないと配偶者控除は受けられません。
具体的な手続き方法を確認しましょう!
会社員なら年末調整で申告

会社員の場合は、年末調整で「配偶者控除等申告書」を提出します。
この用紙に配偶者の情報と年収見込額を記入するだけでOK。
会社が年末調整を行ってくれるので、38万円分の控除が自動的に反映されます。
年末調整で記入する項目
・配偶者の氏名・生年月日
・配偶者のマイナンバー
・配偶者の年収見込額
・自分(納税者)の所得金額
・控除額の計算
年末調整の時期は11月下旬~12月上旬なので、この時期を逃さないようにしましょう。
自営業なら確定申告で申告

自営業やフリーランスの場合は、確定申告で配偶者控除を申告します。
確定申告書の「配偶者控除」の欄に38万円と記入すれば、所得から控除されます。
確定申告の期間は2月16日~3月15日ですが、e-Taxを使えば自宅から簡単に申告できるので便利です。
年末調整を忘れたら確定申告で取り戻せる

もし年末調整で配偶者控除の申告を忘れてしまっても、大丈夫。
翌年の確定申告で申告すれば、払いすぎた税金が還付されます。
還付申告なら1月から受け付けているので、早めに手続きすれば早く還付金が振り込まれるんです。

年末調整を忘れちゃったらどうしよう…

大丈夫にゃ!確定申告で取り戻せるから安心するにゃ!
103万円を超えたら38万円はもらえない?配偶者特別控除との違い
「年収が103万円を超えちゃったから、38万円の控除は受けられない…」と思っていませんか?
実は、条件次第では103万円を超えても38万円の控除が受けられるんです!
配偶者特別控除なら150万円まで38万円

年収103万円を超えると配偶者控除ではなく「配偶者特別控除」の対象になりますが、年収150万円までは38万円の満額控除が受けられるんです。
つまり、103万円を超えても、150万円までなら同じ控除額が受けられるということ。
| 配偶者の年収 | 控除額 | 控除の種類 |
|---|---|---|
| 103万円以下 | 38万円 | 配偶者控除 |
| 103万円超~150万円以下 | 38万円 | 配偶者特別控除 |
| 150万円超~155万円以下 | 36万円 | 配偶者特別控除 |
| 155万円超 | 段階的に減少 | 配偶者特別控除 |
「103万円の壁」と言われますが、税金面では150万円まで満額の控除が受けられるので、それほど気にしなくても大丈夫なんです。
配偶者控除と配偶者特別控除の違い

配偶者控除と配偶者特別控除の違いをまとめてみましょう。
| 項目 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 |
|---|---|---|
| 対象年収 | 103万円以下 | 103万円超~201万円以下 |
| 最大控除額 | 38万円 | 38万円 |
| 控除額の変化 | 一律38万円 | 年収に応じて段階的に減少 |
| 年齢加算 | 70歳以上は48万円 | なし |
配偶者が70歳以上の場合、配偶者控除なら48万円に増額されますが、配偶者特別控除には年齢加算がありません。
社会保険の扶養は別の話

注意が必要なのは、税金の配偶者控除と社会保険の扶養は別物だということ。
税金面では150万円まで満額控除が受けられますが、社会保険の扶養は年収130万円未満が条件です。
130万円を超えると自分で健康保険と年金に加入する必要があり、保険料負担が発生するので注意しましょう。

なるほど!150万円まで38万円もらえるのね♪

その通りにゃ!だから103万円を超えたからって諦めなくていいにゃ!
配偶者控除38万円でよくある誤解と注意点
配偶者控除の38万円について、よくある誤解や見落としやすいポイントをまとめます。
ここをクリアにすれば、もう迷うことはありません!
誤解① 38万円が現金でもらえると思っている

これが最も多い誤解です。
配偶者控除の38万円は所得控除の金額であって、現金でもらえるわけではありません。
実際に安くなる税金は、38万円×税率の金額なので、年収によって3.8万円~12万円程度になります。
誤解② 配偶者の収入にパート代しか含めない

配偶者の収入を計算する際、パート代しか見ていないケースが多いです。
実は、給与以外の収入も合算する必要があるんです。
配偶者の収入に含まれるもの
・パート・アルバイトの給与
・公的年金(雑所得)
・生命保険の満期返戻金(一時所得)
・不動産収入
・株式の配当金(総合課税の場合)
・フリーランスの事業収入
特に見落としやすいのが生命保険の満期返戻金。
これも所得に含まれるので、年末に満期金を受け取った場合は注意が必要です。
注意点 年末調整後に収入が変わった場合

年末調整では配偶者の収入を「見込額」で申告します。
もし実際の収入が見込額と大きく違った場合は、確定申告で修正する必要があるんです。
特に、年末にボーナスや臨時収入があった場合は要注意。
103万円を超えてしまっても、150万円までなら38万円の控除は受けられるので、正しく申告し直しましょう。
配偶者控除38万円を正しく理解して賢く節税。まとめ
配偶者控除の「38万円」は、現金でもらえるわけではなく所得控除の金額です。
実際の節税効果は年収によって7万円~12万円程度になります。

配偶者控除38万円を満額受けるには、配偶者の年収103万円以下、納税者本人の年収900万円以下という条件を満たす必要があります。
ただし、103万円を超えても150万円までは配偶者特別控除で38万円の満額控除が受けられるので、「103万円を超えたら終わり」ではありません。
配偶者控除は申告しないと適用されないので、必ず年末調整か確定申告で手続きしましょう。
もし今年の年末調整を逃してしまっても、来年の確定申告で取り戻せるので大丈夫。
「38万円がもらえる」という誤解をせず、正しく理解して賢く節税していきましょう!

38万円の意味がよくわかったわ!これで安心して申告できる♪

その意気だにゃ!正しく理解して、しっかり節税するにゃ!
「あと数万円稼げたのに…」「扶養を外れた方が実は手元に多く残ったのに…」
数年後にそう気づいても、過ぎた時間は戻ってきません。
今ならオンラインで、「あなたの場合、いくら稼ぐのが一番お金が貯まるか」をプロが無料で試算してくれます。
家計の健康診断だと思って、早めに一度チェックしてみてください。浮いたお金で家族旅行に行けるかもしれませんよ!
👉 【無料】何度でも相談OK!世帯年収を最大化するライフプラン相談はこちら![]()