「配偶者特別控除って、結局いくら戻るの?」
「103万円と150万円、どっちが得なの?」
「年末調整で申告したら、いくら還付されるのかな?」
パートで働く主婦の方なら、一度は気になったことがあるのではないでしょうか。

配偶者特別控除を使うと、夫の税金がおおよそ2万円〜8万円ほど安くなる可能性があります。
でも、正確な金額は配偶者の年収と夫の所得によって変わるんです。
この記事では、配偶者特別控除で実際にいくら戻るのか、年収別のシミュレーションと計算方法を分かりやすく解説します。
2025年の最新改正情報も含めて、あなたの家計がどれくらい得するのか、具体的な金額をお伝えしますね。
配偶者特別控除でいくら戻る?基本の仕組み
まず最初に、配偶者特別控除で「いくら戻る」のか、基本的な仕組みを理解しておきましょう。
この制度を使うことで、夫の所得税や住民税が安くなるんです。
「戻る」とは何を意味するのか
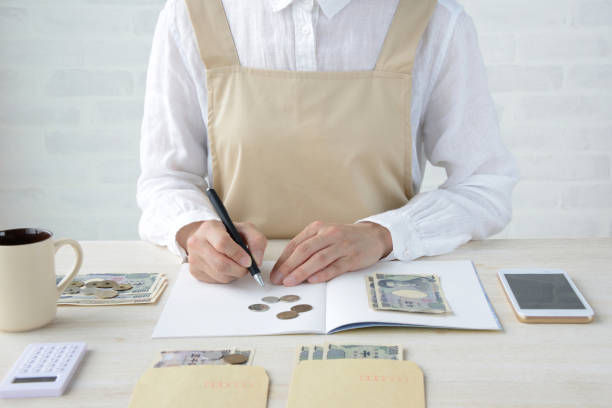
配偶者特別控除で「いくら戻る」という言葉、実は2つの意味があります。
1つ目は、年末調整で還付金として実際に現金が戻ってくる場合。
2つ目は、翌年の住民税が安くなることで、結果的に家計の負担が減る場合です。
多くの方がイメージする「戻る」は、年末調整でお給料と一緒に振り込まれる還付金のことですよね。
控除額と還付金額は違う

ここで注意したいのが、控除額と還付金額は別物だということ。
例えば、配偶者特別控除で38万円の控除を受けられたとしても、38万円が戻ってくるわけではありません。
実際に戻る金額は、控除額 × 夫の所得税率で計算されます。
夫の年収が500万円前後なら所得税率は10%程度なので、38万円の控除があると約3.8万円が所得税で戻る計算になります。
さらに住民税は一律10%なので、38万円 × 10% = 3.8万円が翌年の住民税から減額されるんです。

えっ、控除額がそのまま戻ってくるわけじゃないの?

そうなんだにゃ!控除額に税率をかけた金額が実際に戻る額だにゃ。でも所得税と住民税の両方で軽減されるから、トータルでは結構大きいにゃ!
2025年改正で160万円まで拡大

2025年から配偶者特別控除が改正され、配偶者の年収上限が160万円に引き上げられました。
これまでは150万円までが満額控除(38万円)の対象でしたが、改正後は160万円まで満額控除を受けられます。
つまり、配偶者の年収が103万円でも160万円でも、同じ38万円の控除が受けられるようになったんです。
これは働く主婦にとって、かなり大きな変更ですよね。
税務署から通知が来て青ざめる場合も...
配偶者の年収別・いくら戻るかシミュレーション
それでは、配偶者の年収別に「実際いくら戻るのか」を具体的に見ていきましょう。
ここでは、夫の年収が500万円前後のケースを想定して計算します。
年収103万円の場合・配偶者控除との違い

配偶者の年収が103万円以下の場合、適用されるのは配偶者控除です。
配偶者特別控除ではなく、配偶者控除の方が適用されるんですね。
控除額は38万円(満額)で、夫の所得税率が10%なら約3.8万円、住民税で約3.8万円、合計で約7〜8万円ほどの減税効果があります。
年末調整での還付金は約3.8万円、翌年の住民税が月額3,000円ほど安くなる計算です。
年収103万円の場合の戻る金額
・控除額:38万円(満額)
・所得税の還付:約3.8万円
・住民税の軽減:約3.8万円
・合計減税効果:約7〜8万円
年収130万円の場合・扶養の壁を超えたら

年収が130万円になると、社会保険の扶養から外れる可能性があります。
ただし、配偶者特別控除は引き続き受けられます。
配偶者の所得が75万円(給与収入130万円)の場合、控除額は約21万円程度になります。
夫の所得税率が10%なら約2.1万円、住民税で約2.1万円、合計で約4〜5万円の減税効果です。
103万円の壁と比べると控除額は減りますが、それでも家計の負担はしっかり軽減されますよ。

130万円超えたら控除がなくなるんじゃないの!?

それは違うにゃ!130万円は社会保険の壁で、配偶者特別控除は201万円まで使えるにゃ!混同しないようにするにゃ!
年収150万円・160万円の場合・2025年改正の恩恵

年収が150万円や160万円になると、2025年改正の恩恵を最大限に受けられます。
配偶者の年収が160万円以下なら、控除額は満額の38万円です。
夫の所得税率が10%なら約3.8万円、住民税で約3.8万円、合計で約7〜8万円の減税効果があります。
103万円に抑えていた時と同じ控除額で、年収は50万円以上多く稼げるんです。
これは働く主婦にとって、本当に大きなメリットですよね。
配偶者特別控除の計算方法を分かりやすく解説
「自分の場合はいくら戻るの?」と正確に知りたい方のために、計算方法を解説します。
少し複雑に感じるかもしれませんが、ステップごとに進めれば誰でも計算できますよ。
ステップ1・配偶者の所得金額を確認する

まず最初に、配偶者の所得金額を確認します。
給与収入がある場合、収入から給与所得控除を引いた金額が「所得金額」になります。
例えば、年収150万円の場合の給与所得控除は55万円なので、所得金額は95万円です。
年収103万円なら、所得金額は48万円になります。
給与収入と所得金額の関係
・年収103万円 → 所得48万円
・年収130万円 → 所得75万円
・年収150万円 → 所得95万円
・年収160万円 → 所得105万円
・年収201万円 → 所得133万円
ステップ2・控除額を確認する

配偶者の所得金額が分かったら、次は控除額を確認します。
夫の所得が900万円以下の場合、配偶者の所得に応じて以下の控除額が適用されます。
配偶者の所得48万円以下:配偶者控除38万円
配偶者の所得48万円超95万円以下:38万円
95万円超100万円以下:36万円
100万円超105万円以下:31万円
105万円超110万円以下:26万円
110万円超115万円以下:21万円
115万円超120万円以下:16万円
120万円超125万円以下:11万円
125万円超130万円以下:6万円
130万円超133万円以下:3万円
133万円超:0円
夫の所得が900万円を超えると、控除額は段階的に減っていきます。
ステップ3・還付金額を計算する

控除額が分かったら、最後に還付金額を計算します。
計算式は以下の通りです。
還付金額(所得税)= 配偶者特別控除額 × 夫の所得税率
夫の年収が500万円前後なら、所得税率は10%程度です。
例えば控除額が38万円なら、38万円 × 10% = 3.8万円が所得税から還付されます。
さらに住民税は一律10%なので、38万円 × 10% = 3.8万円が翌年の住民税から軽減されます。
合計で約7〜8万円の減税効果になるわけです。

なるほど!控除額に税率をかければいいのね♪

そうにゃ!所得税と住民税の両方で軽減されるから、意外と大きな金額になるにゃ!
配偶者特別控除を受けるための手続き方法
配偶者特別控除を受けるには、必ず申告が必要です。
申告しないと控除はゼロなので、手続きを忘れないようにしましょう。
年末調整で申告する方法

会社員の夫が配偶者特別控除を受ける場合、年末調整で申告します。
勤務先から配られる「給与所得者の配偶者控除等申告書」に、配偶者の氏名、生年月日、年収見込みを記入します。
この書類を提出すれば、12月の給与または賞与で還付金が振り込まれます。
提出期限は会社によって異なりますが、多くの場合11月中旬から12月上旬です。
年末調整で必要な情報
・配偶者の氏名と生年月日
・配偶者の年収見込み額
・配偶者のマイナンバー(初回のみ)
・配偶者の所得の種類(給与・事業など)
確定申告で申告する方法

年末調整で申告を忘れた場合や、自営業の方は確定申告で配偶者特別控除を申告できます。
確定申告書の「配偶者(特別)控除」の欄に、配偶者の所得金額と控除額を記入します。
e-Taxを使えば自宅から簡単に申告できますし、税務署の窓口や郵送でも提出できます。
確定申告の期間は2月16日から3月15日までですが、還付申告なら1月から受け付けてもらえますよ。
申告を忘れた場合の対処法

年末調整で配偶者特別控除の申告を忘れてしまった場合でも、大丈夫です。
確定申告で遡って申告できます。
過去5年分まで遡って還付申告ができるので、忘れていたことに気づいたらすぐに手続きしましょう。
例えば2024年分の配偶者特別控除を忘れていた場合、2029年12月31日まで還付申告が可能です。
数万円の還付金を受け取り損ねるのはもったいないですから、気づいた時点で手続きしてくださいね。

去年申告するの忘れちゃってたかも…

大丈夫にゃ!5年以内なら確定申告で還付してもらえるにゃ。今からでも間に合うから手続きするにゃ!
配偶者特別控除でよくある間違いと注意点
配偶者特別控除を申告する際、多くの方が勘違いしやすいポイントがあります。
損をしないために、よくある間違いを確認しておきましょう。
年収見込みで判断される
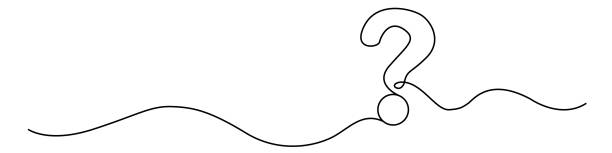
年末調整で配偶者特別控除を申告する際、配偶者の年収は「年収見込み」で判断されます。
12月の給与をもらう前に申告書を提出するため、その時点での見込み額で記入するんです。
でも、実際の年収が見込みと大きくずれた場合は要注意。
例えば、見込みでは150万円以下と申告したのに、年末のボーナスで160万円を超えてしまった場合、控除額が変わる可能性があります。
この場合は、翌年の確定申告で修正する必要があります。
社会保険の扶養とは別物

配偶者特別控除と社会保険の扶養は、まったく別の制度です。
配偶者特別控除は201万円まで使えますが、社会保険の扶養は年収130万円が基準になります。
年収が130万円を超えると、自分で社会保険に加入する必要が出てきます。
この場合、健康保険料や厚生年金保険料を自分で支払うことになるので、手取り額が大きく減ることも。
配偶者特別控除が使えるからといって、社会保険の扶養が外れないわけではないんです。
年収の壁の違い
・103万円の壁:配偶者控除の境界
・130万円の壁:社会保険の扶養の境界
・150万円の壁:旧配偶者特別控除満額の境界
・160万円の壁:2025年改正後の満額境界
・201万円の壁:配偶者特別控除の上限
申告しないと控除はゼロ

配偶者特別控除は、自動では適用されません。
必ず年末調整や確定申告で申告する必要があります。
「妻が扶養内で働いているから自動的に控除される」と思っている方がいますが、それは間違いです。
毎年、会社から配られる「配偶者控除等申告書」にきちんと記入して提出しないと、控除額はゼロになってしまいます。
数万円の減税を受け損ねないように、必ず申告しましょう。

えっ、申告しなくても自動で控除されるんだと思ってた!

それは大きな間違いにゃ!申告しないと控除ゼロだから、毎年忘れずに書類を出すにゃ!
配偶者特別控除を最大限活用するコツ
配偶者特別控除を最大限に活用するには、いくつかのコツがあります。
賢く働いて、家計を最大化しましょう。
160万円ラインを狙う働き方

2025年改正で、年収160万円まで満額控除が受けられるようになりました。
これは大きなチャンスです。
103万円に抑えていた方は、もっと働いても同じ控除額が受けられます。
年収を160万円まで増やせば、世帯収入が50万円以上アップします。
もちろん、社会保険料の負担は増えますが、将来の年金額も増えるので、長期的に見ればメリットが大きいですよ。
年末調整前に年収を確認

年末調整の時期が来たら、必ず配偶者の年収見込みを確認しましょう。
給与明細を見ながら、12月の給与とボーナスを含めた年収を計算します。
特に、ボーナスがある方は注意が必要です。
ボーナス額によっては、思った以上に年収が増えて控除額が変わることもあります。
正確な見込み額を申告することで、追加徴税のリスクを避けられますよ。
iDeCoや医療費控除も併用する

配偶者特別控除だけでなく、他の控除も併用すると、さらに節税効果が高まります。
例えば、夫がiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入すれば、掛金全額が所得控除になります。
医療費が年間10万円を超えた場合は、医療費控除も使えます。
複数の控除を組み合わせることで、税金をグッと抑えられるんです。
年末調整や確定申告の際に、使える控除を漏れなくチェックしましょう。
併用できる主な控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・医療費控除
・iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)
・ふるさと納税(寄附金控除)
しごママで扶養内の働き方をもっと詳しく
配偶者特別控除について理解できても、「結局、自分はどう働くのが一番得なの?」と迷う方も多いはず。
扶養内で働くべきか、それとも扶養を外れてガッツリ働くべきか、ライフスタイルに合った選択が大切です。

「しごママ」では、主婦の働き方に関する情報を幅広く発信しています。
扶養内で働く際の年収の壁、社会保険の加入条件、パートと派遣の違い、履歴書の書き方まで、再就職に必要な情報を網羅的に掲載しています。
「何から始めればいいか分からない」という方は、ぜひ他の記事もチェックしてみてくださいね。

控除のことは分かったけど、結局どう働くのが一番いいのかしら?

それはライフスタイル次第にゃ!しごママの他の記事で、年収別のメリット・デメリットを詳しく解説してるから、参考にしてみるといいにゃ!
配偶者特別控除でいくら戻るか。賢く申告して家計を守ろう
配偶者特別控除でいくら戻るかは、配偶者の年収と夫の所得によって変わります。
2025年の改正で年収160万円まで満額控除が受けられるようになり、働く主婦にとって大きなメリットが生まれました。

年収103万円でも160万円でも、満額38万円の控除が受けられます。
夫の年収が500万円前後なら、所得税と住民税合わせて約7〜8万円の減税効果があるんです。
申告を忘れると控除額はゼロになってしまうので、毎年きちんと手続きすることが大切です。
過去5年分まで遡って還付申告できるので、忘れていた方も今からでも間に合います。
配偶者特別控除を正しく理解して申告すれば、数万円の節税が実現できます。
あなたの家計に合った働き方を選んで、賢く制度を活用していきましょう。
少しの手間で家計が楽になるなら、やらない理由はありませんよね!
「あと数万円稼げたのに…」「扶養を外れた方が実は手元に多く残ったのに…」
数年後にそう気づいても、過ぎた時間は戻ってきません。
今ならオンラインで、「あなたの場合、いくら稼ぐのが一番お金が貯まるか」をプロが無料で試算してくれます。
家計の健康診断だと思って、早めに一度チェックしてみてください。浮いたお金で家族旅行に行けるかもしれませんよ!
👉 【無料】何度でも相談OK!世帯年収を最大化するライフプラン相談はこちら![]()


