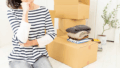「夫が個人事業主だから、私の年収制限ってあるの?」
「扶養から外れる年収ラインって、いくらまで?」
「130万円ってよく聞くけど、本当の基準は何なの?」
自営業の夫を持つ主婦の方なら、こんな疑問を感じたことはないでしょうか。

実は、個人事業主の場合、配偶者の扶養制度は少し複雑なんです。
会社員の夫と異なり、個人事業主(自営業)の妻は「健康保険の扶養家族」という制度に入れないことが多いからです。
この記事では、個人事業主の妻が年収によって何がどう変わるのか、実務的な観点から徹底解説します。
130万円の壁、103万円の壁、48万円の壁。どれが自分に関係あるのか、スッキリ理解できるようになります。
個人事業主の配偶者に「扶養」という概念はない
まず、大切な前提を理解してください。
個人事業主(自営業)の配偶者には、健康保険の扶養という制度が基本的に存在しません。
会社員とは異なる個人事業主の健康保険制度

会社員(給与所得者)の夫なら、妻は「被扶養配偶者」として健康保険に入ることができます。
しかし個人事業主の場合、ほとんどが国民健康保険に加入しており、自営業者の配偶者も国民健康保険に自分で加入する必要があるんです。
つまり、扶養から外れるという概念自体が当てはまらないんです。
ただし、社会保険加入要件の年収基準はある

「扶養から外れる」という表現は正確ではありませんが、年収が増えると実質的な負担が変わるポイントは存在します。
これが「社会保険の加入要件」に関わる年収基準です。
妻がパートやアルバイトで働く場合、年収によって「保険料負担」が発生するタイミングが変わってきます。

え、扶養から外れるんじゃなくて、最初からいないってこと?

そういうことだにゃ。個人事業主の場合、健康保険の扶養制度がないんだにゃ!
税務署から通知が来て青ざめる場合も...
個人事業主の妻が気にすべき年収の壁。実質的な負担が変わるラインとは
では、年収がいくらになると、実質的な負担が変わるのでしょうか。
いくつかの重要なラインがあります。
48万円の壁。配偶者控除がなくなる年収ライン

妻の年収が48万円を超えると、税金の「配偶者控除」がなくなります。
ただし、これは税金の話。健康保険とは関係ありません。
配偶者控除がなくなると、夫の税負担が少し増えるという仕組みです。
48万円の壁で何が変わる?
妻の年収が48万円以下 → 夫が配偶者控除を受ける → 夫の税金が安くなる
妻の年収が48万円超 → 配偶者控除がなくなる → 夫の税金が増える
103万円の壁。妻の所得税が発生するライン

妻の給与年収が103万円を超えると、妻自身に所得税がかかり始めます。
これが「103万円の壁」と呼ばれるものです。
ただし、これも個人事業主の扶養とは直接の関係がありません。
個人事業主の配偶者の場合、すでに国民健康保険の保険料を払っているため、この壁はあまり心配する必要がないんです。
130万円の壁。社会保険加入要件が変わるポイント

年収が130万円を超えると、妻が自分で「厚生年金保険料」を払う対象になる可能性があります。
ただし、これは勤務先の企業規模や勤務時間などによって判断されます。
パート先で社会保険加入要件を満たす場合は、年収130万円付近で社会保険料(健康保険+厚生年金)の支払いが発生することもあります。
個人事業主の妻が気にすべき年収ラインまとめ
【48万円の壁】税金の配偶者控除がなくなる
→ 夫の税負担が増える
【103万円の壁】妻に所得税が発生
→ 妻が税金を払う必要がある
【130万円の壁】社会保険加入要件
→ パート先で社会保険に加入する可能性

色々なラインがあるんだ。でも扶養から外れるわけじゃないんだ。

そう。個人事業主の場合は「実質的な負担が増える年収ライン」と考えるのが正確だにゃ。
個人事業主の妻が国民健康保険から逃げられない理由
では、なぜ個人事業主の配偶者は扶養に入れないのでしょうか。
その背景を理解することが大切です。
個人事業主は国民健康保険に加入する

会社員なら「社会保険」に加入しますが、個人事業主は「国民健康保険」に加入します。
これが根本的な違いです。
会社員の場合、企業が社会保険を用意していて、その中に「扶養制度」が組み込まれているんです。
しかし個人事業主は、法人化していない限り社会保険に入れません。
だから、配偶者も「自分で国民健康保険に加入する」という仕組みなんです。
配偶者も個別に国民健康保険料を払う必要がある

会社員の妻なら、夫の社会保険に扶養として入るので保険料がかかりません。
しかし個人事業主の妻は、たとえ年収がいくら低かろうと、自分で国民健康保険料を支払う必要があるんです。
つまり「扶養から外れる」ではなく、最初から「保険料を払う立場」にいるわけです。

えー、そんなら最初から自分で払わないといけないってこと?

そういうことだにゃ。個人事業主の妻は、扶養の選択肢がないんだにゃ。
個人事業主の妻の年収。税金と保険料の関係を整理する
では、実際のところ、個人事業主の妻の年収が増えるとどんな負担が出てくるのでしょうか。
具体的に見ていきましょう。
年収100万円以下なら、税金の心配はほぼなし

妻の年収が100万円以下なら、
・所得税はかからない
・住民税もかからない(市区町村による)
・社会保険料も発生しない
ただし、国民健康保険料と国民年金は払う必要があります。
この点が会社員の妻と大きく異なるところです。
年収100万円から150万円。税金が発生し始める

年収が103万円を超えると、妻に所得税が発生し始めます。
130万円を超えると、勤務先によってはパート先の社会保険加入要件に該当する可能性が出てきます。
この帯域での手取りがどう変わるかは、年収や社会保険加入の有無によって大きく異なります。
年収150万円以上。本格的に税金と保険料が発生

年収150万円を超えると、所得税と住民税、そして勤務先の社会保険料(健康保険+厚生年金)がしっかり発生します。
この場合、手取りは思ったほど増えていない可能性もあります。
ただし、一度社会保険に加入すれば、厚生年金の加入期間が増えるというメリットもあります。
個人事業主の妻の年収と負担の目安
【年収100万円以下】
所得税:なし 住民税:なし 所得税の負担:少ない
【年収100〜150万円】
所得税:発生 住民税:発生する可能性 社会保険:確認が必要
【年収150万円以上】
所得税:本格的に発生 住民税:発生 社会保険:加入の可能性が高い

あ、やっぱりいろいろ複雑なんだ…

だけど大事なのは「扶養から外れる」という発想を捨てることだにゃ。元々扶養じゃないんだから!
夫が個人事業主の場合、妻はいくらまで稼ぐのが得なのか
「では、実際のところ、妻はいくらまで稼ぐのが得なんですか?」
この質問は、個人事業主の妻から最も多く出される質問です。
妻が100万円までなら、税金の負担は最小限

妻の年収が100万円まで保つなら、所得税も住民税も基本的にかかりません。
夫の税務申告の際に、配偶者控除や扶養控除を受けられる可能性も高いです。
ただし、国民健康保険料と国民年金は払わないといけません。
妻が130万円を越えるなら、確認が必要

妻の年収が130万円を超える場合、勤務先によっては社会保険加入の対象になる可能性があります。
社会保険に加入すれば、厚生年金の積み立てが増えるというメリットがある一方で、毎月の社会保険料が差し引かれます。
ここは「手取りが減るのか、それでも長期的に得なのか」を判断する必要があります。
結論。個人事業主の妻は「制限がない」と考える

実は、個人事業主の配偶者には「年収の上限」がありません。
扶養という概念がないので、理論的には年収1000万円でも働き続けられるんです。
ただし、税金と保険料が発生するだけです。
つまり「扶養から外れるか外れないか」で考えるのではなく、「税金と保険料の負担がいくらまで増えるのか」で考える方が正確なんです。

わぁ、制限がないってこと!?なんだか自由だ〜!

そういうことだにゃ。ただし負担は増えるから、計画的に稼ぐのが大事だにゃ!
個人事業主の妻が確認しておくべき手続き
個人事業主の配偶者として働く場合、いくつか確認しておくべき手続きがあります。
国民健康保険に自分で加入する

個人事業主の妻は、扶養ではなく自分で国民健康保険に加入する必要があります。
市区町村の国民健康保険窓口で手続きをしましょう。
パート先の社会保険加入要件を確認する

年収が130万円に近づいてきたら、勤務先で社会保険加入要件に該当するかどうか確認しましょう。
企業規模や勤務時間によって判断が異なります。
税務申告時に夫に相談する

夫が個人事業主の場合、年末調整や確定申告で配偶者控除の要件を満たしているか確認が必要です。
税理士や会計事務所に相談するのも一つの方法です。

個人事業主の妻が扶養から外れる年収の基準。正しい理解でスッキリしよう
この記事では、個人事業主の配偶者が「扶養から外れる年収」について詳しく解説してきました。
でも、一番大切なポイントをもう一度。

個人事業主の配偶者には「扶養という制度がない」。これが出発点です。
だから「扶養から外れる」という表現そのものが正確ではなく、正しくは「税金や保険料の負担が増えるラインはどこか」という発想が必要なんです。
個人事業主の妻だからこそ、「制限がない」という自由さがあります。
その代わり、年収が増えると税金や保険料も増える。
これをきちんと理解した上で、自分たちにとって最適な働き方を選んでいくことが大切です。
もし、これからパートで稼ぎたいと考えているなら、まずは夫と一緒に「今年はいくらくらい稼ぐのか」を相談しましょう。
そして、その年収に応じて、国民健康保険料や税金がいくらくらいになるのか、市区町村や税務署に問い合わせてみてください。
正確な情報を持つことが、最適な判断につながります。
個人事業主の妻としての働き方、自分たちに合ったペースで進んでいってください。
その先に、充実した人生が待っているはずです。

よかった。スッキリしたわ。これからは自信を持って働けそう!

その調子だにゃ!正しい知識を持つことが、一番の武器だにゃ!
「あと数万円稼げたのに…」「扶養を外れた方が実は手元に多く残ったのに…」
数年後にそう気づいても、過ぎた時間は戻ってきません。
今ならオンラインで、「あなたの場合、いくら稼ぐのが一番お金が貯まるか」をプロが無料で試算してくれます。
家計の健康診断だと思って、早めに一度チェックしてみてください。浮いたお金で家族旅行に行けるかもしれませんよ!
👉 【無料】何度でも相談OK!世帯年収を最大化するライフプラン相談はこちら![]()